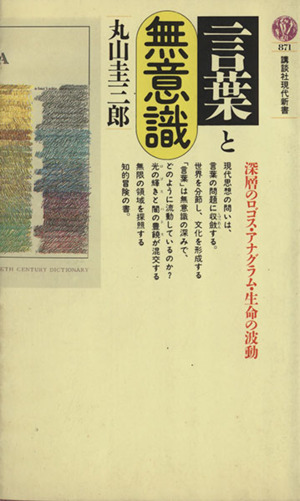言葉と無意識 の商品レビュー
多くの引用と共に、自分の考えが述べられているようである。 言分けという概念が、見分けという概念の対立概念として出てくるが、その定義が書いていない。言分けがもたらした文化の説明、言分けの説明に便利な逆ホメオスタシスの説明はあるが、その説明のどの部分が言分けであるかの説明がない。 ...
多くの引用と共に、自分の考えが述べられているようである。 言分けという概念が、見分けという概念の対立概念として出てくるが、その定義が書いていない。言分けがもたらした文化の説明、言分けの説明に便利な逆ホメオスタシスの説明はあるが、その説明のどの部分が言分けであるかの説明がない。 また、多くのフランス語やドイツ語などカタカナで書かれた語が出てくる、著者の博学ぶりが伝わる書き方がされているが、著者の言いたいことは伝わってこない。エピステーメーとして、ある分野においてははっきりと定義され共通認識がある語として確立しているからこそ、カタカナで示しているのだと思うが、哲学や精神分析学の門外漢たる私には、意味が分からない。ちゃんと説明をしてほしい。 同様にたくさんの論者を引用していて、多くの学者・哲学者・精神分析者・臨床心理学者の支持が得られる主張をしていることが分かる。ただ、それらの論者が、言葉を同じ意味で使っているのかについて、読者には知るよしもない。原著にあたってみないといけないだろう。彼らが何を根拠にそのような主張をしたのかについて、私はまったく知らないため、名前のすごそうな感じによって誤魔化されるか、あるいは、一旦根拠のない主張として受け取っておくしかない。根拠について語られることは、本書においては、ない。 著者は、本書のテーマとなっている無意識という語をフロイトの用いたそれとは違う意味で扱うことを宣言していて、それには定義や説明をしっかりとしている(だから、無意識について書かれている本として本書を手に取った人にとっては驚き、だまされたと感じることもあるだろう)。精神分析の立場で書かれた文章を引用するならば、それはかなり慎重を期さねばならなかっただろう。そうしているのだろうとは思うので、それは信用するしかない。 多くの引用が在り、たくさんのタームあるいはジャーゴンによって論が構成され、知的に深いレベルの議論がなされていることが感じられる。だが、それが人の生き方や考え方というレベルへと下りてくることが非常に希である。人が使う言葉と人の無意識についての議論がされているはずなのだが、それは言葉の上で示されるに留まることが多い。流動的に姿を変える、分節化しにくい私たちの一面を説明しているはずなのだが、言葉のみが上滑りしている印象を受ける。ロゴスにより表層構造をなぞるだけの本書は、深層構造にある分節化される以前の私たち人の本質に迫れているのだろうか。 「一般的に人は」と書かれる内容、著者の友人である会社経営者の言葉は、どれだけの人を納得させられるものなのかは分からないが、少なくとも私にとっては実感のない事例となった。そして、一般人に対する著者の理解は、確かめようと思えば確かめられることでありのだが(心理学の領域ではそれをしないで語ることは許されない)、確かめることはない。 ただ、ソシュールの人生の足跡と業績について書いた部分はすごく面白くて、ソシュールについてもっと知りたいと思わせる魅力があった。 以上を総括すると、新書として出すべき内容とは言えない。単体ではほとんど意味が分からないので、評価できない。被引用者について知っていないと、そもそもの主張を理解しがたいし、都合良くつまみ食いして自分の主張を裏付けている可能性を排除できない。ラカンやドゥルーズ、ソシュール、クリステヴァ、バフチン、フロイト、ユングといった大物をちゃんと理解している人が、丸山氏の一連の著作との関係において読むのが楽しみ方であろう。
Posted by
「言葉はどうやって習得されるのか」この本を読んで、改めて考えさせられた。 概念説明などはやや専門的でわかりにくいところもあるが、筆者が遭遇した電車内での子どものエピソードは実に微笑ましい。「ママ、デンシャって人間?お人形?」 こんな素朴な質問が言葉の概念の真髄を言い得ているので...
「言葉はどうやって習得されるのか」この本を読んで、改めて考えさせられた。 概念説明などはやや専門的でわかりにくいところもあるが、筆者が遭遇した電車内での子どものエピソードは実に微笑ましい。「ママ、デンシャって人間?お人形?」 こんな素朴な質問が言葉の概念の真髄を言い得ているのではないだろうか。「人間=動く、やわらかい」「人形=動かない、固い」、じゃ「動く&固い デンシャはどっち?」 という質問になるわけだ。幼い子どもの質問を意味のないこととしてしまうのは簡単だが、新しいカテゴリーの理解に困難を伴うというプロセスは語学習得を考える上で、必要な観点だと思う。
Posted by
読む前は4章「無意識の復権」に興味があったが、ラカンに絡めての説明のため、挫折気味になりつつなんとか読み進めた感じ。 動物と人間の差異を知ることによって何が明らかになるのかどうかは自分はよくわからないが、どうもにもうまく理解できなかった。 最終章は新書らしくてよかった。
Posted by
――ランガージュ[言語活動]は、ラング以前の象徴性の活動として、音声言語に先立つアルシ・エクリチュール(音声の代理ではない根源的文字、トーテム記号など)やコードなき舞踏としての身振りとも深く関わっている。(中略)そしてアルシ・エクリチュールと同様に、身振りは、象徴作用が生ずるプロ...
――ランガージュ[言語活動]は、ラング以前の象徴性の活動として、音声言語に先立つアルシ・エクリチュール(音声の代理ではない根源的文字、トーテム記号など)やコードなき舞踏としての身振りとも深く関わっている。(中略)そしてアルシ・エクリチュールと同様に、身振りは、象徴作用が生ずるプロセスの形とともにリズムを示していて、観念の代行・再現物ではない。文字も身振りも、ともにランガージュとしての、一切の指向対象をもたない<差異>なのである。(『言葉と無意識』丸山圭三郎)
Posted by
読み終えてみると、なるほど納得のタイトルと内容。ベースにある部分の話から、文化にまで話が派生する。思想を具体的に昇華するといえばいいのだろうか。ソシュールをベースにロラン・バルトが主にテキストや映像で展開したことの文化や生活観といった日常的な枠に反映させたものといえばいいかもしれ...
読み終えてみると、なるほど納得のタイトルと内容。ベースにある部分の話から、文化にまで話が派生する。思想を具体的に昇華するといえばいいのだろうか。ソシュールをベースにロラン・バルトが主にテキストや映像で展開したことの文化や生活観といった日常的な枠に反映させたものといえばいいかもしれない。芸術が、やや特殊、特別なことだという感じが拭えない中で(それが世間一般にとってごく自然な日常の活動になれば別だけど)文化や生活の観点から再認識する丸山圭三郎の語りはビフォーアフターのある読書になると思う。わかっていそうで留保していない、このソシュールベースの感覚は個人的には、いい意味で感覚をアンロックしてくれた気がする。
Posted by
言語学と心理学を繋いだ中間領域における既存研究の概説書のようなものだと思って買ったが、実際は思想書であった。予想外ではあったが、思想書だけあって掘り下げは深いし著者の熱量は感じられるしで大変面白かった。晩年の書ということで、著者の思想の総括的内容といえるのかもしれない。ソシュール...
言語学と心理学を繋いだ中間領域における既存研究の概説書のようなものだと思って買ったが、実際は思想書であった。予想外ではあったが、思想書だけあって掘り下げは深いし著者の熱量は感じられるしで大変面白かった。晩年の書ということで、著者の思想の総括的内容といえるのかもしれない。ソシュールの言語学を礎に言葉というものの考察から人間の精神活動および文化活動を統括的に説明し、西欧的科学合理主義を乗り越えようとするもので、個人的には結構ありかなと思えた。言葉の考察からここまで言えるのかとひとえに感動した。意識内だけに留まらず、意識外との関係にまで踏み込んでいるところが凄い(タイトルにある無意識も一般的用法と違ってこの意識外を指している)。卑近なところでは、精神病についても意識を形成する(というか意識そのものである)言葉という視点から捉え直していて興味深い。特に「均衡のとれた社会的人格を強制するのが治療であるとすれば、これは治療というよりは科学による新たな抑圧であるといわねばならないだろう。」との強烈な批判は一考に値するのではないかと思った。 という具合に興味深く刺激的な内容で満足しているが、やっぱり難しかった。特に3章と4章は読むのにかなり時間がかかった。新書だからと侮ってはいけない。
Posted by
『ソシュールの思想』など日本のソシュール研究のたぶん第一人者である丸山圭三郎が「言葉」と「無意識」について切り込んだもの。1987年の著作なので、ずいぶんと古いが、非常に魅力的なテーマのように思えたので読む。 だが、やや期待外れ。たとえばソシュールのアナグラムを高く評価するが、...
『ソシュールの思想』など日本のソシュール研究のたぶん第一人者である丸山圭三郎が「言葉」と「無意識」について切り込んだもの。1987年の著作なので、ずいぶんと古いが、非常に魅力的なテーマのように思えたので読む。 だが、やや期待外れ。たとえばソシュールのアナグラムを高く評価するが、共感できない。ラカンの「言葉こそが無意識の条件である。言葉が無意識を作り出すのだ」という言葉を紹介しているが、その主題となるべき無意識のテーマへの切り込みが浅いという印象を受ける。最近読んだジュリアン・ジェインズ『神々の沈黙』にも通底するような無意識に関する新しい視点が得られるかもなという期待もあったのだが、少なくともその点はダメだった。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
第一章が難しかったけれど第二章からついていけました。なんとか。総じて、この本は言語学者で構造主義の父と呼ばれるソシュールを中心にした言語論です。それもチョムスキーなどが扱う表層の言語論ではなくて、言葉の生まれる深淵までをも覗きみるタイプの言語学のやり方です。無意識の言語化っていう話が本書の結論部分にでてきますが、ぼくも数年前にユングを読んでそこに気づいていて、あらためてこの考えを深める契機となりました。無意識を意識化していくことによって、日常生活や幼少期に受けてきた抑圧から、自らを解放することができるのではないか、という考えです。そうすることで、ストレスなどの多い現代において、精神面で病んでしまうことが減るように、もっと言えば、病んでしまった心が癒えるように、とする考えです。
Posted by
ソシュールの一般言語学講義ではなく、アナグラム研究を素材として、ロゴスとパトスの問題から治療論にまで至る野心的試みで、新書には収まりきらない密度。各界からの引用も豊富で十分な刺激を与えられる。岸田秀の「コンプレックス」に関するこういう見解は今まで知らなかったが、これは早速頂きであ...
ソシュールの一般言語学講義ではなく、アナグラム研究を素材として、ロゴスとパトスの問題から治療論にまで至る野心的試みで、新書には収まりきらない密度。各界からの引用も豊富で十分な刺激を与えられる。岸田秀の「コンプレックス」に関するこういう見解は今まで知らなかったが、これは早速頂きである。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
ロゴスとは、名づけるることによって異なるものを一つのカテゴリーにとりあつめ世界を有意味化する根源的な存在喚起力として捉えられていた。ギリシャ語のパトスは、ふつう<情念>と訳されるが、これは同時に、一見全くことなった概念と思われそうな<受けること、被ること>ひいとは<受苦>や<受難>という意味を持っていた。孔子は「知る者は好むものに及ばず、好む者は喜ぶものに及ばない」と言っていたが、「読み、書き、生きる」行為が一つに重なる私たちの深層意識においては、ロゴスはパトスであり、パトスはロゴスであるからだ。
Posted by