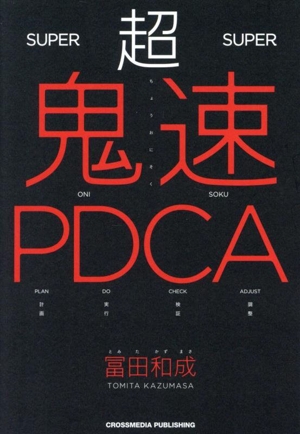商品詳細
| 内容紹介 | |
|---|---|
| 販売会社/発売会社 | クロスメディア・パブリッシング/インプレス |
| 発売年月日 | 2025/03/28 |
| JAN | 9784295410645 |
- 書籍
- 書籍
超鬼速PDCA
商品が入荷した店舗:店
店頭で購入可能な商品の入荷情報となります
ご来店の際には売り切れの場合もございます
オンラインストア上の価格と店頭価格は異なります
お電話やお問い合わせフォームでの在庫確認、お客様宅への発送やお取り置き・お取り寄せは行っておりません
超鬼速PDCA
¥1,848
在庫あり
商品レビュー
4
2件のお客様レビュー
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
本書の初版は読んだのですが、「とにかく高速でPDCA」くらいしか記憶がなかったので、再読もかねて読了。 タイトル通り鬼速でPDCAを回すというのはもちろんですが、組み立て方や各フェーズで抑えるべきポイント(ミッション達成に向けて有効なHow to)が書かれていました。 プラス昨今のAIを活用した課題発見⇒分析⇒解決策検討⇒具体的なToDoの整理も書かれていました。 日頃実践していることが多く書かれている反面、やはりCとAの部分に関しては意識的にやって習慣化していかないと、一朝一夕では身につかないと本書を通じて実感しました。 ちょうど自身の仕事としてその機会が多くなるので、チャレンジです。 ・PDCAは階層に分かれており、業務ごとに細分化することが可能。大目標⇒達成するための中目標⇒動かすための小目標。計画を細分化した分だけPDCAは存在する。(⚙のイメージ) ★PDCAの構築=ゴール・プロセス・How toを見える化。Doは細分化されるため、複数のPDCAがさらに存在するイメージ。各PHASEの理解とスピード感を持ったサイクル運用が必要。 ★まずはゴールを定量化(KGi設定)をする > 期日設定 > 定量化(事業計画と連動) > ゴールを適度に具体化する(1~3か月後) なお定量化はAs-is/To-beを軸にギャップから考える。定量的なことを抑えておく。 ★課題を優先順位付けする。 > インパクトの大きさ > 短時間の成果 > 気軽さ 全てをやろうとするのではなく、まずは優先度の高いもののみ対処する。各課題のKPI設定を行う。 ・解決案についても、上記と同様の3つ(インパクト・時間・気軽さ)にプラスして実現可能性を視野に入れてKPI設定を行う。なおKPI設定にあたっては、最低1つは設定する。 ・PDCAを回す前に定期的に背景/目的を振り返ることが必要。 ・自身が回しているPDCA(中~小)は会社のビジョン(=大PDCA)にマッチしたものになっているか? ・時に思考のリミッターを外して考察する。(極端な考え・アクション) ・問題解決の方法=プロセスの分解(cf.本の目次等)分解したプロセスに対して現状を把握し、出てきた課題に対して対策を考える。 ★Doを失敗する要因としては… > 計画自体が失敗している > タスクレベルまで落とし込まれない > 失敗への恐怖 ⇒ 計画で終わらせず、具体的なアクションに落とし込む/実行可能なレベルで分解する/行動ファースト・失敗の許容 ★KDI=どれだけ計画を実行できたか? ⇒ ラップタイムの設定(month/week)具体的な数値に落とし込む。 実行するプロセスを細分化し、ToDoリスト化(6w3h)し、進捗確認 実行するプロセスにおいて「人」に影響するリスクを十分に考慮する。(相手・チームの弱みを理解して、予めヘッジをかけておく。)⇒コミュニ―ケーションでカバー ★PDCAの継続力を自ら作り出す キーワード ー 目的意識 ー 成果発出 ー 心理的障壁の低さ ー 明確なアクション方法 ⇒ 意志ではなく、知恵と仕組みでカバー ・Checkで失敗するパターン > 検証しない > 検証しかやらない ⇒ KGIの達成率、KPIの達成率、KDIの達成率 ⇒ それぞれの観点で課題を定量的に分析し仮説⇒検証、Ajustしていく。 ・特にKPI・KDIは未達の要因を突き止めること(反対に達成できた要因も) > 行動未達 > 行動量は達成しているが、成果なし > 想定外の課題 > KPIとKDIが連動していない(仮説の誤り) ・Ajust=調整案 > ゴールレベルの庁瀬(中止・変更・追加) > 計画の大幅な見直し > 解決案・Do・Todoレベルの調整 > 調整不要 ⇒ やることの優先順位を組み替える ・Check&Ajustで起こる間違い > 新しいものに目移りしやすい(今やっていることを見直す) > 間違ったものばかりに目が行く(良いモノ・コトも見る) > 意見の統一が図れない(責任の所在の明確化) > 課題のたらい回し > プロセスの可視化が不十分(判断に至ったプロセス) ・AI活用⇒プロンプトのマスターが必須。質問を段階的かつ徐々に具体化していく。ゴール設定⇒課題分析⇒課題設定⇒解決策検討⇒解決策設定を一連化するため、壁打ちするイメージ。
Posted by 
PDCAサイクルを「超鬼速」で回す 継続できなければ効果は望めない 課題がないのは行動をしていない証拠 情報価値が低下する現代において、ますます価値が上昇するビジネススキル 小PDCA、中PDCA、大PDCAが入れ子構造のように回っている 鬼速で前進を続ける限り、新たな課題は常に...
PDCAサイクルを「超鬼速」で回す 継続できなければ効果は望めない 課題がないのは行動をしていない証拠 情報価値が低下する現代において、ますます価値が上昇するビジネススキル 小PDCA、中PDCA、大PDCAが入れ子構造のように回っている 鬼速で前進を続ける限り、新たな課題は常に現れる 立ち止まることはチーム全体のスピードを鈍化させる ゴールは適度に具体的なものにする 理想的な期間設定は3ヶ月後くらい ゴールから逆算して「自分は何をすべきか?」 得意分野を強化することも立派な課題 要因分解が不可欠 本当に取り組むべきボトルネックが浮き彫りになる プロセスで分解することが最も確実で簡単な方法 課題の優先順位付け、最重要基準はインパクト(効果) 事前にリスク、将来的に起こりうる課題を想定できるか 「タスク化」が不十分なまま進めて失敗するケースが多い 時間を資本と捉える 時間の棚卸し 重要・緊急マトリクスで**「捨てる」Doを見つける** 最低限の方向性を固め、動きながら仮説を補強するスタンス **「行動ファースト」**でやるしかない 仮説は修正するためにある ToDoの進捗確認は実行フェーズに含まれる 検証フェーズではKDIやKPIを扱うべき 「できなかった要因」だけでなく、「できた要因」も突き止める 成功パターンをレシピ化する **「想定ラップタイム」**を設定し、テコ入れ策を検討する AI活用による検証の高速化 次のサイクルに活かす学習とナレッジ蓄積 「P→D→C→A→D→C→A…」とスピーディーに回る PDCAの肝は「継続する」こと 仕組み化: 意志力は弱いが、知恵でカバーできる 迷わないためのシンプルなマイルール 15分ミーティング 「捨てる会議」 週報は組織と自分自身の前進を確認する強力な仕掛け AI活用でPDCAサイクルは**「超鬼速」**にアップグレード **「的確な指示(プロンプト)」**がAI活用で重要 「前進を続ける人生の方が絶対的に楽しい」
Posted by