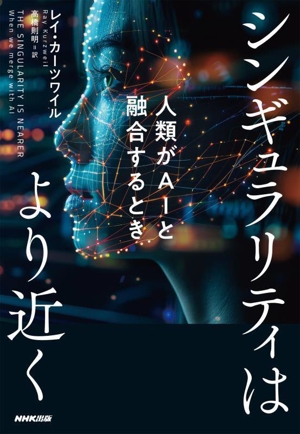

商品詳細
| 内容紹介 | |
|---|---|
| 販売会社/発売会社 | NHK出版 |
| 発売年月日 | 2024/11/25 |
| JAN | 9784140819807 |
- 書籍
- 書籍
シンギュラリティはより近く
商品が入荷した店舗:店
店頭で購入可能な商品の入荷情報となります
ご来店の際には売り切れの場合もございます
オンラインストア上の価格と店頭価格は異なります
お電話やお問い合わせフォームでの在庫確認、お客様宅への発送やお取り置き・お取り寄せは行っておりません
シンギュラリティはより近く
¥2,640
在庫あり
商品レビュー
4.2
29件のお客様レビュー
未来予想学者として著名なレイ・カーツワイル氏によるAI、ナノテクロジーなどの技術によって社会、人間がどのように変容していくかを論じた一冊。 テクノロジーの進歩は寿命の延長、大脳新皮質のクラウド、脳自体の機能拡張などの正の側面もあるが、戦争や犯罪などの負の側面も大きくなる可能性が...
未来予想学者として著名なレイ・カーツワイル氏によるAI、ナノテクロジーなどの技術によって社会、人間がどのように変容していくかを論じた一冊。 テクノロジーの進歩は寿命の延長、大脳新皮質のクラウド、脳自体の機能拡張などの正の側面もあるが、戦争や犯罪などの負の側面も大きくなる可能性がある。 しかし、著者は「慎重かつ楽観的な姿勢」で未来を受容すべきであると語っており、この姿勢は興味深いです。 過去のテクノロジーの進化を見ても、失業者の増加などの経済的な側面や、人間の倫理観的な問題などの議論が起き、その結果として社会に溶け込んでいることを考えると、進歩した未来の魅力に人類は抗えないのではないかと感じます。 ここに記された内容の全てが実現するわけではないと思いますが、現在進行形で進んでいる各分野のテクノロジー進歩や、これから起こりうる可能性に備え、何を考えておかなければならないかという気持ちにさせてくれる一冊でした。
Posted by 
全体を通じて進歩史観と楽観がこれでもかと出ている。そう考える論拠はそこそこ揃っており、まぁそういう未来もあり得るかもなと思わせる。 ただ、4章の統計データは絶対額で見せるべきでないものも絶対額で見せている気がする。またカーネマンやピンカーといったビッグネームとのやり取りがちょこち...
全体を通じて進歩史観と楽観がこれでもかと出ている。そう考える論拠はそこそこ揃っており、まぁそういう未来もあり得るかもなと思わせる。 ただ、4章の統計データは絶対額で見せるべきでないものも絶対額で見せている気がする。またカーネマンやピンカーといったビッグネームとのやり取りがちょこちょこ出ているが、文脈的にそこまで必要か(アピール?ちなみにカーネマンの主張の方が個人的には腹落ちした)とも思い、これらの感じはあまり好みでは無かった。
Posted by 
面白〜い! 以下、興味深かったところのメモ。 ・シンギュラリティ(特異点)は、数学と物理学で使われる言葉で、他と同じようなルールが適用できなくなる点を意味する (この言葉を作ったのが作者らしい!) ・1956年にスタンフォード大学教授のマッカーシーの呼びかけで研究会が行われた...
面白〜い! 以下、興味深かったところのメモ。 ・シンギュラリティ(特異点)は、数学と物理学で使われる言葉で、他と同じようなルールが適用できなくなる点を意味する (この言葉を作ったのが作者らしい!) ・1956年にスタンフォード大学教授のマッカーシーの呼びかけで研究会が行われた。この研究会に備えて、マッカーシーは、人工知能と呼ぶことを提案した ・AIは言葉の意味を、文法規則の本や辞書からではなく、実際に使われている文脈から学ぶ。例えば、ジャムを食べる、ギターのジャム(即興演奏)の使い方を文脈で学ぶ。AIの学習法は、私たちが言葉を学ぶのと全く同じ。 ・googolゴーゴルは、1の次に0が100個も続く桁数を意味する(あのインターネット企業はこの単語のスペルを間違えた)、 (と記載されてるけど、わざとだと思ってた。でも、この作者、ここで働いてたんだよね?だから、正しい情報なのかな?( ºロº)) ・2040年代初めには、ナノロボットが人間の脳の中に入って、その人のデータ全てをコピーできるだろう。あなた2号の登場だ。 (これが日本の内閣府が目指してるムーンショット計画のアバターの作り方なのかな?どうやるのかとずっと不思議に思ってたんだけど。) ・ひとたび人類が太陽光などの安価なエネルギーを得て、AIロボットを開発したら、多くのものがコピーできるようになるので、それらを暴力で奪い取ることは馬鹿らしくなるだろう。情報テクノロジーの進歩は社会に大きな前身をもたらすだろう。 ・2020年代後半には3Dプリンターで衣服や日常品がプリントでき、コストは1ポンド辺り数ペニーにまで安くなるだろう (7–18 yen per kgかな?) ・寿命を、大きく延長するものは、私たちの本質的な部分をバックアップする能力。デジタルの脳は私たちの思考の全てをバックアップできる。シンギュラリティに近づく2040年代半ばに現実になるだろう (万博落合陽一さんnullnullと繋がる!!) ・最終目標は、いつまで生きるのかを自分で決めること。 ・進行中の社会的転換を楽観視する最も重要な理由は、物質的な豊かさが増せば、暴力に走る動機が弱くなることにある。 ・2030年代にはブレイン・コンピューター・インターフェースが実現するだろうが、機械で増強した人間が意思決定をするときに、「人間の管理」における「人間」とは、最終的に何を意味するのかが問題になるだろう (攻殻機動隊みたい( ºロº))
Posted by 

