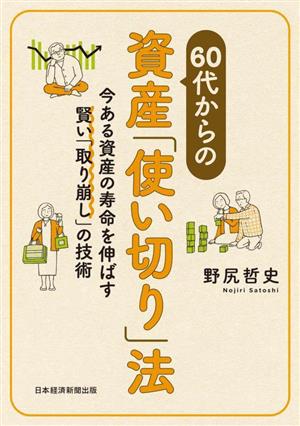

商品詳細
| 内容紹介 | |
|---|---|
| 販売会社/発売会社 | 日経BP/日経BPマーケティン |
| 発売年月日 | 2023/08/25 |
| JAN | 9784296118175 |
- 書籍
- 書籍
60代からの資産「使い切り」法
商品が入荷した店舗:店
店頭で購入可能な商品の入荷情報となります
ご来店の際には売り切れの場合もございます
オンラインストア上の価格と店頭価格は異なります
お電話やお問い合わせフォームでの在庫確認、お客様宅への発送やお取り置き・お取り寄せは行っておりません
60代からの資産「使い切り」法
¥1,760
在庫あり
商品レビュー
3.2
14件のお客様レビュー
親の資産活用のために手に取った本。 これは当事者(親本人)のための本ですね。 サポートしたいと思っている子としては物足りなりなさがありましたが、一読してから親に勧めてみるという使い方なら悪くないのかも。
Posted by 
老後の「資産活用」について分かりやすくまとめられている。 ま、正直、「使い切る」ほど資産はないのだが・・・
Posted by 
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
日経新聞の記事で興味を持って 予測<計画 昨今のコストプッシュ型インフレ、トランプ関税など不確定要素が多いので、 予測しようと思ってもできない。ならば計画というのはとても現実的。 生活費=勤労収入+年金収入+資産収入 勤労収入: 長く働くために 継続雇用で良いのか? ・これまでできなかったこと/やりたかったこと 積立+運用 ⇒ 使いながら運用 ⇒ 使うだけ(80歳~) 年金収入: 繰下げ受給: 〇高齢時に少しでも多く安定した終身年金を受け取れる安心感 資産が減るほど取崩恐怖が増す 〇受給総額が増える 〇働いていたら所得税が少ない ✖受給年齢まで大幅に資産を取り崩すことに気持ちが耐えられるか? ✖市場が悪いときに安心していられるか? ✖心配から少しでも若いときに時間を楽しめないのでは? もっと動けなくなる前に「デザート」時間を楽しみたい 繰上げ受給: 〇資産に余裕があれば自分で運用できる 〇若いときに楽しめる 旅など 〇資産の取崩・減り方が緩やかになる ✖働いていたら所得税が多くなる ✖上記確定拠出型年金と公的年金が合算されるので、勤労収入の抑制圧力になる ✖総受給額が少なくなる ✖高齢時の安定収入が少ない 終身年金は大きい 自称「金融リテラシーが高い」人ほど詐欺被害に 収益率配列リスク:Sequence of returns risk 収益率の平均が同じでも、取崩初期にマイナス収益率だとトータル成績が悪くなる 相場の悪いときに引退=取崩開始すると、資産が足りなくなる可能性 ⇒結局長く働く?/現金資産を多めにする?(運用成績が悪くなる) できるだけ前半にはバッファー資産から使うのもあり(最初の5年を預金取崩だけにする) ⇒このバッファーを低リスクで運用するアイディアは難しいと考えるので同意できない。 資産運用において5年は短期。現金か個人国債がベター。 資産を長く持たせるには、「安く買って、高く売る」 相場が悪いときには取崩額を減らす そのために、長く働くしかないのか?/配当株を増やすか?=入金力 率で取崩す: 3%で運用して4%取崩す、という著者の案には、運用が不確定だから同意できないが、 「使うだけの時期」に残す資産額から取崩しを決めるのは同意。 引き出し率を徐々に上げていく 例)65歳~3% 70歳~4% 80歳~5% 米国の確定拠出年金の引き出しルールが元ネタ RMD:Required Minimum Distribution 最低引き出し制度 IRA:Indivisual Retirement Account 個人退職口座 年齢ごとに残りの配分年数お決め、その配分年数の逆数を引き出し率として使う 120歳で残り年数を2年としている 以下、自分で調べた配分年数 IRSが定める「統一配分表(Uniform Lifetime Table)」に基づく年齢ごとの配分年数 年齢ごとの配分年数(Distribution Period) 年齢 配分年数(分配期間) 72 27.4 73 26.5 74 25.5 75 24.6 76 23.7 77 22.9 78 22.0 79 21.1 80 20.2 81 19.4 82 18.5 83 17.7 84 16.8 85 16.0 86 15.2 87 14.4 88 13.7 89 12.9 90 12.2 91 11.5 92 10.8 93 10.1 94 9.5 95 8.9 96 8.4 ...以下略... 計算方法:80歳 1÷20.2=4.95% 80歳で使うだけの時期とする: 残り試算を20で割って定額で使う ←例えば、80歳で年金にプラスして10万/月欲しい場合 10×12か月×20年=2400万円 80歳の目標残高を2400万円とする 生活スタイルと資産の取崩 前半重視: 健康寿命があるうちに楽しく過ごす 後半重視: 身体が弱った時に使う:介護、リフォーム、有料老人ホーム、家事サービス
Posted by 



