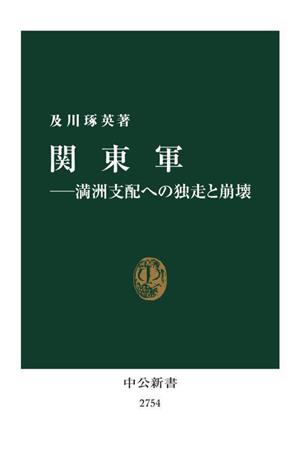- 書籍
- 新書
関東軍 満洲支配への独走と崩壊
商品が入荷した店舗:店
店頭で購入可能な商品の入荷情報となります
ご来店の際には売り切れの場合もございます
オンラインストア上の価格と店頭価格は異なります
お電話やお問い合わせフォームでの在庫確認、お客様宅への発送やお取り置き・お取り寄せは行っておりません
関東軍 満洲支配への独走と崩壊
¥1,012
在庫あり
商品レビュー
3.6
9件のお客様レビュー
”独走” の代名詞として悪名高い関東軍の成立から崩壊までを通史として叙述。 本書で著者は、次の3点を意識して論じたという(まえがき)。 第1:関東軍を取り巻く制度的環境~戦場では予測不可能なことが起こり得るため、指揮官には上官の意図を忖度しつつ臨機応変に対処することが求め...
”独走” の代名詞として悪名高い関東軍の成立から崩壊までを通史として叙述。 本書で著者は、次の3点を意識して論じたという(まえがき)。 第1:関東軍を取り巻く制度的環境~戦場では予測不可能なことが起こり得るため、指揮官には上官の意図を忖度しつつ臨機応変に対処することが求められていたことから、日本陸軍では独断専行が奨励されており、関東軍もそうであった。しかしながら国家機関として、法令や予算による制約があった。そうした中で政府や陸軍中央の思惑を超えて謀略を続け、独走へと至る構造的背景は、いかに形成されたのか。 第2:軍司令官や参謀長、参謀など関東軍軍人の個人的特性~官僚組織である以上人事異動があるが、各人によってどのような特徴があり、作戦や謀略を主導し、満洲国統治に関わったのか。 第3:満洲現地勢力の存在~満洲支配のためには現地勢力の協力は欠かせない。日本からの視点だけではなく、中国東北からの視点により跡付けることが重要。 「満蒙は日本の生命線」と言われたように満蒙に執着した戦前日本であったが、その歴史的経緯や関東軍が果たした役割が詳細に述べられていて大変勉強になった。 関東軍独走について、満洲事変にせよノモンハン事件にせよ、なぜあそこまで強気で行けたのだろうとかねてから疑問に思っていたのだが、その前段階として個別の戦闘での勝利体験等があったからこそ、”次も大丈夫、行ける、強気で攻めるのが大事”といった意識が作戦参謀等に蔓延していたからだったのかと、納得できた次第。
Posted by 
どうして日本がアメリカと戦争することになったかというと、日本が満州事変以降の中国侵攻を行ったことが相当のところ影響している。では、どうして満州事変が起きたかというと、大恐慌以降の世界と日本のマクロ情勢があるわけだが、ミクロ的には関東軍が政府や陸軍の意思を放れて、独走したからという...
どうして日本がアメリカと戦争することになったかというと、日本が満州事変以降の中国侵攻を行ったことが相当のところ影響している。では、どうして満州事変が起きたかというと、大恐慌以降の世界と日本のマクロ情勢があるわけだが、ミクロ的には関東軍が政府や陸軍の意思を放れて、独走したからというのが大きい。 というわけで、関東軍がどうしてそういう体質になったのか、具体的にどういう意思決定のプロセスがあったのかが知りたくなる。 いろいろな本でこのあたりのことは触れてあるのだけど、関東軍だけにフォーカスした本を読むのは初めてになる。ある程度の大きなところは知っているつもりだったが、読んでみると知らないこと、知らない人だらけでびっくりした。 程度の違いはあっても、関東軍も陸軍全体もシビリアンコントロールの効かない組織なんだなと思う。で、関東軍は、陸軍本体のガバナンスも効かないというのも、そのパラレルな現象なんだな。 これが戦前日本のガバナンス状態だったんだと思う。このシステムにおいては、天皇自身も軍や政治をガバナンスできない。戦前日本は、ファシズム国家であっても、断じて全体主義国家ではない。軍部もそうだけど、それ以外のメジャーなプレイヤーが好き勝手にやっていて、バラバラなわけで、全体的な統制とは逆の状態と言える。 それでも何が全体をホールドしていたかというと、国体思想なんだろうと思う。天皇自身はガバナンスできないにも関わらず、思想によってまとまっている。 思想といっても、その解釈の幅はかなり広いわけで、天皇はきっとこう考えているはずだとか、中央では現地の状況はわからず変なことを言っているが、彼らの現場を見れば同様の判断するであろうということで、下剋上、アナーキーな状態に進んでいったんだろうと思う。 そして、事後でそうした命令違反がわかっても、結果がよければお咎めなしだったのが、よりアナーキーを進めたということなんだな。 まあ、そういうことはこの本を読む前から分かっていたのだが、具体的な状況、具体的な人物が出てくると、よりリアルに感じることができた。 新書の入門書というよりは、研究書に近い感じかな?先行の研究で整理されているところは記述がサラッとしていて、著者が中国側の資料も踏まえて調べたところが中心になるので、関東軍関係の本を初めて読む人にとってはやや難しい印象だった。
Posted by 
及川琢英著『関東軍 : 満洲支配への独走と崩壊 (中公新書 ; 2754)』(中央公論新社) 2023.5発行 2023.1.30読了 関東軍といえば、日本史で必ず習うあの事件の首謀者として悪名高い。 張作霖爆殺事件は関東軍参謀の河本大作らが、満洲事変は関東軍作戦参謀の石原...
及川琢英著『関東軍 : 満洲支配への独走と崩壊 (中公新書 ; 2754)』(中央公論新社) 2023.5発行 2023.1.30読了 関東軍といえば、日本史で必ず習うあの事件の首謀者として悪名高い。 張作霖爆殺事件は関東軍参謀の河本大作らが、満洲事変は関東軍作戦参謀の石原莞爾らが起こした謀略として記録されている。 陸軍中央や政府の命令を無視して独断専行で動き、そのことがむしろ奨励されるような風潮を生み出し、その後の日中戦争や太平洋戦争の遠因となった。 先行研究としては、島田俊彦氏の『関東軍』をはじめ多くの研究があるが、これまでの研究では、関東軍自体の組織的特性や満州国との関わりが十分に明らかにされてこなかったという。 そこで、本書では、特に関東軍の組織的特性や軍司令官の個人的特性、満州現地勢力と関東軍の関わりについて筆をさいている。 例えば、関東軍が誕生する以前から、日本軍と満洲現地勢力との間には密接な関係があり、互いに利用しあう関係にあった。謀略レベルにおいては、関東軍成立以前から陸軍中央や政府の方針に背く工作が行われていた。 また、関東軍の行動を制度的に抑える手段が奉勅命令(あるいは臨参委命)しかなく、関東軍の実際の統制は、軍司令官の手腕にかかっていた。本国から送られてきた軍司令官が、強硬論を唱えるエリート参謀らをいかに統率していくかが重要だった。しかし、中央の方針と違っても、作戦が成功さえすれば出世できるという風潮が軍司令官による統制を困難にさせていた。 本書は以上のような問題意識を出発点にしているため、日本の外交や戦争の展開と関連付けた記述は少ない。 事実だけを淡々と記述していくような文体もあって、感情の起伏に乏しい、やや面白みにかける部分があるのも確かだが、膨大な史料に裏付けられた信頼ある研究であることは間違いない。今後の関東軍研究の基本書になっていくことだろう。 https://ndlsearch.ndl.go.jp/books/R100000002-I032810199
Posted by