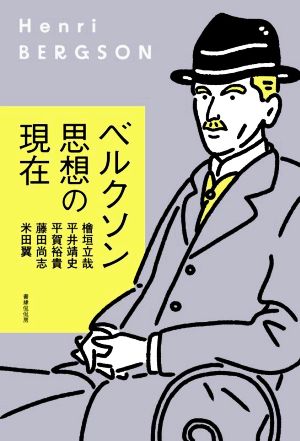
- 新品
- 書籍
- 書籍
- 1215-02-10
ベルクソン思想の現在
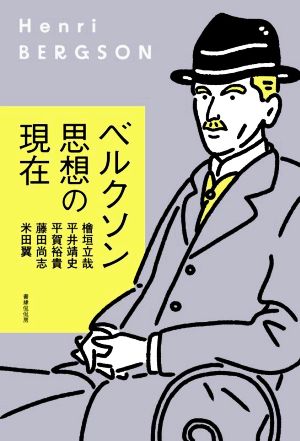
1,980円
獲得ポイント18P
在庫なし
発送時期 1~5日以内に発送

商品詳細
| 内容紹介 | |
|---|---|
| 販売会社/発売会社 | 書肆侃侃房 |
| 発売年月日 | 2022/12/23 |
| JAN | 9784863855564 |
- 書籍
- 書籍
ベルクソン思想の現在
商品が入荷した店舗:店
店頭で購入可能な商品の入荷情報となります
ご来店の際には売り切れの場合もございます
オンラインストア上の価格と店頭価格は異なります
お電話やお問い合わせフォームでの在庫確認、お客様宅への発送やお取り置き・お取り寄せは行っておりません
ベルクソン思想の現在
¥1,980
在庫なし
商品レビュー
5
2件のお客様レビュー
稀代のベルクソン研究者5人がベルクソンの主著4冊について交わした討論を纏めた一冊 広い領域に亘ってイマージュを用い人間について明晰な議論を打ち出してきたベルクソンの思考の片鱗だけでも窺えたような気がする 機械論にも目的論にも還元せずに人間の可能性について向き合うことに真剣だっ...
稀代のベルクソン研究者5人がベルクソンの主著4冊について交わした討論を纏めた一冊 広い領域に亘ってイマージュを用い人間について明晰な議論を打ち出してきたベルクソンの思考の片鱗だけでも窺えたような気がする 機械論にも目的論にも還元せずに人間の可能性について向き合うことに真剣だったベルクソンの気持ちが強く伝わってきた 従来の研究だけでなく最新の研究についても触れられているし、「持続」などの主要概念についても触れられているからどの読者にも刺さると思う ベルクソンという難解な哲学者へのアプローチの第一歩として間違いない良書 イマージュや持続などの、一見わかったつもりになれる概念を分析することで理解できなくした後に、上手く例を使ってまた分からせてくれる 正直この本の著者が書いたベルクソンの本を読むよりも、一般人を対象にしているためこの本の方がわかりやすい 事典としても使える
Posted by 
アンリ・ベルクソン。私が若いとき、ノーベル文学賞受賞者の代表作をアトランダムに読んでいた時期があって、ベルクソンの主著の1つの「時間と自由」を岩波文庫(青版)で読んでみた。まったく歯が立たなかった。数十ページ(いや十数ページ?)で挫折した。「直観」の人の論理構成の歩調に、私はまっ...
アンリ・ベルクソン。私が若いとき、ノーベル文学賞受賞者の代表作をアトランダムに読んでいた時期があって、ベルクソンの主著の1つの「時間と自由」を岩波文庫(青版)で読んでみた。まったく歯が立たなかった。数十ページ(いや十数ページ?)で挫折した。「直観」の人の論理構成の歩調に、私はまったくついて行くことができなかった。 十数年の時を経て、新聞で近頃のベルクソンへの注目の高まりとこの本を紹介する記事を見て、当時の屈辱を返上すべく本書を手に取ってみた。 この本は5人の日本人研究者が各専門分野からベルクソンをフランクに語るという構成。学会発表のような固さはなく、例えると将棋で対戦終了後に自戦解説するような程よい力の抜け具合だ。論文形式ではなく話し言葉なので私でも少しは理解できるかなという期待が生じた。 まあ、それは半分当たり、半分ハズレというところ。ハズレなのは、ベルクソンの思想体系はやはりつかみ切れなかったこと(悲)。当たりなのは、5人の研究者の“哲学そのものへの人生の賭け方”が興味深く読めたこと。それは5人が各自の自著を語る形で自身とベルクソンとの関係性を述べた序章ですでに読める。 まず最年長の檜垣立哉さんはこう書く。「そこには時代の焦燥感のようなものがこめられているとともに、明らかに来るべき21世紀の思考を可能にするポテンシャルを充分に予見させていた」。そして私に染み込んできた檜垣さんの一言-「極限的にいえば哲学の本は少数のわかってくれるひとがわかってくれればよい」。 ここで私のスタンスは定まった。つまりベルクソンを読んでわからないで終わるのではなく、未来につながる方向を自分なりに知覚して姿勢をしっかりと定め、静かにベルクソンの語りを傾聴し続けること。そしてわかるかわからないかを気にするより前に、とにかく読み続けること。それは旅行に出かける前の計画の時点で旅行そのものの80%近くの満足を得られるのと同様に、いくら結果的にわからなくても、わかろうとすることによって哲学の80%は達成していると考えられるからだ。 次に平井靖史さん。平井さんは芸術大学油絵科在学中の卒業制作時点で「本格的に哲学を学ぶしかない」と考え、卒業後に他の大学の哲学科に学士入学した経歴をもつ。そのせいか、平井さんの発想には物事をビジュアライズしたような視点が見られ、ベルクソンが多用する「イメージ」の解析に適応していると思われる。そんな平井さんがベルクソンに出会った頃の正直な所感は興味深いので紹介しておきたい。 「私はあっけなく振り落とされた。『どうやっても無理』という類のわからなさに、初めて襲われたのである…どうやってもわからない、なんてことがあるだろうか。実際、あったのである」。 ベルクソン主著の1つ「道徳と宗教の二源泉」の魅力を語る平賀裕貴さんは、実際に会ったこともなく話として聞いただけの存在の「神秘家」にひとが憧憬を抱くという傾向を、ベルクソンは最も明晰に説明していると考える。しかも一般的な見地の対岸にある「機械」という概念を用いて。そのベルクソンが見いだした一般人には見えがたい領域にこそ真実が潜むと、平賀さんは研究を続ける。 藤田尚志さんは、ひとを行動へと駆り立てる動機に「呼びかけ」という概念を用いたベルクソンの思考に興味をもつ。また「この哲学を築き上げるためには大勢の思索家にさらに大勢の観察者が加わって、互いに補い矯め戒め合いながら、集団的かつ逐歩的な努力を続けるほかあるまい」というベルクソンの残した言葉の忠実な実行者として、ベルクソンの「呼びかけ」を受け継ぎ他の者へ呼びかけるべく堅実に活動をしている。ちなみに福岡で活動する藤田さんはProject Bergson in Japan(PBJ)の立ち上げの中心人物であり、この本が福岡の出版社から出された源流も彼に行き着くとも言い得る。 米田翼さんは5人のなかで一番若い。物事を化学の視点からアプローチする発想を好んだ米田さんは、自分が生まれ育った自然豊かな環境や多くの生き物の謎を化学の観点で解きたいと思うようになった。そして生命や宇宙や自然を化学で読み解く手法を模索するなかでベルクソンに出会った。生物の種がもつ絶対的な共通性があるなかで、個体性や差異が生じている事実を、ベルクソンの生命哲学を用いて解析しようとしている。生物の現在の姿や進化についてオルタナティブな姿を想像させる米田さんの発想はスリリングで、幼時に怪獣や宇宙人に夢中になった私の好奇心を大きくくすぐった。 …ここまでですでに文章が長くなりすぎて、肝心のところの、各研究者が語るベルクソン研究の要点にまったく触れられなかったのは私の至らなさだ。だがベルクソン初心者が本書を手に取るかどうかの指針くらいにはなるのかなと思っている。
Posted by 

