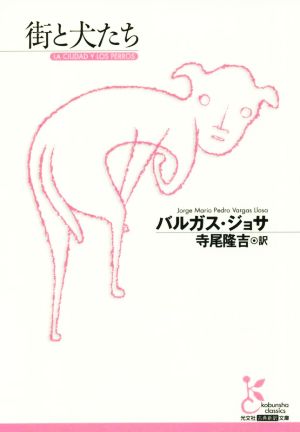

商品詳細
| 内容紹介 | |
|---|---|
| 販売会社/発売会社 | 光文社 |
| 発売年月日 | 2022/06/14 |
| JAN | 9784334754600 |
- 書籍
- 文庫
街と犬たち
商品が入荷した店舗:店
店頭で購入可能な商品の入荷情報となります
ご来店の際には売り切れの場合もございます
オンラインストア上の価格と店頭価格は異なります
お電話やお問い合わせフォームでの在庫確認、お客様宅への発送やお取り置き・お取り寄せは行っておりません
街と犬たち
¥1,694
在庫あり
商品レビュー
4.3
4件のお客様レビュー
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
解説読んでひっくりかえった。 後半のジャガーのキャラの立ち方がすさまじかったので、そう思っても仕方がないし、エピローグでもまたひっくり返った。お前かーい! 作者が奴隷を殺したのはジャガーと言っているのならそれが真実では!? 前半アルベルト、後半はジャガーが主人公だった。
Posted by 
ラテアメ文学ブームの幕開けを告げた『都会と犬ども』(新潮社)。 文庫本ないかなと思ってたら光文社で発刊されていた。タイトルがなんだかマイルドになっていて気づかなかったよぉ。 当時、『街と犬たち』は公序良俗にもとる描写、軍部の価値観と相反するということで、出版不可になったらしい。...
ラテアメ文学ブームの幕開けを告げた『都会と犬ども』(新潮社)。 文庫本ないかなと思ってたら光文社で発刊されていた。タイトルがなんだかマイルドになっていて気づかなかったよぉ。 当時、『街と犬たち』は公序良俗にもとる描写、軍部の価値観と相反するということで、出版不可になったらしい。たしかにね、600ページ越えのボリュームと、表現に辟易してなかなか読み進められなったけど、第一部の終わりのところから一気に面白くなってきた。 ペルーの軍人学校で放たれた1発の銃弾。少年たちが維持してきた牙城が密告によって崩れていくという、少年期から青年期くらいの危うさが描かれている。数人の視点での話が入れ替わり立ち替わり進んでいくけど、その中に「僕」がいて、「僕」とは一体誰なのか…。私はどこかでミスリードされてたようで、最後の最後でそうだったのか!となった。 全体的に粗野な雰囲気が流れていて、カオスな感じで終わるのかなと思ったら、意外にも静かで後味も悪くはない終わり方だった。 ちなみに本文中の差別的表現については、「これを避けることが暗黙の差別となる場合もあることを考慮して、そのまま用いている。」とあとがきにあって、今までで1番納得できる説明だった。
Posted by 
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
原題は「LA CIUDAD Y LOS PERROS」by MARIO VARGAS LLOSA 1963年発表。作者27歳。 杉山晃の訳……新潮社の単行本………「都会と犬ども」1987 寺尾隆吉の訳…光文社古典新訳文庫…「街と犬たち」…2022 新潮社版の訳者解説には重大なネタバレがあるらしいが、新訳のほうは配慮あり。 実際巧みな仕掛けに驚かされた。 解説から読むクチなので、新訳で読めてよかった。 視点人物が変わる小説には慣れっこだが、本作は単にカメラ位置がAさんなのかBさんなのかに留まらず、視点人物にカメラが寄り添うか少し上方から描写するか、という点から違う。結果一人称と三人称が入れ替わる。 それはまだわかるが、仕掛けがその中に紛れ込んでいるものだから、まんまと。 いわゆるラテンアメリカ文学のブームがドカンと来たガブリエル・ガルシア=マルケス「百年の孤独」1967の数年前。 バルガス=リョサでいえば「子犬たち」1959、「緑の家」1966に挟まれた、本作1963。 マジックリアリズムとは関係ないが、視点の切り替えなどは後の作品を準備したものだろう。 個人的な感想としては、「緑の家」「ラ・カテドラルでの対話」「密林の語り部」などよりも文脈依存度が低いぶん、親しみやすい、はっきりと青春小説ともいえる、入門書に合っていると思う。 いわゆる南米土着性が濃くないぶん、現代小説としても読み深められそう。 頭のいい白人のアルベルト(文屋=ブンヤというニュアンスだろう)、気弱な黄色人種リカルド(奴隷=ドレイくらいのニュアンス)、黒人のボアの馬鹿な感じ、ジャガーの悪ガキ、四角四面なガンボア、などキャラクター性が強いのもいいし、アルベルトがリカルドと話していて「こいつ友達になりたいんだろうな」と気づくあたりはBL風味も。 人物構図としては意外と、夏目漱石「こころ」の先生とKに似ているようにも思う。 ホモソーシャルな社会、女性を間に挟んだ(贈与対象とする)ホモセクシュアル、については石原千秋「謎とき村上春樹」で読んだ。 漱石ーリョサー春樹と横滑りに連想するのも面白い。 またテレサという少女が重要人物なのに、視点人物が96%、男性。 約80の断片のうち、テレサが視点人物になるのは、わずか3場面に過ぎない。 ここから読み換えていく……妄想を膨らませるのも面白そう。 おそらくラテンアメリカ文学の一部はもともとマチズモ批判でできていると思うが、さらにホモソーシャル批判という視点で読み直すのも、今ならできるのかも。
Posted by 



