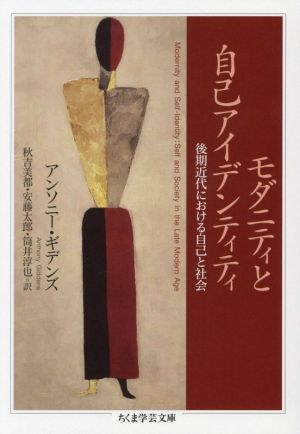

商品詳細
| 内容紹介 | |
|---|---|
| 販売会社/発売会社 | 筑摩書房 |
| 発売年月日 | 2021/08/12 |
| JAN | 9784480510631 |
- 書籍
- 文庫
モダニティと自己アイデンティティ
商品が入荷した店舗:店
店頭で購入可能な商品の入荷情報となります
ご来店の際には売り切れの場合もございます
オンラインストア上の価格と店頭価格は異なります
お電話やお問い合わせフォームでの在庫確認、お客様宅への発送やお取り置き・お取り寄せは行っておりません
モダニティと自己アイデンティティ
¥1,760
在庫あり
商品レビュー
3.5
4件のお客様レビュー
村上春樹作品、そして芥川賞受賞の羽田圭介「スクラップ・アンド・ビルド」、両作では男性主人公が日常を成立させ、自己肯定感を創出させ、満足感を得るための手段としてしばしば「筋トレ」が登場する。 「僕はリュックをかついで電車に乗る。高松駅に出て、それからバスでいつもの体育館に行く。ロ...
村上春樹作品、そして芥川賞受賞の羽田圭介「スクラップ・アンド・ビルド」、両作では男性主人公が日常を成立させ、自己肯定感を創出させ、満足感を得るための手段としてしばしば「筋トレ」が登場する。 「僕はリュックをかついで電車に乗る。高松駅に出て、それからバスでいつもの体育館に行く。ロッカールームでトレーニング用のウェアに着替え、MDウォークマンでプリンスを聴きながらサーキットをまわる。久しぶりだったので、身体は最初のうち悲鳴をあげる。しかし僕はなんとかそれをこなしていく。悲鳴をあげ、負荷を拒否することで、身体は正常な反応をしている。僕がやらなくちゃならないのは、その反応をなだめすかし、組み伏せていくことだ。僕は「リトル・レッド・コーヴェット』を聴きながら、息を吸いこみ、止め、吐きだす。息を吸いこみ、止め、吐きだす。それを規則正しく繰りかえす。筋肉を順番に限界の少し手前まで痛めつけていく。」 私は「筋トレ」が日常の成立・自己肯定感・満足感を創出することが常識であり真理であると確信して疑っておらず、今日この無味乾燥な一日を壊す刺激であると共に、老いへの抵抗、美への挑戦に資する取り組みとして受け入れている。 この真理の理論的裏付けがアンソニー・ギデンズ「モダニティと自己アイデンティティ」である。そう、日常の成立・自己肯定感・満足感の創出とは、すなわち自己アイデンティティの創出である。我々はしばしばそれは内面(誰を愛しどのような職業を選ぶか)に関わるものであり、「身体」を二次的な物として考えがちである。しかし、「服装」「髪型」或いは何を食すかについて考える時、「ダイエット」が頭をよぎらない現代人は珍しいだろう。ルッキズムはしばしば批判的な文脈で用いられるが、いくらそれを否定しようとも人々の美の追求、そのための資本の投入、あらゆる努力と節制、これらの隆盛は留まるところを知らない。整形、脱毛、ホワイトニング、ダイエット、筋トレ、骨格診断、メンズコスメ、日傘、パック、BMI、SPF、パーソナルカラー... 私の「自己アイデンティティ」「ライフスタイル」においても、哲学がどれだけ幅を利かせ読書が広い位置を占め、或いは投資に励み音楽に没頭したとしても、「身体的」なそれはいつ何時も圧倒的影響力を保っている。 これについて紐解く時、やはりその道標となるのはラカンの「鏡像段階理論」である。 鏡像段階理論とは、幼児期の子供はそれまで自らの身体を統一体だとは思っておらず、 鏡を見て初めてそれを認識するというものである。これの意味するところは、人間は鏡に映った自らの像に自らを「同一化」することで自らを認識、つまり自己を確立しているということである。 要するに、「自己アイデンティティ」の原点は精神や心ではなく「身体」にある。だからこそ、自己アイデンティティを語るにつけて、身体は決して二次的なものではあり得ないのである。 少し話を根本に戻すが、ギデンズによれば「自己アイデンティティ」は「信頼」を前提として成り立つ。これは自然に理解のできることである。「自己アイデンティティ」を持たざる人は不安に駆られ、自己の存在を信頼することができないだろう。或いは、より本質的に言えば先述の「鏡像段階理論」において、鏡に映った自らという、自らとは別の物、つまり他者を通して自らの身体を認識(自己を確立)するというプロセスが明らかにするように、自己の確立には他者の存在を要することから、他者との間に信頼関係を構築できない場合に、自己アイデンティティの創出に支障をきたすということは容易に想像がつく。なお、この他者との間の信頼関係の原点としてギデンズが言及しているのは、幼少期における、養育者からの愛情に満ちた関心である。この関心を通して、子の「基本的信頼」は発達する。信頼は他者によって達成され、自己アイデンティティは信頼によって成り立つ。他者→信頼→自己アイデンティティ。ここにおいて自己の確立は他者の存在に結びつくのである。 さて、自己アイデンティティにとって信頼が源であり、自己アイデンティティ創出にはしばしば身体が関わる。この時、以下のようなことが言える。 「能力ある行為者は、他の行為者から能力ある行為者であるとつねにみなされる行為者である。そのような人は身体のコントロールの失策を避けなければならない。万一、そのようなことが起きたとしても、「問題」はないことを身振りや間投詞によって他者に知らせなければならない」 つまり、我々は自らが信頼に値する人間であることを自らの身体によって他者に示し、他者からの信頼を得ることで自己アイデンティティを維持しているのである。筋トレとダイエットとブルベはそれぞれ、我々が他者の信頼を得ようとする時の懸命の努力の結晶なのである。
Posted by 
「再帰的」といい「内的準拠性」といい、社会学プロパー以外には馴染みにくい概念だ。近代は社会も人間も自分自身を反省しながら、繰り返し自らを作り変えていく。伝統社会にはないこの近代特有の性質が「再帰性」であり「内的準拠性」だ。反省は自分に帰ってくるから「再帰的」であり、反省の拠り所は...
「再帰的」といい「内的準拠性」といい、社会学プロパー以外には馴染みにくい概念だ。近代は社会も人間も自分自身を反省しながら、繰り返し自らを作り変えていく。伝統社会にはないこの近代特有の性質が「再帰性」であり「内的準拠性」だ。反省は自分に帰ってくるから「再帰的」であり、反省の拠り所は神や伝統といった自分の外にはなく、自分の内にしかないので「内的準拠」なのだ。 道具立ては手が込んでるが、本書はウェーバーが100年前に提起した合理化と意味喪失の問題を、人格(実存)にフォーカスした機能主義的システム論の枠組みで捉え直したものだ。言うまでもなく自由と実存的不安のジレンマは神を殺した近代の難題だ。ギデンズはなお近代への希望を捨てないが、自分らしい「ライフスタイル」の選択にアイデンティティ再建を託すのはあまりに楽観的だ。ギデンズも自覚するように、資本の論理に絡め取られるのがオチだろう。むろん、もはや世界が詰んでしまったという絶望の上に、よりましな世界の可能性の一つとしてならわからぬではない。 その限りにおいて、可能なるオプションとしては「伝統」も捨てたものではない。オプションであるからには「外的準拠点」にはなり得ない。だが分化した抽象的システムがローカルな世界を侵食しようとも、固有な時間と空間のナラティブとしての伝統は「小さな物語」くらいにはなる筈だ。その成否は伝統そのものよりも、伝統を支える人々の共同的な関わり合いにかかっている。これはライフスタイルの場合も同じだろう。本書にそうした視点が希薄なのは残念だ。実存的不安を個人主義的にとらえ過ぎている。 本書でありがたいのは訳者による充実した解題だ。単行本解題では初学者向けに本書の読み方を指南(細部に拘泥せず、ざっくりと4~7章を先に読め)した上で、本書の問題点を手際よく整理してくれる。文庫解題では原著出版以降の世界の変化をふまえて本書の議論の有効性を論じている。いずれも的確でとても参考になる。忙しい人は6、7章と二つの解題を読めばポイントはつかめる。
Posted by 
どこまでが役に立つかよくわからなかったが、リスクの考えでは卒論の役には立つと想定される。 あとがきで、どこを読むようにと訳者が解説しているのでそれを先に読んでから読む方針をたてるとよいと思われる。
Posted by 



