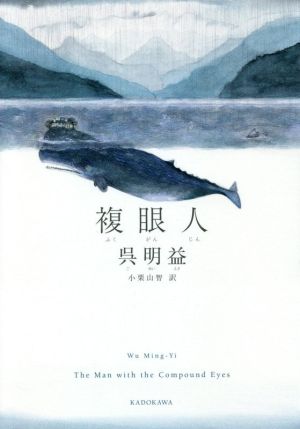
- 新品
- 書籍
- 書籍
- 1222-01-02
複眼人
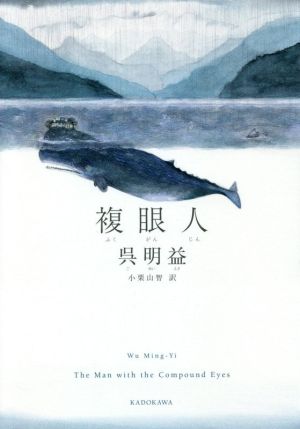
2,420円
獲得ポイント22P
在庫なし
発送時期 1~5日以内に発送

商品詳細
| 内容紹介 | |
|---|---|
| 販売会社/発売会社 | KADOKAWA |
| 発売年月日 | 2021/04/05 |
| JAN | 9784041063262 |
- 書籍
- 書籍
複眼人
商品が入荷した店舗:店
店頭で購入可能な商品の入荷情報となります
ご来店の際には売り切れの場合もございます
オンラインストア上の価格と店頭価格は異なります
お電話やお問い合わせフォームでの在庫確認、お客様宅への発送やお取り置き・お取り寄せは行っておりません
複眼人
¥2,420
在庫なし
商品レビュー
4.1
23件のお客様レビュー
ウー・ミンイーが描く世界では、死者の記憶と超自然的な存在が幻想的に入り混じる。 本作は、避けられない死と終わりを受け止めてゆく物語だ。 “『波を浜辺にとどめられる島はない。』 死、それは取り立てであり、ときにそれはただの別れに過ぎず、誰に借りを作るわけでもない。 海が深く、...
ウー・ミンイーが描く世界では、死者の記憶と超自然的な存在が幻想的に入り混じる。 本作は、避けられない死と終わりを受け止めてゆく物語だ。 “『波を浜辺にとどめられる島はない。』 死、それは取り立てであり、ときにそれはただの別れに過ぎず、誰に借りを作るわけでもない。 海が深く、日々が長いように、魂もいずれ肉体を裏切るのだ” “『昔は川は話したりしなかった。互いに想い合う男女が川に落ち、二人の歌い合う声が川のせせらぎとなった。その和音から、われわれの歌は生まれた。』 人は生きていなくても、死んだとはいえないこともある。せせらぎとなった二人のように” 前者は、海の一族であるワヨワヨ島の人々の死生観であり、後者は山の一族である台湾先住民の布農(ブヌン)族の民話だ。 厳しい自然に囲まれて生きる人々は、命が奪われて死を迎えるることへの諦念と、同時に個人の死を超えて一族と世界の記憶として生きることを伝えてきた。 本作には様々な声による語りが含まれている。 野生動物の命を奪いとる狩を、変容した社会で続けていくことの倫理、利便性と発展のために、人が山や海の環境を技術によって変えていくことの倫理が、当事者である登場人物によって自問されるが、何かを断罪することなどできない。 ワヨワヨ島の次男は180回目の満月の夜(15歳だ)に島を離れて、死出の旅に向かうのが掟だ。 人口の抑制が必要なのは、文明と隔絶した未開の地でもテクノロジーが進んだ文明社会でも同列であり、対比してどちらを選んでも人類の課題が解決するわけではないのだと誰しもが分かっている。 大きな主題として、後半に浮かび上がるのは、人だけが持つ“文字で記憶を再現する力、想像で記憶を創り上げる力”についてだ。 太平洋を望む海辺の家に住む、大学で文学を教えるアリスは、幼い息子を失った絶望に取り憑かれて自殺の準備を整えてゆく。 前半でアリスは、次のように独白する。 “人生というものは、自分の考えを挟むことは許されず、ほとんどは否応なしに受け入れるしかない。オーナーの独断で料理が決まるレストランで食事するようなものなのだ。” しかし、二つの守るべき命との出会いを通じて、自殺を踏み止まって生き続けているアリスは、失っていた小説を描く気持ちを徐々に取り戻す。 なぜ書くのか、何を書くのかと問われてアリスはこう答える。 『物語を書いて、ある人を助けるの。』 『かつてあったこと、でも本当はなかったかもしれないこと』 アリスは、短編と長編の二冊の本を書き上げる。 息子の失踪という謎への、一つへの回答がここで明らかになるが、それを謎解きと捉えるのは少し違うのだと感じる。 記憶の罠に閉じ込めていた存在を、解放して昇華するという創作の力にこそ意味がある。 人生は選べないかもしれない。だが、物語が書かれ、読み継がれてゆくことによって救いがもたらされるのではないかという想いが伝わる。 物語の終盤に、まるで本作の主題歌のような、ボブ・ディランの『A Hard Rain's a-Gonna Fall(はげしい雨が降る)』が、ハファイ、サラそしてアリスによって、終末の風景のような海を目の前にして、歌い継がれる。 世界の行く末を憂うようなその歌詞は、しかしここでは彼女たちが愛した、もう会えない人々−顔も分からぬ想い人、父親、トムとトト、そしてアトレ -に向けた哀歌として胸に迫ってくる。 旋律に乗せた歌詞もまた、個人の記憶や想いを時代を超えて多義的に伝えることができる、人だけができる文字による創作の力だ。 “自然は残酷なものではないよ。少なくとも人類に対して特別に残酷というわけじゃない。視線は、反撃もしない。意思のないものに「反撃」などできるわけもないのだから。自然はただ自然がすべきことをしているだけだ。海面が上昇するなら上昇すればいい。僕たちが引っ越しをすればいい間に合わなければ、海に沈んで魚の餌になるまでさ。そういう考えもいいと思わないかい?” ”この世界で遠い場所などありはしない。もちろん近い場所もない。脳裏に突然浮かんだそんな言葉の中の矛盾について、アリスは考えていた”
Posted by 
パンチライン引用 〜人生は、いわば交換の連続なのだ。自分が持っているものと相手が持っているものとを交換する。自分の未来を差し出して、今ないものを手にする。交換を繰り返していくうちに、かつて手放したものが再び戻ってくるかもしれない。それがハファイの考えだった。〜 変わり続けるもの...
パンチライン引用 〜人生は、いわば交換の連続なのだ。自分が持っているものと相手が持っているものとを交換する。自分の未来を差し出して、今ないものを手にする。交換を繰り返していくうちに、かつて手放したものが再び戻ってくるかもしれない。それがハファイの考えだった。〜 変わり続けるもの。文化や立場が違えば、同じ景色には映らない。その人が持つ眼によって、同じ事象でも全く違う映り方をする。 話がてんてんとして、ついていけなかった。。。過去と現在も入り乱れていて、海に浮かぶゴミの渦みたいな小説だった。
Posted by 
呉明益の小説は、『歩道橋の魔術師』『自転車泥棒』を読み、これで3冊目。今まで読んだ2冊が、中華商場や、第二次大戦といった、台湾の歴史的な記憶を拠り所にした物語だったのに対して、『複眼人』は、ファンタジー要素が強く、印象がかなり違う作品だった。 世界中の人間が捨てたゴミが太平洋沖...
呉明益の小説は、『歩道橋の魔術師』『自転車泥棒』を読み、これで3冊目。今まで読んだ2冊が、中華商場や、第二次大戦といった、台湾の歴史的な記憶を拠り所にした物語だったのに対して、『複眼人』は、ファンタジー要素が強く、印象がかなり違う作品だった。 世界中の人間が捨てたゴミが太平洋沖に集まってできた「ゴミの島」が、台湾に衝突するという事件を中心に、そこにいた様々な人たちが描かれる。一番印象的だったのは、自殺寸前の大学教師の女性「アリス」の話だった。 「アリス」は、登山に出かけた夫と息子を失ったことで、自殺を考えるようになる。しかし、ちょうどその時、野良猫が家に舞い込み、「オハヨ」と名づけ、育て出したことで、自殺を思いとどまる。「アリス」にとって、この物語は、いかにして夫の「トム」と、息子の「トト」の死を受け入れるかという物語だった。彼女は、「複眼人」という小説を書き、「トト」は、自分の書いた文字の中で生きていたのだとすることで、二人の死を受け入れる。 「複眼人」というのは、彼女が書いた小説だと思われる物語の中で、これまた「トム」と「トト」だと思われる「男」と「少年」が、死の直前に出会う超自然的な存在だ。複眼人は、人間の男の姿をし、その名の通り、目が複眼になっている。彼の複眼には、一つひとつの個眼に、全く別の様々な情景が映し出されている。 面白いのは、この「複眼人」が、実在するのか、しないのか、「トム」と「トト」の身に起こったことが、現実に起きた出来事なのかどうかが、分からないことだ。この物語には、「アリス」の他に、台湾の先住民族や海外からやってきた技術者、神話の島から追放された少年などが登場する。それぞれの人物が、それぞれの人生における身近な人の死との関わりの中で、神話のような超自然的な経験をする。「アリス」の物語は、そうした登場人物たちの経験が語られる中に置かれることで、夢なのか、現実なのか、判別がつかなくなる。 「トム」の遺体は、山の中で見つかったものの、息子の「トト」は、遺体どころか、結局、その痕跡すら発見することができない。そうした現実を、「複眼人」という物語にし、猫の「オハヨ」と生きていくことを決意することで、彼女は受け入れられるようになる。
Posted by 



