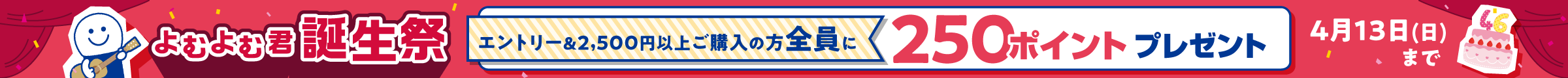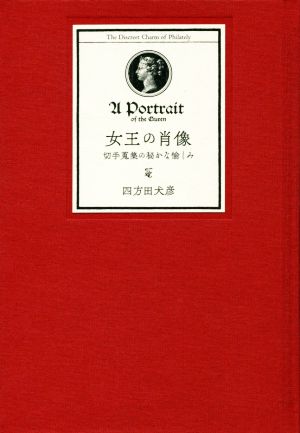- 書籍
- 書籍
女王の肖像
商品が入荷した店舗:店
店頭で購入可能な商品の入荷情報となります
ご来店の際には売り切れの場合もございます
オンラインストア上の価格と店頭価格は異なります
お電話やお問い合わせフォームでの在庫確認、お客様宅への発送やお取り置き・お取り寄せは行っておりません
女王の肖像
¥2,750
在庫あり
商品レビュー
4.3
3件のお客様レビュー
「多くの大人たちは小学生のころに、一度は切手を集めることに夢中になった体験をもっているからである」との一文に首を大きく縦に振った。事実、私も小学生高学年から中学校卒業にかけて切手収集に熱中した。著者は日本切手とは別に、世界中から父親の職場宛てに届いた封筒に貼られた外国切手を集めた...
「多くの大人たちは小学生のころに、一度は切手を集めることに夢中になった体験をもっているからである」との一文に首を大きく縦に振った。事実、私も小学生高学年から中学校卒業にかけて切手収集に熱中した。著者は日本切手とは別に、世界中から父親の職場宛てに届いた封筒に貼られた外国切手を集めたそうだが、私は日本切手の、しかも普通切手に関心を持った。発行時期の違いによりデザインは同じまま刷色だけが違う「色違い物」に特に興味を引かれた。だから、本書に登場する切手の多くは私に馴染みがないのだが、どのエピソードからも、著者の切手収集、あるいは切手そのものに対する愛情が伝わってくる。 著者は切手収集の未来について、「昔日のようなブームを巻き起こすことは、もうないだろう」と本書の最後に書いている。そうだとすれば、将来的に、本書を読もうとする人も、本書のような本を書こうという人もいなくなってしまうかもしれない。そのような「暗い未来」の一因は著者の言うように切手の「資産価値の凋落」であり、あるいはひょっとすると、郵便局で郵便物を発送しようとしても、切手代わりのお手軽シールをペタッと貼られてしまうという「郵便局が郵便切手を蔑ろにして」しまうような風潮も要因なのかもしれない。 それに加え個人的には、使用が現実に廃れつつあるにもかかわらず、次々に新切手が発行される現状も切手収集を萎えさせているように思えてならない。「世界中の切手をすべて集めるにはどうしたらいいのですか」と無邪気に尋ねた少年時代の著者に対し、日本郵趣協会の職員は苦笑いしつつテーマを絞るようにアドバイスする。でも、仮に1つのテーマを決めたとしても、世界中の切手どころか、日本切手でさえもすべてを集めきることはできないのではないか。切手に限らず、「集めきれない(コンプリートできない)」ことは収集の意欲を削ぐように思う。 切手の歴史、目打ち、印刷技法など、切手にまつわる蘊蓄も面白いが、もし、一度でも切手を集めたことがある人なら、本書の随所に登場する、収集家をとらえて離さない切手収集の魅力(魔力)に大きく共感を覚えるだろう。そして、本書を読み終えてから、自分がかつて集めた切手を収めたスクラップブックを久しぶりに開くに違いない。
Posted by 
ロンドンの切手商にふらりと立ち寄ったのをきっかけに、少年時代に熱中した切手蒐集の道に再び嵌まり込んだ著者がその魅力を語る。 四方田さんの著作のなかでも特に軽い読み心地のエッセイ。小〜中学生時代のコレクションに施したイラストなどが載っていてとても可愛い。 切手蒐集趣味全盛期とい...
ロンドンの切手商にふらりと立ち寄ったのをきっかけに、少年時代に熱中した切手蒐集の道に再び嵌まり込んだ著者がその魅力を語る。 四方田さんの著作のなかでも特に軽い読み心地のエッセイ。小〜中学生時代のコレクションに施したイラストなどが載っていてとても可愛い。 切手蒐集趣味全盛期といえる70年代の思い出話も楽しいが、それ以上に切手を通して世界の政治を眺める章が面白い。切手システムの生みの親であり、自国の切手には国名を書かず植民地の切手に女王の肖像を刻ませたイングランド。毛沢東が文革時代に大量に刷った真っ赤な切手。ユーゴスラヴィアから亡命した人びとがヨーロッパにアピールするために作ったクロアチア切手。日本が植民地化した東アジアで使われていた切手に残る二度刷り。米軍占領下の沖縄で作られた独自の切手。「切手は、大国が子供部屋で差し出す名刺である」というベンヤミンの言葉通り、切手というミニチュアのプロパガンダを通じて子どもたちは世界を見ていたのだ。 王族や時の主導者の肖像を使った切手は、イギリスをはじめ世界中にある。だが日本は皇族を切手にするのは慎重に避けてきた。そこには畏敬の対象を映像化しないという古来の呪術的な考え方があるのではないかという。一方で、肖像切手は庶民に強烈な刷り込みを与えるプロパガンダになりうるが、同時にその顔の横に少額の値段が書いてあることで肖像の人物を矮小化もする。日本政府がこのことに気づいているのだとすれば、日本にカリカチュアの文化が根付かないのにも一役かっているのかもしれない。 私も小学生時代に一瞬だけ切手を集めていたけど、ディズニー柄の切手を集めるばかりで国際情勢にまで興味を広げなかった。今思えばディズニー柄なのにアメリカだけじゃなく色んな国からでていたのは、切手コレクターを狙って外貨を獲得する手段だったのだなぁ。
Posted by 
映画学者で1953年生まれの著者が、小学生時代から続けてきた切手収集について語ったエッセイ本。お父さんがダイハツで輸出業務を担当していたことから、注文郵便に貼られた世界の切手を目にする機会が多かったといい、豊富な留学体験も相まって、視点は国際的である。中国の文化大革命時の切手(...
映画学者で1953年生まれの著者が、小学生時代から続けてきた切手収集について語ったエッセイ本。お父さんがダイハツで輸出業務を担当していたことから、注文郵便に貼られた世界の切手を目にする機会が多かったといい、豊富な留学体験も相まって、視点は国際的である。中国の文化大革命時の切手(スローガンだけ書かれた赤い切手)とか興味深く読んだ。 日本で皇室の肖像を描いた切手が皇太子成婚を除いてないことを世界でも異例なことと分析。「強力な権力者にしたところで、ひとたび切手に描かれた瞬間から額面表示の奴隷と化してしまう」「いかに神聖不可侵とされる映像でも、切手となった以上は消印という残酷な試練を免れることはできない」という。御真影の伝統がある日本ではなおさらタブーだったのであろう。 現在の日本の記念切手乱発についても著者は辛辣だ。「新切手の過剰な氾濫ぶりを見ると、逆に複雑な気持ちになってしまう」「切手蒐集が昔日のようなブームを巻起こすことは、もうないだろう」「どこの郵便局でも平然と売っていて、いつでも安価で購入できる切手とは、フェティシズムの対立物である」「人は他人が欲しがらないようなものなど、絶対に自分から欲しがろうとはしない」とは至言だ。
Posted by