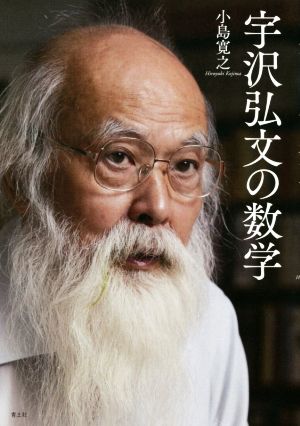
- 新品
- 書籍
- 書籍
- 1213-01-03
宇沢弘文の数学
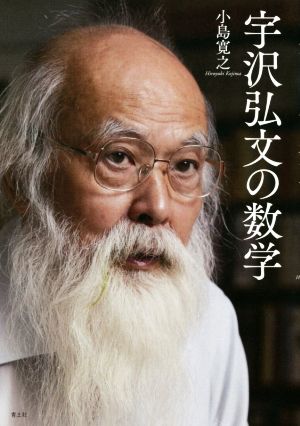
1,980円
獲得ポイント18P
在庫なし
発送時期 1~5日以内に発送

商品詳細
| 内容紹介 | |
|---|---|
| 販売会社/発売会社 | 青土社 |
| 発売年月日 | 2018/09/19 |
| JAN | 9784791771004 |
- 書籍
- 書籍
宇沢弘文の数学
商品が入荷した店舗:店
店頭で購入可能な商品の入荷情報となります
ご来店の際には売り切れの場合もございます
オンラインストア上の価格と店頭価格は異なります
お電話やお問い合わせフォームでの在庫確認、お客様宅への発送やお取り置き・お取り寄せは行っておりません
宇沢弘文の数学
¥1,980
在庫なし
商品レビュー
4
5件のお客様レビュー
1. 宇沢弘文と制度学派の経済学 本書では、宇沢弘文の経済学の思想とその影響について詳述されている。宇沢は、帰国後にアメリカでの経験から数学的な手法による経済学の限界を認識し、制度学派の視点から経済学を再構築することを目指した。彼の講義は、経済学を人権や文化、貧困といった問題の...
1. 宇沢弘文と制度学派の経済学 本書では、宇沢弘文の経済学の思想とその影響について詳述されている。宇沢は、帰国後にアメリカでの経験から数学的な手法による経済学の限界を認識し、制度学派の視点から経済学を再構築することを目指した。彼の講義は、経済学を人権や文化、貧困といった問題の文脈で考える重要性を教え、従来の経済学のあり方に対する批判を促した。 2. 社会的共通資本の理論 宇沢は「社会的共通資本」という概念を提唱し、これは経済活動における公共財の重要性を強調するものである。具体的には、医療や教育などの社会的資本は、平等に供給されるべきであると主張した。この理論は、貧困や資本の非可塑性、社会の動的安定性などの問題に対する解決策を提供するもので、彼の思想の核心を成している。 3. 数学と経済学の関係 本書では、数学が経済学の理論や実践にどのように関わるかについても言及されている。宇沢は、数学が本来持つ「言語性」や「技術性」を強調し、数学が社会的機能を果たすためにどう活用されるべきかを考察した。特に、数学が経済学の中でどのように役立つか、またその限界についても深く論じられている。 4. ゲーム理論と経済学の進化 本書では、ゲーム理論の発展とその経済学への応用についても触れられている。ゲーム理論は、利益追求の行動がどのように相互作用するかを明らかにするものであり、経済学の理解を深める重要なツールとして位置付けられている。宇沢の理論は、これらの新たな枠組みを取り入れながら進化し続けていることを示唆している。 5. 結論 本書は、宇沢弘文の経済学に対するアプローチとその社会的意義を深く掘り下げ、彼の理論が現代の経済学に与える影響を考察している。社会的共通資本の理論や数学との関係、ゲーム理論の重要性を通じて、経済学の再構築の必要性を訴えかけている。宇沢の思想は、単なる理論に留まらず、現実の経済問題に対する解決策を提供するものであり、今後の研究や実践においても重要な指針となるだろう。
Posted by 
タメになるとは思うのだが、ゲーム理論や統計学の基礎を間に挟めたのは、宇沢弘文に関連があるからと言えばそう解釈もできるが、敢えてこれを読みたかった訳ではなく、しかも極めて初歩的な内容で、何がしたかったのか分からずやや残念である。 もう少し発展的な宇沢弘文の考察、特に宇沢弘文が新古...
タメになるとは思うのだが、ゲーム理論や統計学の基礎を間に挟めたのは、宇沢弘文に関連があるからと言えばそう解釈もできるが、敢えてこれを読みたかった訳ではなく、しかも極めて初歩的な内容で、何がしたかったのか分からずやや残念である。 もう少し発展的な宇沢弘文の考察、特に宇沢弘文が新古典派から制度学派に転じた理由、これに対し、決して転換したのではなく、渡米と帰国を経ながらも、学問は一貫した問題意識に通ずるとの著者の主張、宇沢弘文には生涯テーマとして資本と貧困があったと言うなら、これを深く掘り下げて欲しかった。
Posted by 
タイトルから想像する人がいるかもしれない”宇沢弘文の数学の業績”や”宇沢弘文の業績の数学的側面”とかいった内容ではなく、”宇沢弘文の業績”を理解するための助けになる数学的知識の紹介・エッセイが前半、後半は宇沢弘文の志を受け継いで発展させるために基礎になりそうな最新のゲーム理論など...
タイトルから想像する人がいるかもしれない”宇沢弘文の数学の業績”や”宇沢弘文の業績の数学的側面”とかいった内容ではなく、”宇沢弘文の業績”を理解するための助けになる数学的知識の紹介・エッセイが前半、後半は宇沢弘文の志を受け継いで発展させるために基礎になりそうな最新のゲーム理論などの知識の紹介となっている。差別の生まれる過程についてのゲーム理論からの知見など興味深い。タイトルでの印象のように硬くはなく、簡潔にまとまっており読みやすい。やっぱりタイトルとのミスマッチ感はあるかなぁ…著者の想いはわかるにしても。
Posted by 



