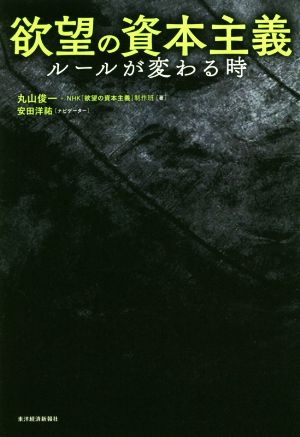商品詳細
| 内容紹介 | |
|---|---|
| 販売会社/発売会社 | 東洋経済新報社 |
| 発売年月日 | 2017/03/01 |
| JAN | 9784492371190 |
- 書籍
- 書籍
欲望の資本主義
商品が入荷した店舗:店
店頭で購入可能な商品の入荷情報となります
ご来店の際には売り切れの場合もございます
お客様宅への発送や電話でのお取り置き・お取り寄せは行っておりません
欲望の資本主義
¥1,650
在庫あり
商品レビュー
3.9
35件のお客様レビュー
本書の中でのセドラチェクの言葉に考えさせられた。欲望の資本主義というタイトルに対し、欲望を満足するための労働における哲学のような話だ。 一つは、「必要もないものを買うために、したくもない仕事をする」これはエデンの園の呪いだ。アダムとイブの物語は、禁断の果実を食べたと言う「消費に...
本書の中でのセドラチェクの言葉に考えさせられた。欲望の資本主義というタイトルに対し、欲望を満足するための労働における哲学のような話だ。 一つは、「必要もないものを買うために、したくもない仕事をする」これはエデンの園の呪いだ。アダムとイブの物語は、禁断の果実を食べたと言う「消費における呪い」を生んだのだという。禁断の果実が「不必要な消費」なのかは分からない。こじつけという気もするが、そこに顕示的消費を当てはめるならば、キリスト教の物語をそのように利用したこと自体が興味深い、と思った。禁断の果実を食した事は、罪とされているのだから、つまり、セドラチェクは、過剰な消費を罪と位置付けているという事になる。 その上で、我々はその罪を背負って、奴隷のように働いているということかと。しかし、この労働の捉え方も面白い。現代の私たちの仕事の大半は、情報の移動であり、これはアリストテレスから見たら娯楽だと考えるだろうと言う。一方で、私たちが自由な時間ができれば、ジョギングをしたり狩りをしたり、庭の手入れをしたり、釣りをしたり、料理をする。アリストテレスにとっては、これは逆に仕事であるはずだと。つまり、仕事と娯楽の逆転可能性、ランダム性が人間にはつきまとう。 「ほしいものが、ほしいわ」糸井重里の西武百貨店でのキャッチコピーだが、これは足ることを知るという言葉とは相反する。自らの際限なき欲望をくすぐり続ける。欲深き、罪深き人間だという事だ。 仕事と娯楽は何故逆転するのか、それは単純に、労働に対価が懸かっているからという事ではないだろうか。毎日走る、人より早く走ることを目指す趣味もあり、その労苦は、対価の有無以外に、労働と大差がないからだ。 シリーズものなので続編も読んでいきたい。
Posted by 
スティグリッツのイノベーションへの主張が印象的だった。 "イノベーションにより生産性は上昇しない" シリコンバレーの企業の成長や利益の源泉は広告によるものが多い つまり、利益が他企業から移行しているだけで生産性向上にはつながっていないのでは? 新しいテクノロジ...
スティグリッツのイノベーションへの主張が印象的だった。 "イノベーションにより生産性は上昇しない" シリコンバレーの企業の成長や利益の源泉は広告によるものが多い つまり、利益が他企業から移行しているだけで生産性向上にはつながっていないのでは? 新しいテクノロジーの成功例の一部は短期的に法をかいくぐっているものも多い ウーバーやエアビーなど
Posted by 
昔観た番組が面白かったので。経済学のコペルニクス的転回があるかというコンセプトも大いに共感できるし、そう言えばマクロ経済学って面白かったよなぁと思い出させてくれた。 スタンフォードはあまりにも立場というか物事の見方が違い過ぎて、論点がかみ合っていない印象。
Posted by