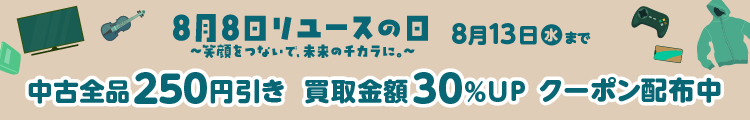- 新品
- 書籍
- 書籍
- 1215-03-00
心理学をまじめに考える方法 真実を見抜く批判的思考

2,970円
獲得ポイント27P
在庫なし
発送時期 1~5日以内に発送

商品詳細
| 内容紹介 | |
|---|---|
| 販売会社/発売会社 | 誠信書房 |
| 発売年月日 | 2016/07/01 |
| JAN | 9784414306316 |
- 書籍
- 書籍
心理学をまじめに考える方法
商品が入荷した店舗:店
店頭で購入可能な商品の入荷情報となります
ご来店の際には売り切れの場合もございます
オンラインストア上の価格と店頭価格は異なります
お電話やお問い合わせフォームでの在庫確認、お客様宅への発送やお取り置き・お取り寄せは行っておりません
心理学をまじめに考える方法
¥2,970
在庫なし
商品レビュー
4
3件のお客様レビュー
理学の研究成果を解説するのではなく、日常生活で出会う心理学的な情報や主張を、一般の読者が批判的に評価するための「思考ツール」を提供することを目的としています。メディア等で不正確な情報が広まりやすい心理学において、批判的思考力は特に重要です。 本書はまず、心理学が占星術のような疑...
理学の研究成果を解説するのではなく、日常生活で出会う心理学的な情報や主張を、一般の読者が批判的に評価するための「思考ツール」を提供することを目的としています。メディア等で不正確な情報が広まりやすい心理学において、批判的思考力は特に重要です。 本書はまず、心理学が占星術のような疑似科学とは異なり、体系的な経験主義(観察に基づく)、公知(誰もが検証可能な知見)、検証可能な問題を扱う科学であることを強調します。科学的な理論は、潜在的に誤りであることが証明できる反証可能性を持つ必要があり、概念は観察・測定可能な操作によって定義されなければなりません(操作主義)。個人的な体験談や事例研究、支持証言は、科学的な証拠としては不十分です。 次に、情報を評価する上での重要な注意点を解説します。二つの事柄に関連があっても(相関関係)、一方がもう一方の原因であるとは限りません(因果関係)。隠れた第3の変数が影響している可能性や、偶然の一致である可能性を常に考慮すべきです。因果関係を明らかにするには、他の条件を揃えて特定の要因だけを操作し、その影響を比較する実験が重要になります(賢馬ハンスの例)。一つの実験結果だけで結論を出すのではなく、異なる手法を用いた複数の研究結果が一致するか(収束証拠)を確認することが、信頼性の高い結論を得るために不可欠です。 さらに、行動の原因は一つではなく複数ある(複合原因)こと、人間の行動には確率や偶然が関わることを理解する必要性を説きます。「実験室の研究は現実的でない」という批判もありますが、原因を特定するために意図的に状況を単純化・操作することは科学的手法の強みなのです。
Posted by 
ブクログのレビューで良い感想がありました。引用させていただきます。 「心理学の科学性,というか科学志向性を考えるために良い本だと思います。」 FROM gsd9720さんのレビュー 私も同じ感想を持ちました。 本書では,心理学がどこまで科学的か,しかしなぜ科学として(他の科...
ブクログのレビューで良い感想がありました。引用させていただきます。 「心理学の科学性,というか科学志向性を考えるために良い本だと思います。」 FROM gsd9720さんのレビュー 私も同じ感想を持ちました。 本書では,心理学がどこまで科学的か,しかしなぜ科学として(他の科学のようには)見てもらえないのか,について説明されていました。 心理学は,その方法を科学から持ち込んだという歴史があります。ですので,心理学の方法がいかに科学的かを説明する本書は的を射ていると思います。現在用いられている心理学の方法はまさに「科学」でしょう。 しかし,心理学が対象するモノ(つまり,人間の心)は,科学の対象とは違います。(自然)科学は人間(研究者)の観測が対象とするモノ(研究対象)に影響を与えることはありませんが,心理学は不可避的にそれが起こる場合があります。 ※ (自然)科学における観測問題は,人間の観測がモノに影響を与えているのではなく,モノの振る舞いを人間がより正確に捉えられるようになった結果としての現象であると私は考えています。 そのような「対象とするモノ」の違いがあるにもかかわらず,方法の科学性をもって心理学を科学であると宣言することは,私には一定の違和感があります。 たとえば,煮物をつくるときに鍋を使いますが,野菜炒めを作るときにはフライパンを使うと思います。このときの,鍋かフライパンか,が方法です。もちろんフライパンで煮物を作ることもできますが,もっとも美味しい煮物を作ることができるのは鍋であろうと思います。 すなわち,心理学が対象とする人間の心にはそれを捉えるために科学の方法以外の適切な方法があるのではないか,その方法をきちんと見つけ出せたときに,心理学ははじめて「科学」になるのではないかと思います(そのときの「科学」が自然科学的かはわかりませんが)。 心理学が対象するモノは多様です。したがって,中には,従来の(そして現在に続く)心理学的方法がうまく適用できるところもあると思います。他方,それがうまくいかない分野もあると思います。 ヴントが実験心理学と民族心理学を構想したように,自然科学的心理学と人文科学的心理学とがうまく共存したとき,心理学ははじめて人間科学として素敵な学問になるのではないかと思います。 その意味で,本書は,自然科学的心理学の方向性について考えさせてくれるもので,また,胡散臭い「エセ心理学」と(自然科学的)心理学を見分ける視点を養ってもくれるものでした。
Posted by 
心理学の科学性、というか科学志向性を考えるために良い本だと思います。心理学を学ぼうとする人って「心理学はこころの科学です」って言われてきたと思うのですが、その科学性がなんなのか、いまいちよくわからないと思うのです。というか、その点をきちんと教えられていない。この本は、心理学者が考...
心理学の科学性、というか科学志向性を考えるために良い本だと思います。心理学を学ぼうとする人って「心理学はこころの科学です」って言われてきたと思うのですが、その科学性がなんなのか、いまいちよくわからないと思うのです。というか、その点をきちんと教えられていない。この本は、心理学者が考えているところの心理学の科学性について紹介したものです。心理学科の学部生なんかは読んでおくと研究法の授業なんかの勘所がつかめるようになるのではないでしょうか。
Posted by