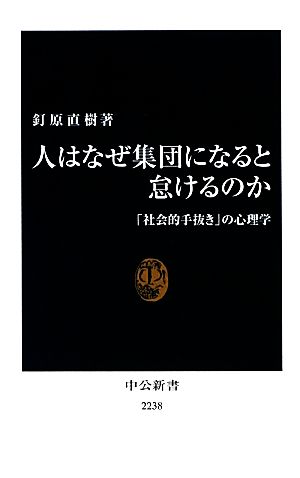
- 新品
- 書籍
- 新書
人はなぜ集団になると怠けるのか 「社会的手抜き」の心理学 中公新書
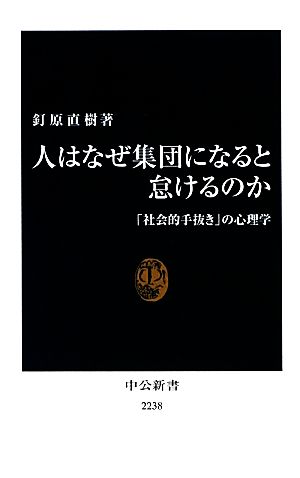
968円
獲得ポイント8P
在庫なし
発送時期 1~5日以内に発送

商品詳細
| 内容紹介 | |
|---|---|
| 販売会社/発売会社 | 中央公論新社 |
| 発売年月日 | 2013/10/25 |
| JAN | 9784121022387 |
- 書籍
- 新書
人はなぜ集団になると怠けるのか
商品が入荷した店舗:店
店頭で購入可能な商品の入荷情報となります
ご来店の際には売り切れの場合もございます
お客様宅への発送や電話でのお取り置き・お取り寄せは行っておりません
人はなぜ集団になると怠けるのか
¥968
在庫なし
商品レビュー
3.1
23件のお客様レビュー
■社会的手抜き 個人が単独で作業を行った場合にくらべて、集団で作業を行う場合のほうが1人当たりの努力の量(動機づけ)が低下する現象を社会的手抜きという。 ■社会的手抜きの原因 ・「道具性」欠如の認識:「自分が頑張っても、それが集団全体の業績にはあまり影響しない」 ・「努力の不...
■社会的手抜き 個人が単独で作業を行った場合にくらべて、集団で作業を行う場合のほうが1人当たりの努力の量(動機づけ)が低下する現象を社会的手抜きという。 ■社会的手抜きの原因 ・「道具性」欠如の認識:「自分が頑張っても、それが集団全体の業績にはあまり影響しない」 ・「努力の不要性」の認識:他の人がしっかり仕事をしているので自分が頑張る必要はない ・「評価可能性」欠如の認識:たとえ頑張ってもそれが他の人にはわからないので評価されない …日常、指導的な立場にある人が緊急時でもリーダーシップをとることが明らかになった。上司は上司として、父親は父親として、その役割を果たそうとする傾向がある。よほどのことがない限り、責任が分散するとか、日常の役割を放棄して自己中心的振る舞いをすることはないようである。 ■無意識での社会的手抜き 社会的手抜きやケーラー効果が意識的に行われるものか否かについては明確ではないが、これまでのこの分野の数多くの研究をレビューした結果によれば、自己報告と実際のパフォーマンスの相関は0.25しかなかった。これは社会的手抜きの大部分は無意識のメカニズムに基づいていることを示唆している。もしそうであれば、社会的手抜きの存在を意識化させれば、それを低減することが可能になると思われる。
Posted by 
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
・集団になると人は怠け、単独作業より努力の量が低下する。1+1が2にならない ・社会的手抜きを無くすのは難しい ・女性は対人関係指向で人間関係に注意を払う傾向がある ・男性は同調しないことで他者より優位に立つことを考えたり、それができなければ集団から離れたりする ・腐ったリンゴ効果は存在する ・対策としては、リーダーによる働きかけ、監視、社会的手抜きという現象がありそれが現に見られたという情報を与えるなど
Posted by 
集団での作業努力が個々人の努力量の総和よりも低下する現象「社会的手抜き」を、綱引きや居眠り、生活保護や投票に至るまで数多くの具体例を提示しながら、その対策について論じている本。 ここで明らかになるのは手抜きが、ただの怠惰だけではないということだ。 例えば、仕事中にインターネッ...
集団での作業努力が個々人の努力量の総和よりも低下する現象「社会的手抜き」を、綱引きや居眠り、生活保護や投票に至るまで数多くの具体例を提示しながら、その対策について論じている本。 ここで明らかになるのは手抜きが、ただの怠惰だけではないということだ。 例えば、仕事中にインターネットの利用などのサイバー手抜きを行うと気分転換ができたり、士気の上昇などが確認されている。また、集団サイズが大きい場合において、手抜きに対する許容度が大きければ、社会的手抜きの悪影響を受けにくいといった報告もある。 このような手抜きの性質を筆者は、1.努力の不要性、2.道具性、3.評価可能性を挙げて説明を試みている。 1.努力の不要性は、個人のパフォーマンス(成果)が、集団の業績にどれだけ貢献するかどうかの指標である。ほとんど全体に影響がなければ努力の必要性を感じなくなる。 2.道具性は、個人あるいは集団のパフォーマンスがどれだけ報酬になるかどうか(成果や業績が報酬に役に立つか)の指標である。パフォーマンスの向上が報われないと感じると手抜きに繋がる。 3.評価可能性は、集団の報酬が個人の報酬につながるかどうかの指標である。全体が潤っても個人が貧しいままではモチベは低下する。 このように、手抜きにはある種の「合理性」が見て取れる。もちろん、社会的手抜きによる損失は存在し対策を講じられてきた。だが、逆にその社会的手抜きが、集団や組織を維持している側面も存在している。「手抜きの攻防戦」は今に始まったことではなく、今後も決着がつきそうにもない。 なら、手抜きの多面性を認めた上で、どう付き合っていくのか。それを考えるのが今後の課題である。
Posted by 

