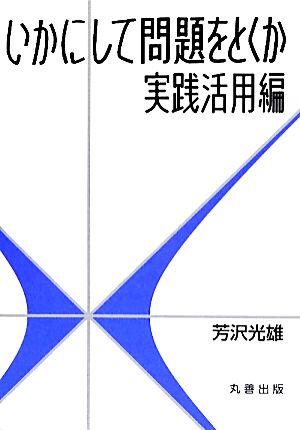

商品詳細
| 内容紹介 | |
|---|---|
| 販売会社/発売会社 | 丸善出版 |
| 発売年月日 | 2012/04/21 |
| JAN | 9784621085295 |
- 書籍
- 書籍
いかにして問題をとくか 実践活用編
商品が入荷した店舗:店
店頭で購入可能な商品の入荷情報となります
ご来店の際には売り切れの場合もございます
オンラインストア上の価格と店頭価格は異なります
お電話やお問い合わせフォームでの在庫確認、お客様宅への発送やお取り置き・お取り寄せは行っておりません
いかにして問題をとくか 実践活用編
¥1,540
在庫あり
商品レビュー
3.2
25件のお客様レビュー
おもしろい。 数学を知っていると日常生活がまた違った景色になる。 扱われている論理や問題は自分には難しかったが、数学に親しむ必要があるのはよくわかった。 簡単なところから数学を学びなおし、日常的に数字で考える、数学の理論で考えるクセをつけておこう。 そうすると、いろいろなことが...
おもしろい。 数学を知っていると日常生活がまた違った景色になる。 扱われている論理や問題は自分には難しかったが、数学に親しむ必要があるのはよくわかった。 簡単なところから数学を学びなおし、日常的に数字で考える、数学の理論で考えるクセをつけておこう。 そうすると、いろいろなことが整理される。 問題はほぐして、自分のもっている知識をつかい、解決し、検証することが必要だ。 以下、ネットに出ていたまとめ。 おもしろかったので貼っておく。 4つのステップ 1.問題を理解すること。 問題が何であるのか。何が原因かを分析する。原因は全て列挙する。 2.計画をたてること。 可能性のある解決策を列挙して、ベストな解決を選ぶ。 3.計画を実行すること。 計画を着実に実行する。弱気にならず努力する。 4.振り返ってみること。 解決策を実行後、問題が解決したか評価する。 未解決ならば見直しを行い、問題が解決するまで繰り返す。 *帰納的な発想を用いる。 帰納とは観察や特殊な事例の組み合わせから一般的な法則を発見する手続きである。 自然数で3位までまずはやってみる。 *背理法を用いる。 間違った過程から、著しく不合理な結論を導いて、その仮定の誤りであることを示すことである。 *条件を使いこなしているか。 明らかになっている条件だけでなく、隠れている条件はないか。を考える。 *図を描いて考える。 図にはグラフも含まれる。 *逆向きに考える。 *一般化して考える。
Posted by 
4つのステップ 1.問題を理解すること。 問題が何であるのか。何が原因かを分析する。原因は全て列挙する。 2.計画をたてること。 可能性のある解決策を列挙して、ベストな解決を選ぶ。 3.計画を実行すること。 計画を着実に実行する。弱気にならず努力する。 4.振り返ってみること。 ...
4つのステップ 1.問題を理解すること。 問題が何であるのか。何が原因かを分析する。原因は全て列挙する。 2.計画をたてること。 可能性のある解決策を列挙して、ベストな解決を選ぶ。 3.計画を実行すること。 計画を着実に実行する。弱気にならず努力する。 4.振り返ってみること。 解決策を実行後、問題が解決したか評価する。 未解決ならば見直しを行い、問題が解決するまで繰り返す。 *帰納的な発想を用いる。 帰納とは観察や特殊な事例の組み合わせから一般的な法則を発見する手続きである。 自然数で3位までまずはやってみる。 *背理法を用いる。 間違ったかていから、著しく不合理な結論を導いて、その仮定の誤りであること を示すことである。 *条件を使いこなしているか。 明らかになっている条件だけでなく、隠れている条件はないか。を考える。 *図を描いて考える。 図にはグラフも含まれる。 *逆向きに考える。 *一般化して考える。 考えることは面白いと改めて感じた。
Posted by 
ポリアの"How to Solve It"(いかにして問題をとくか)を項目ごとに具体的な事例や数学問題をもとに解説されています。具体的な実例を通じて問題解決の重要な考え方がまとめられているので,役立つ場面も多いかと思います。 ただ,馴染みのある話題や,すで...
ポリアの"How to Solve It"(いかにして問題をとくか)を項目ごとに具体的な事例や数学問題をもとに解説されています。具体的な実例を通じて問題解決の重要な考え方がまとめられているので,役立つ場面も多いかと思います。 ただ,馴染みのある話題や,すでに知っている話も多く,改めて問題解決の考え方について読んでみるというような状況になる方もいらっしゃるかもしれません。また,「いかにして問題をとくか」の実践活用編となっていますが,ポリアの著作の引用は各章の冒頭くらいで,後は実際の問題解決の場面や数学問題の解説になっていますので,ポリアの解説書ではなく,ポリアの著作を基にした実践活用の具体例をまとめた書籍と捉える必要があると考えます。
Posted by 



