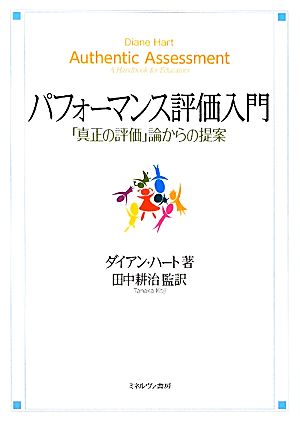- 書籍
- 書籍
パフォーマンス評価入門
商品が入荷した店舗:店
店頭で購入可能な商品の入荷情報となります
ご来店の際には売り切れの場合もございます
オンラインストア上の価格と店頭価格は異なります
お電話やお問い合わせフォームでの在庫確認、お客様宅への発送やお取り置き・お取り寄せは行っておりません
パフォーマンス評価入門
¥3,300
在庫あり
商品レビュー
3
2件のお客様レビュー
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
2025年、初読破。 書店で見つけメルカリで購入。 内容を見ると、アメリカで1994年に書かれたものらしい。少し昔の本ということもあり、自分がこれまでに読んだ本にあったパフォーマンス課題(評価)の説明とは少し異なるものだった。 今まで読んだ本の元になっているというか、再確認したと言う部分が大きい印象。 従来のテストによる評価と比較すると、パフォーマンス評価の主な特徴として以下のような点が挙げられる。 ・実生活や学際的な課題を反映している。 (個人的には、この「学際的な」の部分が大切だと思う。学際的ということは、パフォーマンス評価は必ずしも実生活とつながるものではないということ。ここに留意しておかないと、日常と繋がる内容=パフォーマンス評価(課題)のような捉えになってしまう恐れがある。) ・知識やスキルを統合して行うオープンエンドな問題及び課題を扱う。 ・しばしば他者との協力が必要になる。 ・前もって子どもに課題の内容が知らされる。 ・評価尺度(ルーブリック)が明確であり子どもにも知らされている。 準備にかかるコストや妥当性・信頼性への不安は概ね予想通り。ただそれも踏まえた上で、パフォーマンス評価の価値を見出し実施するかどうか。 それは教師それぞれに委ねられている。 もし学ぶ価値のあるものであれば、それは評価する価値のあるものだ。 どれだけ客観的に…と言っても、主観を全て排除することはできない。そこを割り切って、ルーブリックに基づく評価を行うことも大切だ思う。 全単元でパフォーマンス評価(課題)を取り扱うのではなく、特に重要だと思った単元において、「ここは特に多面的に評価したい」と感じるものから、まずは取り組みたい。 また、本書の中には、パフォーマンス課題として、短い課題や多肢選択式問題なども示されていたので、この部分も参考にしたい。
Posted by 
今年買った本。 今年出ているから、当たり前かなぁ…。 評価と聞けばテストのこと…みたいな反応しかしない人がいっぱい。受験にかかわる教科の人達は特に。それって勉強不足で、本当に生徒の学習向上を考えるのなら評価として乏しいと思う。だけど、しがみついている。 そこから離れて、大局的に成...
今年買った本。 今年出ているから、当たり前かなぁ…。 評価と聞けばテストのこと…みたいな反応しかしない人がいっぱい。受験にかかわる教科の人達は特に。それって勉強不足で、本当に生徒の学習向上を考えるのなら評価として乏しいと思う。だけど、しがみついている。 そこから離れて、大局的に成績向上を見ることができない限り伸びないと思う。何点取れたか?それで測れるように問題を創ることもある程度できるとは思うけど…。 ポートフォリオ評価の一番すごいところは、生徒自身が自分の成長を振り返ることができていくこと。これは共感。
Posted by