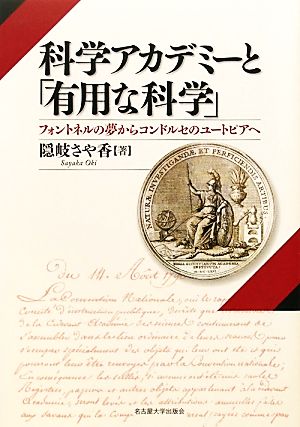

商品詳細
| 内容紹介 | |
|---|---|
| 販売会社/発売会社 | 名古屋大学出版会 |
| 発売年月日 | 2011/03/03 |
| JAN | 9784815806613 |
- 書籍
- 書籍
科学アカデミーと「有用な科学」
商品が入荷した店舗:店
店頭で購入可能な商品の入荷情報となります
ご来店の際には売り切れの場合もございます
オンラインストア上の価格と店頭価格は異なります
お電話やお問い合わせフォームでの在庫確認、お客様宅への発送やお取り置き・お取り寄せは行っておりません
科学アカデミーと「有用な科学」
¥8,140
在庫あり
商品レビュー
4
1件のお客様レビュー
パリ王立アカデミーを主題として、18世紀における科学と政治の関係を、制度的な側面から思想的な側面まで含めて総合的に扱っている研究。王立アカデミーは当初、「科学の共和国」としてのアカデミーという側面と、王国の社団編成の中に特権団体として組み込まれた技能団体としての側面を併せ持ってい...
パリ王立アカデミーを主題として、18世紀における科学と政治の関係を、制度的な側面から思想的な側面まで含めて総合的に扱っている研究。王立アカデミーは当初、「科学の共和国」としてのアカデミーという側面と、王国の社団編成の中に特権団体として組み込まれた技能団体としての側面を併せ持っていた。18世紀前半には政治や宗教といった論争を招きやすい題材が扱われることは忌避されていた。しかし、科学の有用性をめぐる議論が深化していくのと平行して、行政各部との関係がより密なものになっていく。初期のフォントネルやレオミュルにおいては、好奇心にとっての「有用性」を示し、軍事・産業に応用可能な実験科学の場を提供する点でアカデミーの存在意義が説かれていた。それが、フィロゾーフの啓蒙思想がフランスを席巻するなかで、科学の「有用性」観念も変化していく。啓蒙思想においては、分かりやすさと実用性を重視するビュフォン系の科学観(自然科学)と客観性と厳密さを重視するダランベール系の科学観(数理科学)の対立図式が存在したが、ダランベールの弟子であるコンドルセは両者の乗り越えを図った。コンドルセは解析による確率論の書き換えというラプラスの業績に依拠しつつ、自然現象と社会現象を等しく数学の言語によって記述できるという立場をとる。ここから科学アカデミーの存在意義も改めて説かれることになる。コンドルセにとってアカデミーは、長期的視野に立つ理論研究を行う場であり、かつ等しく科学の言語で記述された自然科学・社会科学により行政の合理的意志決定の基盤を提供する場でもあった。そのような観点から、18世紀後半の様々な行政事業に対するアカデミー会員個人、あるいは組織としてのアカデミーの深い関与が正当化され、あるいは推奨される。制度的にも、テュルゴーを引き継いだブルトュイユがアカデミーを次第に組織として動員し始めることによって、アカデミーは一種の諮問機関としての役割を担うことになった。その点で、1780年代のアカデミーは近代科学の制度化という観点からすると先進的であったと評されるが、それを可能にしたのはフランスの政治秩序の後進性(中央集権化が相対的に進展していない、売官制など)であった。革命期に科学アカデミーに対する批判が高まる中で、コンドルセは公教育論というかたちで、ラヴォワジェは国民公会などとの折衝のなかで、科学アカデミーやそれを引き継ぐ組織の存在意義を改めて説くことになるが、啓蒙期から存在してきたアカデミー(他のアカデミーも含めて)の権威主義体質に対する反発、あるいは数理科学に対するジャコバン的非難に押し切られるかたちで、結局アカデミーは廃止されることになった。それゆえ、最終的に公共にとって有用な科学の共和国という理想は、科学によって生じる人間同士の断絶を科学の普及によって克服しようとするコンドルセのユートピア論として後世に残されることになる。制度的にはエコール・ポリテクニークなどのかたちで科学アカデミーの経験が生かされることになった。それを担ったのは、ラプラスやラグランジュといった人々であった。コンドルセに対する関心から手にとったが、王立科学アカデミーの制度的位置づけやそれに関わった色々な人々の科学観などが極めて具体的に展開されており、フランス政治史や政治思想史に関心のある人、あるいはフーコーが問題化したような「統治」の領域に関わる様々な思想に関心を持つ人、要するに科学(社会科学を含めて)と政治の関係に何がしかの関心を持つ人にとって、極めて示唆に富む研究であると思う。
Posted by 

