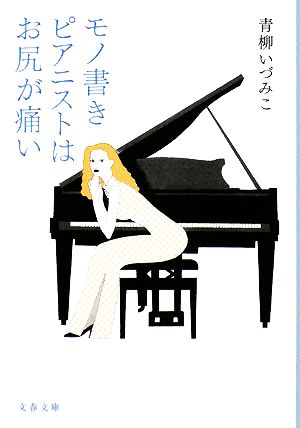
- 新品
- 書籍
- 文庫
- 1224-35-03
モノ書きピアニストはお尻が痛い 文春文庫
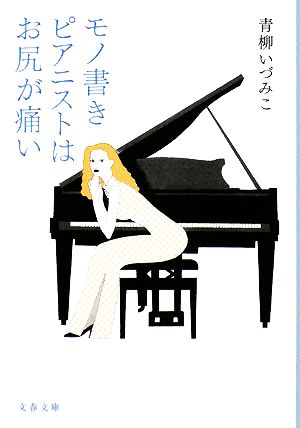
660円
獲得ポイント6P
在庫なし
発送時期 1~5日以内に発送

商品詳細
| 内容紹介 | |
|---|---|
| 販売会社/発売会社 | 文藝春秋 |
| 発売年月日 | 2008/11/10 |
| JAN | 9784167753146 |
- 書籍
- 文庫
モノ書きピアニストはお尻が痛い
商品が入荷した店舗:店
店頭で購入可能な商品の入荷情報となります
ご来店の際には売り切れの場合もございます
オンラインストア上の価格と店頭価格は異なります
お電話やお問い合わせフォームでの在庫確認、お客様宅への発送やお取り置き・お取り寄せは行っておりません
モノ書きピアニストはお尻が痛い
¥660
在庫なし
商品レビュー
3.3
11件のお客様レビュー
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
「ボクたち クラシックつながり」が面白かったので、二作目に挑戦。本書は、現役ピアニストと文筆家という二足のわらじを履いて活躍中の筆者のエッセイ集。 私の好きな印象派のドビュッシーやラヴェル、サティなどの情報も満載。 以下は、備忘録がわり。 ・ドビュッシー「沈める寺」は、ブルターニュの町イスにまつわる伝説がモチーフ ・ドビュッシーかアンチワーグナーなのは愛情の裏返し ・サティを上手く弾けるのは、超優等生か超劣等生のどちらか ・サティのオカルト趣味は筋金入り ・シューベルトは梅毒で死んだ ・モーツァルトはスカトロジスト ・音楽学校には3種の生徒。親に管理されて音楽一筋で頑張っている子とスポーツも勉強も器用に両立させられる子、好きで始めたが素質があったのでたまたま合格した子。シューベルトを弾くのが上手いのは、最後のタイプ ・フランスで人気なのはワーグナーやブラームスで、ドイツではドビュッシーやラヴェルとみんな天の邪鬼 ・シューマンの生きていた時代は、妻のクララの方が有名だったので、クララの夫として紹介されていた ・ドビュッシーはラヴェルの人工的な作風を嫌って「手品師、常に準備されたもので1回しか人を驚かせない」と酷評するも「これ以上の才能はない」と認める ・調性の範囲内で生涯の仕事を終えたラヴェルに対して、ドビュッシーは複旋法性と複調性を多用した大胆な書法を試み、二十世紀音楽に通じる道を切り開いた。ラヴェルの革新性は、時代を先取りするものではあったが、時の流れを踏み越えることは出来なかった ・筆者の演奏で好評だった曲、ラヴェル「オンディーヌ」とドビュッシー「葉末を渡る鐘の音」 ・キャンセルする天才(アルゲリッチ)とキャンセルしない天才(ラローチャ) ・技巧派の天才、ポリーニとミケランジェリ(ドビュッシーといえばミケランジェリ) ・ピアノ科のピアノに未来はない(作曲科の生徒と比較したもので、ピアノ科生徒は弾けるように弾き、作曲科生徒は弾かなければならないように弾く) ・筆者の苦手な作曲家系ピアニストは、アファナシエフやクロスリー ・ピアニスト的ピアニストの傑作がアルゲリッチ ・ピアニストのお尻には椅子の座り過ぎによるアザがある ・「批評の暴力」「批評の諸問題」では心無い批評家の言葉がどれほど演奏家を傷つけるのかをこう訴える 《批評する側の価値基準がはっきりしていれば、演奏する方もそれを正しく解釈して次の演奏に役立てることが出来る。演奏家は、本当に命をすり減らして弾いているのだから、批評する方も少なくともそれだけの心構えで聴いてほしい》 本当に音楽批評家って何なんだろうね。もちろんヨイショの記事ばかりでも困るが、批評するなら最低限その根拠位は明確にすべきでしょう。
Posted by 
20年ほど前に、様々な媒体に発表された文章をまとめたエッセイ集。 もちろん、文庫となった2008年からも、すでに十数年経っている。 ただ、今読んでも面白く読める一冊だ。 青柳さんのことは、ドビュッシーの楽譜を分析した本のことを新聞で読んで知った。 演奏家としてだけでなく、音楽学...
20年ほど前に、様々な媒体に発表された文章をまとめたエッセイ集。 もちろん、文庫となった2008年からも、すでに十数年経っている。 ただ、今読んでも面白く読める一冊だ。 青柳さんのことは、ドビュッシーの楽譜を分析した本のことを新聞で読んで知った。 演奏家としてだけでなく、音楽学の方でも業績を残す、とんでもない才能だと思ったことを覚えている。 その才能は、きっとお祖父さん譲り。 仏文学者青柳瑞穂が、その人だという。 そして、そのアイディンティティが、この人にとって相当大きいものであることが、本書からわかる。 そういった「二足の草鞋」を履くことの意義と難しさも、本書にはしっかり書かれている。 音楽であれ、本であれ、批評とは本当に難しい。 (演奏家がそんなに批評を気にしているとは知らなかったが。) ピアノを弾くとき、指を曲げるか伸ばすか論争。 それを提起したのは青柳さんだったのか。 たしかに、5年ほど前、30年ぶりにピアノのレッスンを再開したとき、昔と違い指をそれほど丸めなくていいと指導され、びっくりしたことを、自分の経験として知っている。 どちらかが絶対的に正しいわけでないが、どちらで育ってきたかによって、レパートリーに若干差がつくという話は面白かった。 あとがきが小池昌代さんだということもあって、本書を買った。 なんか、二倍得をした気分。
Posted by 
マルセイユのあばずれ娘、若い日からの大酒のみ!個性的なピアニストだということを文章の端々に感じる。ドビュッシーの演奏及び文筆両面の専門家のようだが、ドビュッシーのイメージからは、この方の素顔が遠いことが面白いところ。演奏前の緊張を描いている文章、また批評家の文章の難しさ、また演奏...
マルセイユのあばずれ娘、若い日からの大酒のみ!個性的なピアニストだということを文章の端々に感じる。ドビュッシーの演奏及び文筆両面の専門家のようだが、ドビュッシーのイメージからは、この方の素顔が遠いことが面白いところ。演奏前の緊張を描いている文章、また批評家の文章の難しさ、また演奏者への影響の大きさなどの文が実に興味深く読めた。またドビュッシーとワーグナー、あるいはラヴェルやマーラーとの比較なども面白い。お淑やかな印象を与える女性ピアニストの実像は中村紘子もそうだったが、実は大きなギャップがありそうだ。しかし、舞台上で多くの人を前にする人なら、むしろ当然なのかも知れない。
Posted by 



