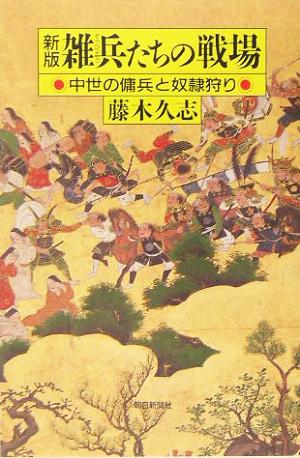

商品詳細
| 内容紹介 | |
|---|---|
| 販売会社/発売会社 | 朝日新聞社 |
| 発売年月日 | 2005/06/25 |
| JAN | 9784022598776 |
- 書籍
- 書籍
雑兵たちの戦場 新版
商品が入荷した店舗:店
店頭で購入可能な商品の入荷情報となります
ご来店の際には売り切れの場合もございます
オンラインストア上の価格と店頭価格は異なります
お電話やお問い合わせフォームでの在庫確認、お客様宅への発送やお取り置き・お取り寄せは行っておりません
雑兵たちの戦場 新版
¥1,430
在庫あり
商品レビュー
4.2
15件のお客様レビュー
「奴隷制度」って聞くとなんとなくアフリカとかアメリカとかを連想しがちだけど、戦国末期の日本人も実はかなりの数が東南アジアに奴隷として人身売買されていた、っていうのは結構衝撃的。 なんとなく虐げられるだけの弱いイメージのあった戦国期の農村は、思ったより逞しく、したたかに生きていた...
「奴隷制度」って聞くとなんとなくアフリカとかアメリカとかを連想しがちだけど、戦国末期の日本人も実はかなりの数が東南アジアに奴隷として人身売買されていた、っていうのは結構衝撃的。 なんとなく虐げられるだけの弱いイメージのあった戦国期の農村は、思ったより逞しく、したたかに生きていたんだなぁと思った。
Posted by 
※以前ブログに書いた感想をこちらに載せました。 自分は日本史興味が無くて(日本人なのにー) 高校も地理を選択してたし なので、中学以来 日本史的なものは読んでこなかったですー。 日本史の本なんて読んでこなかったから、すっごい読みにくい 斜め読みできないですー 読むのに時間かか...
※以前ブログに書いた感想をこちらに載せました。 自分は日本史興味が無くて(日本人なのにー) 高校も地理を選択してたし なので、中学以来 日本史的なものは読んでこなかったですー。 日本史の本なんて読んでこなかったから、すっごい読みにくい 斜め読みできないですー 読むのに時間かかってしまったー・・・。 読んでみて 日本、もとは野蛮?な国だったのねーって思った。 日本には奴隷っていうのはなかったと思ってたら、違った。 昔は生きるのがホント大変だわーって思った・・・。 戦になると戦地の町の人たちを連れてってしまって、大きな都市で人身売買してたみたいΣ(`□´/)/。 男も女も子供も連れてかれて、子供はどこぞの屋敷で働かされてたり(奉公?)。 九州の港町に連れてって、東南アジアとか遠くはポルトガルとかに奴隷として売られちゃったりΣ('◇'*)エェッ!? えー!?海外に売られちゃった人ってその後どうなっちゃったわけ??? やだーそんなの! そんな風になりたくない―。 ほか、身代金要求のために連れてかれたりしてたみたい。 なんだ? 戦なんて時代劇みたいにかっこよく??ない!じゃん^^; 戦の時にちゃんと戦う人なんて、武将とその仲間・部下たちだけで他の人は 農閑期の口減らしと出稼ぎのために加わった傭兵たちで、戦地での略奪・人取りが目的だったって言う・・・。 戦があった時期を調べてみると、農閑期の時とかに多いみたい。 でもって、年1回もしくは2回とか戦してたりする・・・。 そんなに戦ばっかしてんの?? やっぱり、それって、戦地に盗みに行くのが目的??(((( ;゚д゚))) 米とか物とか人とか? で、それ、売り飛ばしたりするのかな? あと、戦地の田畑を荒らして回ったり、家を焼いて回ったり。 もう、ホントに略奪行為じゃん(((( ;゚д゚)) 日本中世の頃は 戦での略奪OK!!みたいな感じだったらしい。 それに昔は今ほど作物取れなかっただろうし、 飢饉とかになると餓死者が多かったみたい。 秋に収穫したものが無くなる春先に餓死者が多くて、夏は下痢などの病気で死者が多かったみたい。 だから、戦っていうのは武士だけじゃなくて 農業だけでは食べていけない農民たちが稼ぐために 傭兵として参加してたらしい。 豊臣秀吉の頃から平安になっていったみたいだけど、(秀吉は戦の時に略奪すんな!って通知?出してたみたい)国内が平和になったところで朝鮮に出兵して行き場を失った傭兵たちの稼ぐ場所を海外に移したんじゃないか?みたいなことだった・・・。 この時も、朝鮮から多くの人を奴隷として日本に連れってたみたい。 うわー・・・(; ̄Д ̄) この時代、もう 生きてくだけで精いっぱいで、 精神論なんて言ってられなさそう・・・。 戦に行って乱取りして、それで生きていくしかないのか・・・。 衣食住が満たされてないと荒むよねー・・・。 犯罪も増えると思うし。 犯罪とか言ってる場合じゃねー!ってとこですか・・・。 生きるって大変(;;) 今はなんていい時代なんだ・・・。 大変な思いして生きて繋がってて、 今こうやって自分が生きてるってーのは奇跡なんだなーと・・・。
Posted by 
戦国時代といえば有名武将を連想するが、この本で取り上げられているのは、武士とも呼ばれない身分の低い兵卒たち。 戦場では掠奪が当たり前で、城攻めという目標そっちのけで掠奪し、その戦利品には人も含まれており、人は奴隷として東南アジアやポルトガルへ売られていったこと、 東南アジアでは...
戦国時代といえば有名武将を連想するが、この本で取り上げられているのは、武士とも呼ばれない身分の低い兵卒たち。 戦場では掠奪が当たり前で、城攻めという目標そっちのけで掠奪し、その戦利品には人も含まれており、人は奴隷として東南アジアやポルトガルへ売られていったこと、 東南アジアでは傭兵として動員されていたことや好戦的な民族と海外からは見られていたことなど、知らないことが多かった。 ヨーロッパ方面に売られた奴隷はどのように生きていたのだろうという疑問が沸いた。 農閑期などには食糧不足が深刻になるため、収穫狙いで出稼ぎで出兵し食いつなぐ”食うための戦争”をしていたという。 戦争は、いつの時代も掠奪を伴い、小説やドラマで描かれるような「武将に忠義を尽くす武士たち」という戦国時代というイメージがファンタジーだと思い知らされる。 当時、仏教が普及していたと思うのだが、慈悲の心や道徳観などは、どうだったのだろう。 子を売り、親を売る、庶民の日常生活がサバイバル状態のこの時代に生まれなくてよかったとすら思ってしまう。 豊臣秀吉の朝鮮出兵は秀吉の認知症や乱心説などのイメージが強かったが、国内統一後、戦場での掠奪の機会を海外に求め、公共事業(鉱山の採掘、築城)や地方の過疎化の防止など、略奪のエネルギーを抑え込むための苦肉の策を凝らしていたことなどを知り、これまでの秀吉のイメージが一変した。
Posted by 



