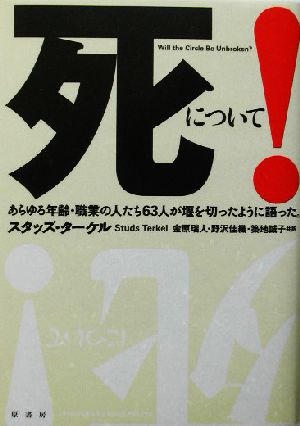
- 新品
- 書籍
- 書籍
- 1215-02-02
死について! あらゆる年齢・職業の人たち63人が堰を切ったように語った。
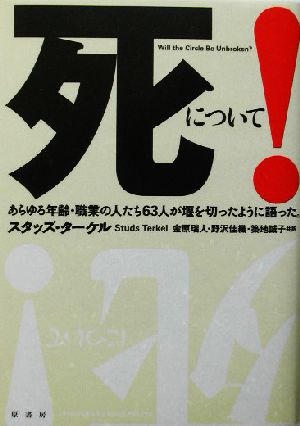
3,080円
獲得ポイント28P
在庫なし
発送時期 1~5日以内に発送

商品詳細
| 内容紹介 | |
|---|---|
| 販売会社/発売会社 | 原書房 |
| 発売年月日 | 2003/09/24 |
| JAN | 9784562036813 |
- 書籍
- 書籍
死について!
商品が入荷した店舗:店
店頭で購入可能な商品の入荷情報となります
ご来店の際には売り切れの場合もございます
オンラインストア上の価格と店頭価格は異なります
お電話やお問い合わせフォームでの在庫確認、お客様宅への発送やお取り置き・お取り寄せは行っておりません
死について!
¥3,080
在庫なし
商品レビュー
3.8
6件のお客様レビュー
死という遠くにあるようで、近くにあるもの。でも誰にでも等しく訪れるもの。わかるようでわからない「死」というテーマに対して、疑似体験を通して考えさせてくれる本です。災害等で、いつ何時大切な人がいなくなるかもしれない今の時代にこそ、死について考えてほしいと思い、この本をおすすめします...
死という遠くにあるようで、近くにあるもの。でも誰にでも等しく訪れるもの。わかるようでわからない「死」というテーマに対して、疑似体験を通して考えさせてくれる本です。災害等で、いつ何時大切な人がいなくなるかもしれない今の時代にこそ、死について考えてほしいと思い、この本をおすすめします。
Posted by 
面白く読んだ。 和訳が上手でスラスラ読めたし、安心感があった。 宗教をしっかり持っているって意味では アメリカ人の考えかたは日本人と 違う捉え方もあるし 仏教に行く人もいるし。 でも一番は人種差別や戦争の生々しい声を 市井の人の気持ちを垣間見ることができて 良かった。 卒論の時に...
面白く読んだ。 和訳が上手でスラスラ読めたし、安心感があった。 宗教をしっかり持っているって意味では アメリカ人の考えかたは日本人と 違う捉え方もあるし 仏教に行く人もいるし。 でも一番は人種差別や戦争の生々しい声を 市井の人の気持ちを垣間見ることができて 良かった。 卒論の時にこの本のことを知っていたら もう少しよい考察が出来たかも⁇
Posted by 
誰もが必ず受け取る出来事だけれど、まず第一に語ることになれば私のものでない死についてから語ることになるだろう。それはいかなる語り方になったとしても、どこに語り手がいるのかということを照らし出すような語りになる。彼岸と此岸。 それなら皆、同じ場所ではないのかと思われるかもしれない...
誰もが必ず受け取る出来事だけれど、まず第一に語ることになれば私のものでない死についてから語ることになるだろう。それはいかなる語り方になったとしても、どこに語り手がいるのかということを照らし出すような語りになる。彼岸と此岸。 それなら皆、同じ場所ではないのかと思われるかもしれない。ある意味ではそうだが、生きているこの世界はそれぞれ緩やかにつながりながらも、空間的、時間的に異なっていく。あるいは社会階層的に。これらの面を含めてより強力に、語り手の位置を指し示そうとする彼らの語りうる死と死者たちは確かに彼らとともにある。 本書は2001年に書かれた。21世紀に入ったばかりで少し浮かれていたような気分もあったが、持続可能な文化に向けてまだまだ問題が多いと言われていた時代だ。エイズも恐ろしい疫病として一般によく認知されるようになっていた。 同じ年に9.11もあったはずだが、誰のインタビューにも出ていないのでおそらくはその前にすべてのインタビューは終わっていたのだろう。むしろ戦争はベトナム、湾岸戦争、こういった単語と結びついており、アメリカ本土は戦地でなかった。 世界は変わっていく。我々も同じように流されもするので、それに気づくためには死者たちの墓標は役に立つかもしれない(こんな言い方はすすんでしたいわけでないが)。われわれ生きているものたちの内臓のようなものだし。そういったデリケートな話題であるにもかかわらず、しっかりとした関係のうえに誠実なインタビューを続けてこられたターケルのこの仕事にはまったく感服するほかない。
Posted by 



