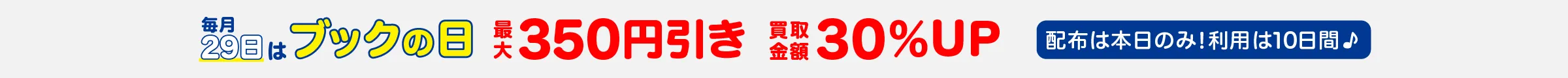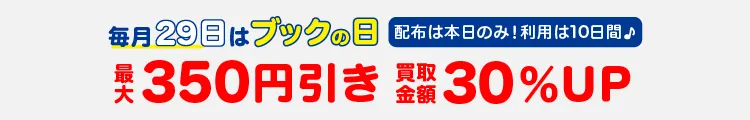- 中古
- 店舗受取可
- 書籍
- 新書
- 1226-32-02
限界の国立大学 法人化20年、何が最高学府を劣化させるのか 朝日新書976

定価 ¥924
605円 定価より319円(34%)おトク
獲得ポイント5P
在庫あり
発送時期 1~5日以内に発送

店舗受取サービス対応商品【送料無料】
店舗受取なら1点でも送料無料!
店着予定:1/2(金)~1/7(水)
店舗到着予定:1/2(金)~1/7(水)
店舗受取目安:1/2(金)~1/7(水)
店舗到着予定
1/2(金)~1/7

店舗受取サービス対応商品
店舗受取なら1点でも送料無料!
店舗到着予定
1/2(金)~1/7(水)

商品詳細
| 内容紹介 | |
|---|---|
| 販売会社/発売会社 | 朝日新聞出版 |
| 発売年月日 | 2024/11/13 |
| JAN | 9784022952912 |
- 書籍
- 新書
限界の国立大学
商品が入荷した店舗:0店
店頭で購入可能な商品の入荷情報となります
ご来店の際には売り切れの場合もございます
オンラインストア上の価格と店頭価格は異なります
お電話やお問い合わせフォームでの在庫確認、お客様宅への発送やお取り置き・お取り寄せは行っておりません
限界の国立大学
¥605
在庫あり
商品レビュー
3.3
8件のお客様レビュー
国立大が法人化から20年でどう変わったかを、主に学長や教職員へのアンケートから現状をとらえたレポート。やはり、というか残念ながら大学は悲惨になっているのがまざまざと示されてます。 ただ法人化と運営費交付金の削減があまり分けてとらえられてないのと、ではどうすべきか、というところまで...
国立大が法人化から20年でどう変わったかを、主に学長や教職員へのアンケートから現状をとらえたレポート。やはり、というか残念ながら大学は悲惨になっているのがまざまざと示されてます。 ただ法人化と運営費交付金の削減があまり分けてとらえられてないのと、ではどうすべきか、というところまであまり掘り下げてはいないので、アンケート結果からの現状紹介にとどまってる感がもったいないかな。 大手新聞社さんなので、もっと主張を持って意見を述べて欲しいですね。その方が共感なり疑問なり持ちやすい気がします。
Posted by 
結局、国立大学はどうあるべきかは見えてこない。これから少子化が進むとますます現在の国立大学数を維持するのは難しくなる。大学の先生になることを夢見ても不安定なら誰が夢見るだろう。疲れて貧しい教員に教えられる学生は何を学べるんだろう。教育や研究を自由に余裕を持ってやれて、大学行って学...
結局、国立大学はどうあるべきかは見えてこない。これから少子化が進むとますます現在の国立大学数を維持するのは難しくなる。大学の先生になることを夢見ても不安定なら誰が夢見るだろう。疲れて貧しい教員に教えられる学生は何を学べるんだろう。教育や研究を自由に余裕を持ってやれて、大学行って学んでよかったと子供たちが思えるゆとりや遊び心を維持できるほど日本って豊かじゃないと再認識させられた。
Posted by 
運営費交付金の削減による人件費のコストカット、研究時間の減少、任期付き教員の増加など悪影響が限界に達していることは事実であり、そのことは何よりこの20年の日本の研究力の低下として明らかになっている。 ただ本書でも学長と教職組合員で評価の分かれるのが大学の自治とガバナンス。朝日新聞...
運営費交付金の削減による人件費のコストカット、研究時間の減少、任期付き教員の増加など悪影響が限界に達していることは事実であり、そのことは何よりこの20年の日本の研究力の低下として明らかになっている。 ただ本書でも学長と教職組合員で評価の分かれるのが大学の自治とガバナンス。朝日新聞としては大学の自治が危機に瀕していると訴えたいようだが、やりたい放題だった過去に戻るのが適当でもあるまい。 財政面とガバナンスの問題は切り分けて論じるのが公平ではないか。
Posted by