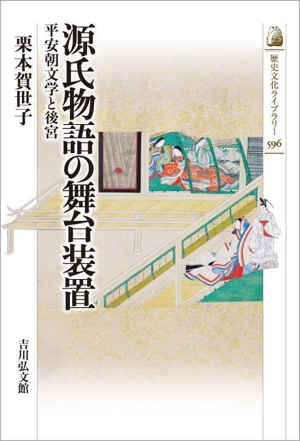
- 中古
- 店舗受取可
- 書籍
- 書籍
- 1220-02-01
源氏物語の舞台装置 平安朝文学と後宮 歴史文化ライブラリー596
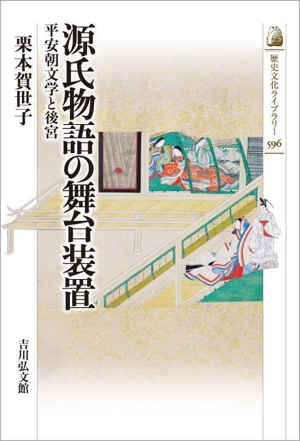
定価 ¥1,870
1,375円 定価より495円(26%)おトク
獲得ポイント12P
在庫わずか ご注文はお早めに
発送時期 1~5日以内に発送

店舗受取サービス対応商品
店舗受取なら1点でも送料無料!
店舗到着予定
2/21(金)~2/26(水)

商品詳細
| 内容紹介 | |
|---|---|
| 販売会社/発売会社 | 吉川弘文館 |
| 発売年月日 | 2024/05/24 |
| JAN | 9784642059961 |


店舗受取サービス
対応商品
店舗受取なら1点でも送料無料!
さらにお買い物で使えるポイントがたまる
店舗到着予定
2/21(金)~2/26(水)
- 書籍
- 書籍
源氏物語の舞台装置
商品が入荷した店舗:0店
店頭で購入可能な商品の入荷情報となります
ご来店の際には売り切れの場合もございます
オンラインストア上の価格と店頭価格は異なります
お電話やお問い合わせフォームでの在庫確認、お客様宅への発送やお取り置き・お取り寄せは行っておりません
源氏物語の舞台装置
¥1,375
在庫わずか
ご注文はお早めに
商品レビュー
4
2件のお客様レビュー
平安京というと、碁盤の目のような図の大内裏。 そして、内裏には七殿五舎の後宮があり…という図は、資料集などで子どものころから何度も見てきた。 源氏物語にも枕草子にも、さまざまな殿舎が登場し、そこに住む女性たちがそう呼ばれる。 まさしく、本書の副題にあるように、平安文学の「舞台装置...
平安京というと、碁盤の目のような図の大内裏。 そして、内裏には七殿五舎の後宮があり…という図は、資料集などで子どものころから何度も見てきた。 源氏物語にも枕草子にも、さまざまな殿舎が登場し、そこに住む女性たちがそう呼ばれる。 まさしく、本書の副題にあるように、平安文学の「舞台装置」。 子どもの頃はくだんの図を見て、ほぉ…と思っていたのだが、ほどなく、実は平安京も、大内裏も内裏も、あの図は「理念図」であって、実際にあのような規模で存在したかどうか微妙だという話を聞くことになる。 では、後宮の建物は、実際どれくらい建設されていたのか。 遺構などから何かわかったのか、と思って本書を手にしたのだが、そういう本ではなかった。 本書では、実際の記録と物語の記述をそれぞれ調べ、平安京の後宮の各殿舎が、どういう立場の人々に使われ、どのようなイメージをもって見られていたかを解き明かしている。 弘徽殿=最上位のキサキの住まい →物語では「悪役母后」の居所で男女の出会いの場 承香殿=第二位のキサキの住まい 歴史上でも高位でありながら、子に恵まれなかったり寵愛が薄かったりして立后できなかった人が多く、物語にもこの殿の女主人は脇役的存在になりがち。 麗景殿=第三の格式ながら印象が薄い 歴史上では後ろ盾を失ったり、寵愛を失ったりする「転落」の境遇に陥った人が多い。そのうち村上天皇に入内した荘子女王は、寵愛は薄いものの教養の高さが賞賛されたことで記憶され、それが源氏物語の花散里の姉である麗景殿の女御の造形に生かされているという話が面白かった。 初めて知ったこととしては… ・天皇の生活の場は、最初から清涼殿ではなかった 当初紫宸殿の背後にある仁寿殿で生活していたらしい。そこで天皇が死を迎えると、次の天皇は建て直すか、隣の清涼殿に移っていたが、宇多朝以降宮廷行事が清涼殿を念頭に確立していったため、固定化したとのこと。 ・一人のキサキが複数の殿舎を使うことがある 権勢が強い場合や、後宮で暮らす人が少ない時期はそういうこともあったそうだ。格下の「舎」である飛香舎(藤壺)の地位が高くなったのは、弘徽殿の隣であったからという。 ・正妃の住まいは常寧殿 後宮の中心にあり、仁寿殿の背後にあることから、格式の高い建物で、仁明・陽成・朱雀天皇も住居としたり、皇后・母后がここに入ったりしたが、御在所が清涼殿に移ると、弘徽殿に住まい、ここを併用する例が増えていったらしい。 始めの期待とは異なっていた(手前勝手な期待なので、そこは、まあ…)とはいえ、新たに知ることも多かったので、満足度は高かった。
Posted by 
著者は日本文学研究者。 幼少時から「源氏物語」に親しみ、意外にわかっていない後宮の世界を中心に研究している。后妃制度や后妃の住まいや暮らしぶりといった事柄である。歴史的事実を明らかにして、物語の記述と比較検討するという手法を用いている。 本書の主題は内裏にある後宮の様々な建物が...
著者は日本文学研究者。 幼少時から「源氏物語」に親しみ、意外にわかっていない後宮の世界を中心に研究している。后妃制度や后妃の住まいや暮らしぶりといった事柄である。歴史的事実を明らかにして、物語の記述と比較検討するという手法を用いている。 本書の主題は内裏にある後宮の様々な建物がどういった位置づけにあったかである。 「源氏物語」には、弘徽殿、麗景殿、桐壺、藤壺、梅壺、とさまざまな建物の名前が出てくる。これらは内裏に暮らす后妃たちや女官たちが暮らす場所で、後宮殿舎と呼ばれる。 天皇の住まいである清涼殿の後ろ側に位置するのが、五つの「舎」、凝華舎(梅壺)・飛香舎(藤壺)・襲芳舎(雷鳴壺)・淑景舎(桐壺)・昭陽舎(梨壺)、そして七つの「殿」、弘徽殿・承香殿・麗景殿・宣耀殿・常寧殿・登華殿・貞観殿である。 弘徽殿といえば、「源氏物語」では、悪役格の弘徽殿の女御(後の弘徽殿の大后)が思い浮かぶ。史実でも格の高い建物であり、皇后や、天皇の母である母后が使用する場である。物語上でもこれを受けて、権勢を振るう女性が住む舞台とされることが多い。 承香殿は弘徽殿に次ぐ格の高さなのだが、史実では、この建物に入った女性の多くは、身分が高く期待も大きかったが、皇后や国母になれなかった。どこか残念なイメージが付き、物語でも地味な脇役の女君の住まいと設定されがちである。 桐壺は、光源氏一族が三代連続(桐壺更衣、光源氏、明石女御)で使用した場だが、史実上も藤原兼家・道隆・原子が使用したことがある。「狭衣(さごろも)物語」の中では、父帝に愛される皇子・兵部卿宮の住まいとなっている。 藤壺は上位の后妃の住まいとなることはほとんどなかったが、村上朝の藤原安子が皇后・東宮母となった例があり、どこか華やかなイメージがあったようである。 物語作者は史実がもたらす後宮殿舎のそれぞれの特徴も利用しながら、物語の背景を膨らませ、豊かな物語世界を形作った。読者側もそれを感じ取り、一段深く物語を味わい、その空気を楽しんだものと思われる。 各殿舎がどのような経緯で格付けされたか、その位置関係やちょっとしたエピソードも紹介され、興味深い。 平安時代の読者には及ばないが、こうした背景を知ることで、より深く後宮物語を味わうことができるだろう。
Posted by 


