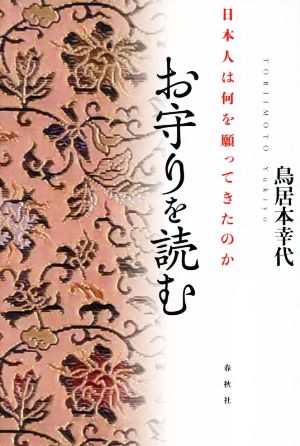
- 中古
- 書籍
- 書籍
- 1206-07-01
お守りを読む 日本人は何を願ってきたのか
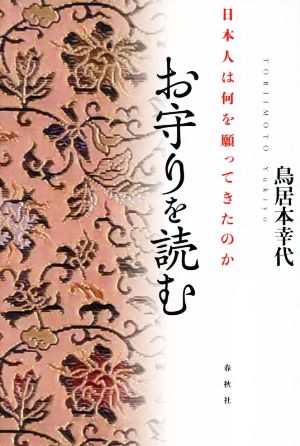
定価 ¥2,200
1,045円 定価より1,155円(52%)おトク
獲得ポイント9P
在庫なし
発送時期 1~5日以内に発送

商品詳細
| 内容紹介 | |
|---|---|
| 販売会社/発売会社 | 春秋社 |
| 発売年月日 | 2022/11/17 |
| JAN | 9784393482292 |
- 書籍
- 書籍
お守りを読む
商品が入荷した店舗:0店
店頭で購入可能な商品の入荷情報となります
ご来店の際には売り切れの場合もございます
オンラインストア上の価格と店頭価格は異なります
お電話やお問い合わせフォームでの在庫確認、お客様宅への発送やお取り置き・お取り寄せは行っておりません
お守りを読む
¥1,045
在庫なし
商品レビュー
4
2件のお客様レビュー
読者の皆様、明けましておめでとうございます。 この時期のメインイベントといえば、初詣。 初詣で多くの人が授与所で頂くものといえば、お守り。 そんなお守りのルーツをたどると興味深いことが分かった。 「いつ読むか、今でしょう」ということで、読んでみた。 ...
読者の皆様、明けましておめでとうございます。 この時期のメインイベントといえば、初詣。 初詣で多くの人が授与所で頂くものといえば、お守り。 そんなお守りのルーツをたどると興味深いことが分かった。 「いつ読むか、今でしょう」ということで、読んでみた。 最古のお守りはいつだったのか。 それは長岡京で延暦9年(790)の秋から冬にかけて、原因不明の疫病と受け止められた天然痘が広まり、人々は感染するのではないかとおびえていた。 そういうときに人々が頼ったのは、素盞鳴尊(すさのうのみこと)の故事に傚った「蘇民将来之子孫者(そみんしょうらいのしそんのもの)」と記された呪符木管だった。 長岡京跡から発見された。 「疾病の大流行がお守りを誕生させたとは、なんと皮肉なことではありませんか」と著者は述べている。 現代でもコロナ禍で話題になった「アマビエ」があるくらいだから、いつの時代も何かにすがりたくなる心理は変わらないようだ。 神社やお寺で授与されるお守りは、明治時代になってからのようだった。 一般にお守りと呼んでいるものは、「守り札」の尊称で、神仏の名号(みょうごう)や、社寺の名を記したお札(またの名を護符とも言う)をコンパクトにした、お守り=お札。 この習慣が広まったのは、中世以降だそうだ。 日本人は、昔から大きいものを小さくまとめるのが好きなのかなとふと思った。 ここで大きく関わったのは「御師(おし)」というブラタモリで何回か登場した「現代のコンシュルジュ」(byタモリ)だ。 熊野権現(熊野大社)の御師は、八咫烏(やたがらす)という熊野権現の使いを意匠した「熊野牛王符(くまのごおうふ)」と呼ぶ特殊なお札を全国に広めた。 江戸時代になると伊勢神宮の伊勢御師(伊勢地方では「おんし」と呼ぶ)が、活躍して、毎年一度、御師檀家宅を訪れ、「大神宮」と書かれている「大麻」と呼ぶお札を配布した。 神社やお寺に参拝して頂くことのある「お守り」について知らないことが多くあったので興味深いなあ。
Posted by 
御利益のルーツとは 人はなぜ、お守りをもつのか。怨霊を鎮める王朝人の儀式、邪気を祓うための風習、清少納言もおこなった物詣、疫病除けの浮世絵…。疫病の脅威から身を護る手だてとして誕生し、千年をこえる歴史のなかで日本人の精神を涵養してきたともいえるお守り。厄災への対処から、健康や繁栄...
御利益のルーツとは 人はなぜ、お守りをもつのか。怨霊を鎮める王朝人の儀式、邪気を祓うための風習、清少納言もおこなった物詣、疫病除けの浮世絵…。疫病の脅威から身を護る手だてとして誕生し、千年をこえる歴史のなかで日本人の精神を涵養してきたともいえるお守り。厄災への対処から、健康や繁栄、心願成就、将来への祈りまで。お守りという万華鏡をとおしてみえてくる、知られざる歴史と驚きのエピソード。 伝承や古典、史料などにみえる多彩な様相から起源と変遷をたどり、祈りと願いの文化を探る。 1 お守りのルーツは疫病退散を願う呪符: 日本初の疫病は天然痘だった 仏教伝来と天然痘の広まり 長岡京 平安貴族 御霊会 蘇民将来の故事 2 邪気から身体を護る術: 屠蘇は邪気を祓う薬 邪気祓いの七種粥・小豆粥 意外なひな祭りの起源 菖蒲 3 懸守で道中安全を祈る: 観世音菩薩の現世利益を願う 藤原道綱母、夫の浮気に苦しみ物詣をする 聖書納言の物詣 懸守をつけて物詣 4 進化するお守り: 勇み肌を演出する胸守の登場 疱瘡除けの錦絵―疱瘡絵 高僧良源 進化・多様化する現代のお守り
Posted by 



