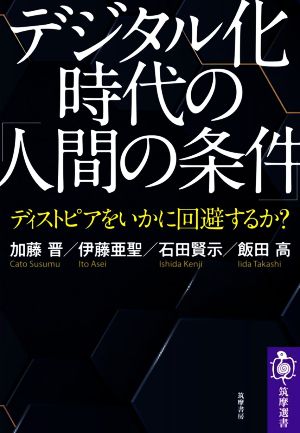
- 中古
- 店舗受取可
- 書籍
- 書籍
- 1206-03-03
デジタル化時代の「人間の条件」 ディストピアをいかに回避するか? 筑摩選書0222
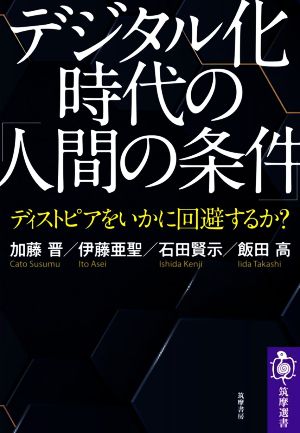
定価 ¥1,760
220円 定価より1,540円(87%)おトク
獲得ポイント2P
在庫あり
発送時期 1~5日以内に発送

店舗受取サービス対応商品
店舗受取なら1点でも送料無料!
店舗到着予定
2/21(金)~2/26(水)

商品詳細
| 内容紹介 | |
|---|---|
| 販売会社/発売会社 | 筑摩書房 |
| 発売年月日 | 2021/11/17 |
| JAN | 9784480017413 |


店舗受取サービス
対応商品
店舗受取なら1点でも送料無料!
さらにお買い物で使えるポイントがたまる
店舗到着予定
2/21(金)~2/26(水)
- 書籍
- 書籍
デジタル化時代の「人間の条件」
商品が入荷した店舗:0店
店頭で購入可能な商品の入荷情報となります
ご来店の際には売り切れの場合もございます
オンラインストア上の価格と店頭価格は異なります
お電話やお問い合わせフォームでの在庫確認、お客様宅への発送やお取り置き・お取り寄せは行っておりません
デジタル化時代の「人間の条件」
¥220
在庫あり
商品レビュー
2.5
2件のお客様レビュー
デジタル化は社会のさまざまな領域を変えていく。 例えば、事務や製造などの中間的な業務が減り、労働が二極化する。 効率化がかえって人々を忙しくさせる。 コミュニケーションの公的私的領域をシームレスにする、などなど。 そしてこの流れは不可逆だ。では、民主主義は、公共性はどうなる?
Posted by 
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
自分の身体は自分で所有しているから、それが生み出す成果は自分のものだとする。個人情報も自分の生み出す成果だとすれば、それから得られる成果は本来自分のものであるはず。ただ、現在のテック企業においては個人情報の集積とその解析と結果については提供者に与えられていない。生産手段を持たない労働者が資本家のもつ生産手段を用いて労働をする環境下において、搾取される構造にあると見抜いたマルクスの理論が「情報」の領域にも展開されうるとする。つまり、開示された情報とプラットフォームとが結合して生産物を生み出す際に情報を提供したプラットフォーム利用者が得られる益が生産物よりも少ないのではないかと指摘している。また、情報は唯一性(同時使用が困難であり、再利用不可である性質)を持たないため、流用、転用がほぼ無限に行える条件をもつため、より一層搾取になりやすい。(半永久的に、どこでも誰でもその情報によって価値を生み出し得るから) デジタル化によって、サジェスト機能や検索アルゴリズムの最適化によって取り得る情報が狭まる。それによる全体主義化を警告する。 自分の都合のいい情報だけが集まることによる体験の個別化・最適化をアルゴリズムによってなされることで、そうしたほうがいい、そうあるべき、そうでないといけないという欲望を駆り立てる。サジェストされるものが正しく、それに従うのが正しいという考えに立ってしまうことになると、個人の固有性が失われ、全体主義的な「一」に取り込まれてしまう。 そうならないように固有性を維持しよう、人間の本質を考えよう。 上記が本紙で読み取った内容である。ここから個人的感想を述べたい。 2章でデジタル化と経済の中で「アダム・スミスやマルクスは労働に力点を置いて公共性を除外したが、その公共性がデジタル化によって問題化していてその問題については6章で議論する」としていたが、感受性が乏しいのかそういった議論は6章でなかったように思う。 また、全体的にアーレントの考えた概念を当てはめて今のデジタル化を論じているが、デジタル化による指摘点については目新しさはないように思う。まあよく言われている問題点ってアーレントの言葉だとこれだよね、みたいな話でしかないように思えた。この当てはめるということに力点を置いていたのだと思うので、これはこれでいいのだろう。ただ、あとがきで筆者が言うように、結論としては言い切ったものではなく、議論の余白が残る形となっていて、アーレントの話を当てはめて、それでどうなるのか、新しく何が問題として見えてくるのかみたいなところが、個人的には受け取ることができず、さみしい気がした。
Posted by 


