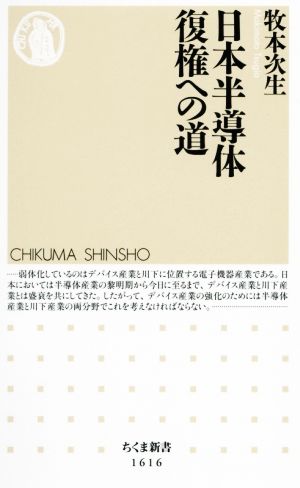
- 中古
- 店舗受取可
- 書籍
- 新書
- 1226-23-02
日本半導体復権への道 ちくま新書
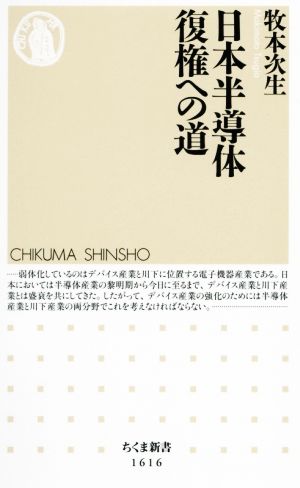
定価 ¥968
110円 定価より858円(88%)おトク
獲得ポイント1P
在庫わずか ご注文はお早めに
発送時期 1~5日以内に発送

店舗受取サービス対応商品
店舗受取なら1点でも送料無料!
店舗到着予定
2/26(水)~3/3(月)

商品詳細
| 内容紹介 | |
|---|---|
| 販売会社/発売会社 | 筑摩書房 |
| 発売年月日 | 2021/11/10 |
| JAN | 9784480074423 |


店舗受取サービス
対応商品
店舗受取なら1点でも送料無料!
さらにお買い物で使えるポイントがたまる
店舗到着予定
2/26(水)~3/3(月)
- 書籍
- 新書
日本半導体復権への道
商品が入荷した店舗:0店
店頭で購入可能な商品の入荷情報となります
ご来店の際には売り切れの場合もございます
オンラインストア上の価格と店頭価格は異なります
お電話やお問い合わせフォームでの在庫確認、お客様宅への発送やお取り置き・お取り寄せは行っておりません
日本半導体復権への道
¥110
在庫わずか
ご注文はお早めに
商品レビュー
3.6
5件のお客様レビュー
積読していた一冊。半導体の将来というより、過去半導体市場を日本が勝った経緯を知る上で有益な一冊だと思った。
Posted by 
ハーバード大学修士、東大博士、史上最年少の32歳で日立製作所の部長職に就き「出る杭」と呼ばれた著者。半導体の歌まで作り、本書で紹介する程、少し変わった人という印象。後半は自らの半導体半生を振り返りながらも、戦略上いかに半導体が重要かを説く。尖った人材。しかし、だからこそユニークな...
ハーバード大学修士、東大博士、史上最年少の32歳で日立製作所の部長職に就き「出る杭」と呼ばれた著者。半導体の歌まで作り、本書で紹介する程、少し変わった人という印象。後半は自らの半導体半生を振り返りながらも、戦略上いかに半導体が重要かを説く。尖った人材。しかし、だからこそユニークな生き様という気がする。 トランプ政権の発足以来、米中半導体摩擦が激しくなった。中国は世界最大の半導体消費国であるが、国内で生産する事は限定的であり、大半を輸入に依存。国産比率を上げるために政府が巨額の資金を投入していることにアメリカは警戒を強めており、安全保障上の懸念となる主要企業をエンティティーリストに入れて制裁を加えた。これによ、ファーウェイのスマホ事業は失速。また、20年末頃から、地政学的リスクが顕在化し、自動車向け半導体の調達が不安定化。 本書で面白いなと感じたのは、こうしたエポックメイキング的な史実よりもサイドストーリー。例えば、2021年テスラが人型のロボットを開発すると発表。テスラボットと名付けられたロボットの高さは172センチ重さ57キロ。あるいは、1997年の『デジタル遊牧民』という書が、半導体の進化によりポケットサイズの万能端末、リモートワーク、リモート講義などを予言。極め付けは、学天則の話。生物学者で元・北海道帝国大学教授の西村真琴が作った“人造人間”で東洋初のロボット。 学天則で検索すると、奇妙なロボットの写真が見つかる。1928年の話だ。不思議な時代の匂いを感じ、まるで古いアルバムを開くよう。変わった人からは、変わった物の見方を学ぶ。
Posted by 
日本の半導体が世界シェア50%から10%に落ち込み、今後0%すら予測される状態において、いかに復活するかについての本。 著者は1990年代に既にデジタルノマドワーカーを想定した講演を行っていた。 かつて日本が高シェアを誇っていた半導体産業を凋落させたのは、主にアメリカからの圧力...
日本の半導体が世界シェア50%から10%に落ち込み、今後0%すら予測される状態において、いかに復活するかについての本。 著者は1990年代に既にデジタルノマドワーカーを想定した講演を行っていた。 かつて日本が高シェアを誇っていた半導体産業を凋落させたのは、主にアメリカからの圧力と、日本製品が強かったアナログ商品から日本が世界シェアをとれなかったデジタル商品への転換、それにともなう半導体産業の垂直統合型から水平分業型への転換に対応できなかったことなどにあった。 現在は、日本内外で日本製スマホなどの完成品の需要がないため、日本製半導体デバイスの需要も生まれないという関係にある。 一方、川上の半導体材料と半導体製造装置は日本が高い世界シェアを持つ。 半導体は、過去に日米、日韓、米中の貿易問題が起こっているが、アメリカや中国、韓国に比べ、日本のトップは半導体への関心が薄いと指摘している。 スマホやデジタルデバイスで遅れをとった日本が半導体産業で復権するには、自動運転車とロボティクスにおいてシェアを獲得し、その流れに乗ることだと提言している。 自動運転車なついては、著者はアップルカーが新しいクルマの形を示すと予言しているが、スティーブ・ジョブズなきアップルにその能力があるのかは疑問。
Posted by 


