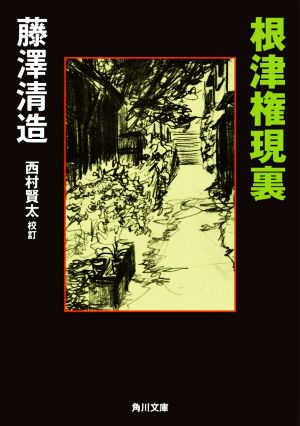
- 中古
- 書籍
- 文庫
- 1225-06-06
根津権現裏 角川文庫
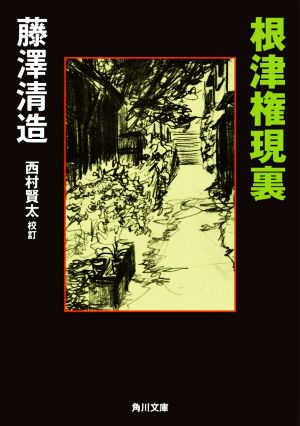
定価 ¥1,232
1,100円 定価より132円(10%)おトク
獲得ポイント10P
在庫なし
発送時期 1~5日以内に発送

商品詳細
| 内容紹介 | |
|---|---|
| 販売会社/発売会社 | KADOKAWA |
| 発売年月日 | 2020/12/24 |
| JAN | 9784041079607 |
- 書籍
- 文庫
根津権現裏
商品が入荷した店舗:0店
店頭で購入可能な商品の入荷情報となります
ご来店の際には売り切れの場合もございます
オンラインストア上の価格と店頭価格は異なります
お電話やお問い合わせフォームでの在庫確認、お客様宅への発送やお取り置き・お取り寄せは行っておりません
根津権現裏
¥1,100
在庫なし
商品レビュー
3.5
3件のお客様レビュー
1109 西村 賢太 1967年東京都江戸川区生まれ。中卒。2007年『暗渠の宿』で野間文芸新人賞、11年『苦役列車』で芥川賞を受賞。著書に『どうで死ぬ身の一踊り』『二度はゆけぬ町の地図』『小銭をかぞえる』『瘡瘢旅行』『人もいない春』『廃疾かかえて』『一私小説書きの日乗』等があ...
1109 西村 賢太 1967年東京都江戸川区生まれ。中卒。2007年『暗渠の宿』で野間文芸新人賞、11年『苦役列車』で芥川賞を受賞。著書に『どうで死ぬ身の一踊り』『二度はゆけぬ町の地図』『小銭をかぞえる』『瘡瘢旅行』『人もいない春』『廃疾かかえて』『一私小説書きの日乗』等がある。 妙な言いかたには違いないが、藤澤清造と 云えば長らく〝忘れられた作家〟の代表的な存在であった。 藤澤清造は、明治二十二(一八八九) 年に石川県の七尾に生まれている(生年を同じくする作家には、久保田万太郎、 室生犀星、内田 百、夢野久作らがある)。 人の一生において、家が焼けると云うのもなかなか経験し得ぬ不運だが、清造の不運はこの三年後に父親が急死、生家の地所は借金の担保として押さえられ、成績優秀だったにもかかわらず、経済的な理由で尋常高等小学校第四学年卒業後の進学を断念、 丁稚奉公に出されるも、間もなく右足に骨髄炎を病んで充分な処置もできぬまま、自宅療養を送る流れへと続いてゆく。 その頃の清造の 唯一 の慰めは安価で入手して読む小説であり、 殊に泉鏡花を 耽読 していた。 足の状態に小康を得てからは再び近くの 足袋屋や代書屋で働き、そこで得る僅かな賃金を貯めて明治三十九(一九〇六) 年、現代の満年齢では十六歳時に上京する。
Posted by 
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
「ああ、何時までこうした生活を続けねばならないのか。」 これは、主人公が知人宅に着物を借りに行くも叶わず、帰りしな閉店間際の鮨屋に少し詰めてもらい食べながら吐露した言葉だ。とても他人事とは思えず身に沁みた。 貧苦に加えて病苦にも囚われ抜け出せない主人公の不平不満、カネの渇望、富める者や健やかな者への羨望と嫉妬、貧乏や愚鈍への嫌悪と怨嗟、そして友人の自殺。陰鬱な繰り言・恨み言や出来事が落語か講談のような明るさと軽やかさのある文体で綴られている。持病に苦しみ、その日の食事どころか嗜好品の煙草1本すら儘ならぬ主人公の生活苦の生々しさに慄き、また本気で脱却改善を望んでいるのか判らぬ彼の中途半端な言動にかなり苛々とさせられもしたが、読み応えある一冊だった。
Posted by 
前回の読書会課題図書、 苦役列車から寡聞にして未読だったこちらを。 実は当の読書会でお借りしていたうちの1冊。 校訂は西村賢太さん。 とりあえずコチラを読んで、苦役列車の文体がなぜあんなにも古めかしく、難読漢字がたくさん出てくるのかがわかった。 めちゃくちゃリスペクトしてるのね...
前回の読書会課題図書、 苦役列車から寡聞にして未読だったこちらを。 実は当の読書会でお借りしていたうちの1冊。 校訂は西村賢太さん。 とりあえずコチラを読んで、苦役列車の文体がなぜあんなにも古めかしく、難読漢字がたくさん出てくるのかがわかった。 めちゃくちゃリスペクトしてるのね。 読む前から、内容は陰鬱で救われない私小説であるらしいと聞いていたので、心して読みはじめたんだけど… …めっちゃ面白いと思ってしまった。 確かに救われない。 貧困と病気に生活を苛まれ、 似たような境遇の友人が自ら縊死した原因についてああでもないこうでもないと模索するという、本当に陰鬱な内容。 特に最後の方は著者の頭の中の言葉がダラダラと垂れ流されているような…、 思考の行ったり来たりを追想しているような、 なんとも重苦しく、正直、 「ああ苦痛だ、長いなぁ」とも感じたものだった。しかも私小説だからたぶんどんでん返しとか劇的なカタルシスも期待できない状況で、ラスト10頁ほどを読み進めるのは結構しんどかった。 だったらどこが面白かったのか。 たぶんこれはわたしの性格の悪さゆえなのかもしれない。 とことん不幸で、不平不満を綴っているブログとか、某SNSとかを興味本位で読んでいる感覚に近い。 西村賢太さんが惹かれたのは絶対そこじゃないと思うんだけど、わたしにとっては貧困や病気、絶望感を持った人間の思考を覗き見るのは罪悪感もあるけどどうにも興味深いな、と感じてしまうのだ。 自分は絶対そうならないとは思わないけど、そうなった時に自分ならどう考えるかという予行演習をしているみたいな。 いや、やっぱり興味本位な部分が大きいな。 途中に出てくる極端なルッキズムにも嫌悪感というよりも新鮮さを感じた。 それと多分この時代背景。 大正時代くらいの小説が好きなので、この頃の東京の一端をライブ感ある文章で見られるのは単純に楽しい。 それにしても、時々読みにくいと感じるところもあったけど、全体的に端正で直線的なわかりやすい文章は現代的な校訂があったとしてもかなり良く、そこに支えられて面白いと思わされる部分も大きかった。 なんだかいろいろな感情がわいてくる味わい深い小説でした。読んで良かった。
Posted by 



