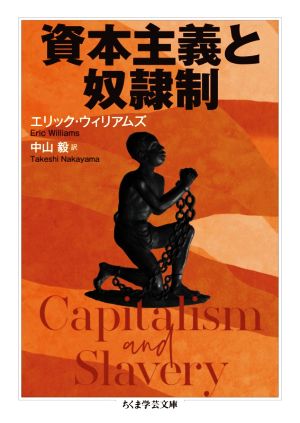
- 中古
- 書籍
- 文庫
- 1224-26-02
資本主義と奴隷制 ちくま学芸文庫
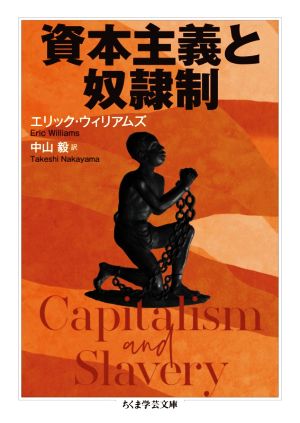
定価 ¥1,980
1,595円 定価より385円(19%)おトク
獲得ポイント14P
在庫なし
発送時期 1~5日以内に発送

商品詳細
| 内容紹介 | |
|---|---|
| 販売会社/発売会社 | 筑摩書房 |
| 発売年月日 | 2020/07/13 |
| JAN | 9784480099921 |
- 書籍
- 文庫
資本主義と奴隷制
商品が入荷した店舗:0店
店頭で購入可能な商品の入荷情報となります
ご来店の際には売り切れの場合もございます
オンラインストア上の価格と店頭価格は異なります
お電話やお問い合わせフォームでの在庫確認、お客様宅への発送やお取り置き・お取り寄せは行っておりません
資本主義と奴隷制
¥1,595
在庫なし
商品レビュー
3.8
7件のお客様レビュー
私たちが生きている時代を理解するためには、資本主義というものを理解しないといけないと思っていて、そしてそれは現代の資本主義や経済理論だけではなくて、その歴史を理解することが必要と思っている。 そういう意味で昔から読んでみたいリストにずっとあるのがウォーラーステインの「近代世界シ...
私たちが生きている時代を理解するためには、資本主義というものを理解しないといけないと思っていて、そしてそれは現代の資本主義や経済理論だけではなくて、その歴史を理解することが必要と思っている。 そういう意味で昔から読んでみたいリストにずっとあるのがウォーラーステインの「近代世界システム」であるが、これがなかなかに大著で、結構、難しげなので、前書き的な部分から先を読み始められない。 というわけで、そのための準備運動になりそうな本を少しづつ読んで前提知識をインプットしているところ。 この本は、資本主義の起源、マルクス的にいうと原始的蓄積としてのアメリカ大陸における奴隷制の存在に注目したもの。 なんというか、この本が出る前は、ウェーバー流のプロテスタントの倫理といったものが、資本主義が発展した原動力であったという理解が主流であったわけで、当時としては画期的というか論争的な本であったわけだ。 もちろん、ウェーバーの理論が全く間違っているわけでもなく、そうした宗教や国の文化が経済システムに影響を与えるというのはそうだと思う。だが、20世紀の後半以降、経済が発展しているところは移り変わっているわけで、それを国民性だけで理解することは難しい。 そして、そうした文化的なアプローチは、ある種のイデオロギーになりがちで、現実の搾取構造を綺麗な精神論でお覆い隠す役割を果たすことになる可能性がある。 さて、本書のポイントは、イギリスの資本主義の発展は、アフリカでの奴隷貿易→カリブ海やアメリカ大陸における奴隷を使ったプランテーションによる砂糖や綿などの作物→アメリカでの農作物などを使ったイギリスでの工業生産物→そしてその生産物のアフリカなどへの輸出という三角貿易による循環があったということ。 そして、このサイクルの最重要部分がアフリカでの奴隷貿易であり、ここでの富の蓄積がイギリスの経済発展の原点になったということ。 奴隷貿易というと、さぞ怪しげな、マフィア的な人々がやっているんだろうと思うが、それがなんともジェントルマンな人々なのだ。そして、植民地でプランテーション経営をやっているのは確かに一攫千金を狙う感じの人々なのだが、金持ちになって故国に帰れば、もてはやされてしまうわけだ。 19世紀になって、奴隷制に対する批判が高まり、徐々に廃止されていくわけだが、それは単に人道的なものではなく、重商主義と植民地主義的なアプローチが限界に達して、自由主義的なシステムに転換した方がより経済的に儲けることができるようになったためとのこと。 つまり、資本主義、儲けるシステムの都合で、奴隷制が正当化され、その後、廃止されるということになったということ。イギリスは、18~19世紀に重商主義から自由主義に経済的なイデオロギーの転換がなされるのだが、それはあくまでも、原始的蓄積が十分になされ、産業革命による工業生産力が増し、ヘゲモニーをとることができた、つまり、世界が市場となり、植民地経営のコストとそれが生み出す制約が邪魔になってからのことだ。 こうした現実の変化の中で、さまざまな人が、節操なく立場をコロコロと変えながら、自分の利益に都合の良い言説を述べていたということのようだ。 先日読んだラス=カサスのスペインによるアメリカのインディオの虐殺と奴隷化の後に起きたイギリスなどによる黒人奴隷によるプランテーション経営の実態がなんとなくわかってきた気がする。 1944年の本なので、現在の歴史学から見ると間違いも多いのかもしれないが、資本主義というシステムの起源について大まかに理解するにあたっては、説得力のある議論だと思った。 ちなみに、著者は歴史家であるとともに、トリニダード・トバゴ共和国の初代首相でもある。理論と実践の人なのであった。
Posted by 
黒人差別のルーツが奴隷制にあったと短絡的にイメージしていたが、アメリカにおける奴隷制のルーツを本書で捉え直すとその認識も変わる。 また、著者は奴隷貿易に当時携わった人間の人間性を否定するのではなく、当時の価値観としてそれは倫理的に問題視されていなかっただけと述べる。別の章では奴隷...
黒人差別のルーツが奴隷制にあったと短絡的にイメージしていたが、アメリカにおける奴隷制のルーツを本書で捉え直すとその認識も変わる。 また、著者は奴隷貿易に当時携わった人間の人間性を否定するのではなく、当時の価値観としてそれは倫理的に問題視されていなかっただけと述べる。別の章では奴隷制廃止論者の根拠は倫理観ではなく商業的都合であった例を取り上げている。 奴隷制や人種差別問題は、それを考える際にイメージや感情のバイアスがかかりやすいが、本書ではその認識や姿勢を改めさせてくれる。
Posted by 
【文章】 読み辛い 【ハマり】 ★★・・・ 【気付き】 ★★★・・ 奴隷の多くが黒人であったのは、人種差別的なものが元にあったからではなく、あくまで経済的な理由からであった。白人や、アメリカ先住民より、労働に対する能力が高かった。
Posted by 



