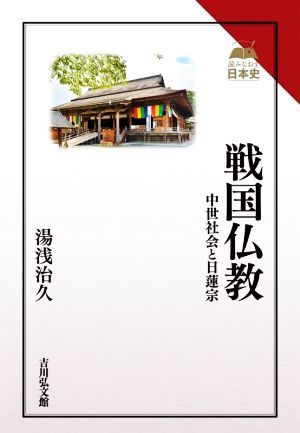
- 中古
- 書籍
- 書籍
- 1215-05-05
戦国仏教 中世社会と日蓮宗 読みなおす日本史
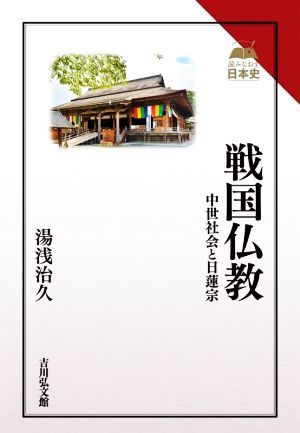
定価 ¥2,420
1,430円 定価より990円(40%)おトク
獲得ポイント13P
在庫なし
発送時期 1~5日以内に発送

商品詳細
| 内容紹介 | |
|---|---|
| 販売会社/発売会社 | 吉川弘文館 |
| 発売年月日 | 2020/06/11 |
| JAN | 9784642071185 |
- 書籍
- 書籍
戦国仏教
商品が入荷した店舗:0店
店頭で購入可能な商品の入荷情報となります
ご来店の際には売り切れの場合もございます
オンラインストア上の価格と店頭価格は異なります
お電話やお問い合わせフォームでの在庫確認、お客様宅への発送やお取り置き・お取り寄せは行っておりません
戦国仏教
¥1,430
在庫なし
商品レビュー
3.5
3件のお客様レビュー
概要 本書は「戦国仏教」の成立過程とその社会的影響を探求しており、特に日蓮宗を中心に、宗教と社会の関係性、さらには歴史的背景を詳細に分析しています。これにより、戦国時代の仏教がどのように地域社会に根ざし、民衆の信仰や実生活に影響を与えたのかを明らかにしています。 戦国仏教の定義...
概要 本書は「戦国仏教」の成立過程とその社会的影響を探求しており、特に日蓮宗を中心に、宗教と社会の関係性、さらには歴史的背景を詳細に分析しています。これにより、戦国時代の仏教がどのように地域社会に根ざし、民衆の信仰や実生活に影響を与えたのかを明らかにしています。 戦国仏教の定義と背景 - 戦国仏教とは: 戦国時代における仏教のあり方を指し、特に日蓮宗に焦点を当てています。この時代の仏教は、宗教的平等を強調し、民衆に対する救済の手段として機能しました。 - 歴史的背景: 中世の日本社会における仏教の役割、特に鎌倉仏教から戦国仏教への移行が論じられています。信仰の多様性と地域社会との関わりが強調されています。 日蓮宗の特徴 - 教えの内容: 日蓮宗は「念仏以外の行いを排除する」思想を持ち、特に法然の教えからの転換を図りました。この宗派は、全ての人々が平等に救済されるという主張を強め、社会における宗教的平等を語りました。 - 社会的関与: 日蓮宗は、地域社会の実情に深く関わり、民衆の声を反映させる形で発展しました。特に、農民や庶民との接触を通じて信仰を広め、地域に根ざした仏教の形を築くことに成功しました。 戦国時代の仏教の役割 - 社会的影響: 戦国時代の仏教は、単なる宗教的教義に留まらず、社会的な役割を果たしました。寺院は避難所として機能し、地域住民を支える存在としての役割が強調されています。 - 信仰の浸透: 地域における仏教の受容は、単なる教義の普及にとどまらず、民俗信仰との結びつきによって強化されました。例えば、地域の祭りや行事に仏教的要素が取り入れられることで、信仰が日常生活に深く根付くようになりました。 研究の意義 - 宗教と社会の相互作用の理解: 本書は、戦国仏教を通じて宗教と社会の関係性を考察する重要な資料となっています。地域の実情を反映した信仰の形が、どのように形成されていったのかを解明することで、現代における宗教の役割についても示唆を与えています。 - 歴史的な視点からの分析: 歴史的背景に基づいた分析を通じて、戦国時代の宗教的動向が現代に与える影響を考えることができます。 結論 本書は、戦国時代の仏教がどのように地域社会に深く根差し、民衆の生活に影響を与えたのかを明らかにすることで、宗教と社会の相互作用を深く探求しています。日蓮宗を中心に、仏教の多様な側面を探ることで、戦国仏教の成立過程とその意義を理解することができます。
Posted by 
2009年刊行本の再刊。中世日本における日蓮宗を主な題材として、いわゆる新仏教が戦国時代の地域社会に浸透していく過程を描く内容。物流や町場・村落の発展と絡み合いながら教線を伸ばし、また変質していく様相が興味深かった。
Posted by 
いわゆる鎌倉仏教の位置付けは、顕密体制論により大きく修正を迫られたが、一向宗や法華宗、禅宗等が社会に浸透し、影響力を持つようになったのは戦国時代であることから、これを「戦国仏教」という概念で捉えようという提唱がある研究者からなされた。 そうした動きを受け、著者は、本書において...
いわゆる鎌倉仏教の位置付けは、顕密体制論により大きく修正を迫られたが、一向宗や法華宗、禅宗等が社会に浸透し、影響力を持つようになったのは戦国時代であることから、これを「戦国仏教」という概念で捉えようという提唱がある研究者からなされた。 そうした動きを受け、著者は、本書において、鎌倉仏教、特に日蓮宗が現実社会に浸透していく過程を跡づけようとする。 親鸞や日蓮、道元といった祖師については、その生涯であたり、著作を少し読んだりしたことはあるが、確かに宗教が現実に力を持つためには、支配階級から庶民階層に至るまで、その教えが広まらなければならない、その展開過程については、これまであまり関心を持たずに来てしまった。 教えの純粋性を守り原理主義の道を行くのか、それとも多少の妥協はするにせよ、広く布教を目指すのかといった教義、方向性の違いによる争いや、寺院が社会のネットワークとなり、地域金融や流通に大きな役割を果たしていたことなど、新しく知ることができた。 *直接内容に関わることではないが、本書は、2009年中公新書として刊行され、今回、吉川弘文館の『読みなおす日本史』シリーズから改めて刊行になった。10年前には、こうしたテーマに関心がなかったので、新書という目に留まりやすいものなのに、全く見た記憶もない。人文書のような学ぶ者の共有財産がこのような形で甦えることは、誠に嬉しいことである。応援しています。
Posted by 



