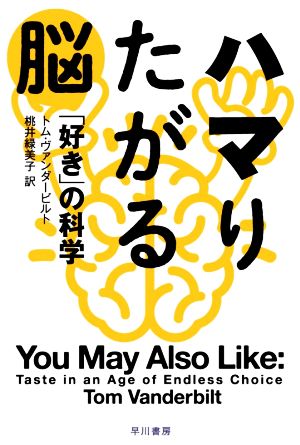
- 中古
- 書籍
- 文庫
ハマりたがる脳 「好き」の科学 ハヤカワ文庫NF
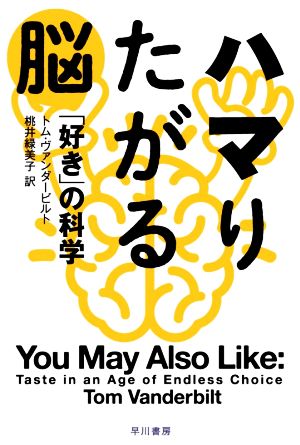
定価 ¥1,254
¥385 定価より869円(69%)おトク
獲得ポイント3P
在庫なし
発送時期 1~5日以内に発送

商品詳細
| 内容紹介 | |
|---|---|
| 販売会社/発売会社 | 早川書房 |
| 発売年月日 | 2020/06/04 |
| JAN | 9784150505585 |
- 書籍
- 文庫
ハマりたがる脳
商品が入荷した店舗:0店
店頭で購入可能な商品の入荷情報となります
ご来店の際には売り切れの場合もございます
お客様宅への発送や電話でのお取り置き・お取り寄せは行っておりません
ハマりたがる脳
¥385
在庫なし
商品レビュー
3.3
4件のお客様レビュー
前略。体操選手の審査員は、順位をつける必要があるので、最初の方の演技には控えめな得点をつけがちであったり、難度と完成度は独立しているはずなのに不自然に相関してしまうなど。こう考えると審判が存在するあらゆる競技の不公平さ、特に評点で優劣が決まる体操やスケートなどの競技は人間心理が暗...
前略。体操選手の審査員は、順位をつける必要があるので、最初の方の演技には控えめな得点をつけがちであったり、難度と完成度は独立しているはずなのに不自然に相関してしまうなど。こう考えると審判が存在するあらゆる競技の不公平さ、特に評点で優劣が決まる体操やスケートなどの競技は人間心理が暗黙に混入している。特に逐次的に進行する場合、不可逆になる。
Posted by 
好きな音楽は?と聞かれたらみなさん何と答えますか?ぼくはスピッツが好きです。どれかひとつの曲に絞れ、と言われたらどうしよう。マイナーだけど「君と暮らせたら」かな? じゃあ好きな音楽はなぜ好きなのでしょうか?ぼくはどうしてスピッツが好きなのか。どこか懐かしさのあるポップなサウンド...
好きな音楽は?と聞かれたらみなさん何と答えますか?ぼくはスピッツが好きです。どれかひとつの曲に絞れ、と言われたらどうしよう。マイナーだけど「君と暮らせたら」かな? じゃあ好きな音楽はなぜ好きなのでしょうか?ぼくはどうしてスピッツが好きなのか。どこか懐かしさのあるポップなサウンドが好き。草野さんの高くて柔らかい日本語的な歌声が好き。一見よくわからないけれど奥深い歌詞が好き。。。 と、理由を書いてみましたが、ほんとうにそうだから好きなのでしょうか?ぼくは、スピッツが好きだから好きなのであって、ここに書いたのは後付けの理由ではないか。ただ単にスピッツの特徴を書いただけではないのか。 これが、食べ物の話だったらもう少し分かりやすいんです。甘いものが好きなのは、糖分は重要な栄養素だからですし、苦いものが嫌いなのはそれが毒かもしれないからです。好き嫌いに従って食べたほうが生存できる可能性が高いし、進化論的にもそのような好みが生き残る。 しかも、味が分からない状態でも、ヒトは甘いものを好むようです。ある実験では、被験者に、糖の入った錠剤を紅茶と一緒に飲ませた場合と、ただの錠剤を紅茶と一緒に飲ませた場合とで紅茶の味を比較させました。錠剤だから味はしないはずなんですが(噛んじゃダメだよ笑)、被験者は糖の錠剤と一緒に飲んだ紅茶を好みました。腸で吸収された糖分から、報酬系を通じて被験者は美味しさを感じたようです。 でも音楽ではこうはいきません。どんな音楽を聴いていようが、それで死ぬことはありませんから。他方、食べ物にしろ音楽にしろ、ヒトは慣れ親しんだものを好きになるということが確かめられています。これは単純接触効果というのですが、たしかに、小さい頃からぼくはスピッツに囲まれて過ごしていました。親が好きで「CRISPY!」以降のアルバムはぜんぶ家にありましたし、クルマに乗るとよくかかっていた。知らず知らずにスピッツが好きになっていき、心地いいと感じるようになったわけですね。 音楽や映画などの趣味については、デブリューが「ディスタンクシオン」のなかで、社会的地位との相関が大きく、むしろ自身の文化資本を見せつけて他者との差異化を図る目的で使われていると指摘しています。自分のステータスを示すためにオペラを観たりクラシック音楽を聞いたりする。これも一理あって、(あまり大声では言いたくないが)スピッツ好きって言ってる自分カッコいいみたいなのは多少あるんです。(いま、「ラズベリー」を聴きながらこれを書いているから、それでいいのか?という気もしてきたが)スピッツの爽やかな感じに寄せることで、自分のイメージを操作したいっていう思いはなくはない。ただ、現代はデブリューの時代と違って、みんながAmazonとかSpotifyにアクセスできますから、趣味に対するコストが当時と違っている点には留意が必要です。 流行りについてはどう考えればいいでしょうか。あるときはこのアーティストが好きだったけど、あるときは違うアーティストが好きだ、ということはよくあります(ぼくはスピッツ一筋ですよ!、、、ほとんど、だいたい、、、)。ヒトには模倣する習慣があります。自然と他人の(よい行いを)真似をすることで、社会的に学習が進んでいきます。他方で、模倣するだけでは社会は進歩しません。ひとと違うことをしたいという機能も備わっていて、そのときの発見が社会に利益をもたらします。このバランスで流行りは移り変わっていきます。つまり、多くのひとがマネをすると流行るけれど、少しずつ違うことをする個体がいて、あるときに違う何かが真似されて流行っていく。そんな感じです。 ふだん生きていると「好き」は身近すぎてあまり深く考えませんが、こうして見ていくと不思議なことだと思いませんか?それって面白くないですか? というわけで、本紹介のはずがほぼスピッツの話になってしまいましたが、スピッツ好きのひとがいたら仲良くしてください。
Posted by 
Netflixのおすすめメカニズムなど興味深い事例はじめ豊富。なかばから、音楽、食の事例が満載されている。訳者によるあとがきが、要約としてよくまとまっている。
Posted by 

