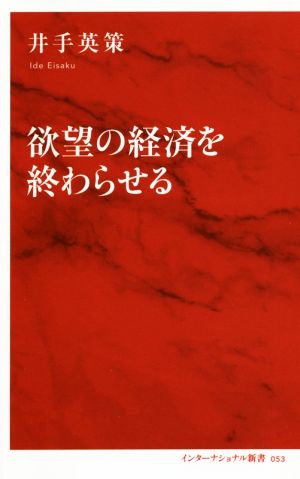
- 中古
- 書籍
- 新書
欲望の経済を終わらせる インターナショナル新書053
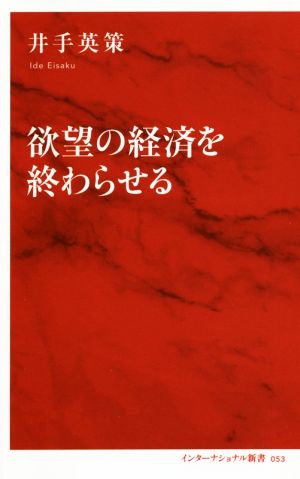
定価 ¥968
220円 定価より748円(77%)おトク
獲得ポイント2P
在庫なし
発送時期 1~5日以内に発送

商品詳細
| 内容紹介 | |
|---|---|
| 販売会社/発売会社 | 集英社インターナショナル/集英社 |
| 発売年月日 | 2020/06/05 |
| JAN | 9784797680539 |
- 書籍
- 新書
欲望の経済を終わらせる
商品が入荷した店舗:0店
店頭で購入可能な商品の入荷情報となります
ご来店の際には売り切れの場合もございます
オンラインストア上の価格と店頭価格は異なります
お電話やお問い合わせフォームでの在庫確認、お客様宅への発送やお取り置き・お取り寄せは行っておりません
欲望の経済を終わらせる
¥220
在庫なし
商品レビュー
3.5
7件のお客様レビュー
同じ著者の本を読んだので続いて。 主張されている内容に特に変わりなし。 私の感想も特に変化なし。 頼りあえる社会に生きたいと願うし、それが達成出来るのであれば高負担もやむなしという事は理解出来ます。
Posted by 
本書では、財政をフル活用することで国民に対して無差別に「ベーシック・サービス」(医療、教育等)を提供し、それによって各人が安心・安全な生活を送れるようにすることを提唱しています。そのためには消費税を20%くらいにまで引き上げる必要があるとのこと。著者の主張が本当に効果的かどうかは...
本書では、財政をフル活用することで国民に対して無差別に「ベーシック・サービス」(医療、教育等)を提供し、それによって各人が安心・安全な生活を送れるようにすることを提唱しています。そのためには消費税を20%くらいにまで引き上げる必要があるとのこと。著者の主張が本当に効果的かどうかは別にして、感じた点を列挙します。 まず、本書における新自由主義批判は、カール・ポランニーの思想を焼き直して日本の特殊な状況にあてはめようとしている印象を受けたこと。その意味で日本が米国などと異なる点についての解説は有効だと感じました。他方、著者が主張する「ベーシック・サービス」とは、ジョン・ロールズの基本財の「財」をサービスにしたものであって、特に目新しいものではないこと。そう考えると、ロールズに批判を加えたアマルティア・センの主張が頭をよぎるわけです。つまり、ベーシック・サービスを国民全員に無差別に提供しますよ、といっても、それを行使する能力(ケイパビリティ)には当然差があるわけで、ケイパビリティの高い人ほど良いサービスを受けられることになるということで、ベーシックサービスの提供、だけでは片手落ちだということです。 最後に、本書で大きな違和感を持った箇所として、著者が財政を互酬の視点から論じていることです。互酬とは二者間の関係が対等であることが大前提であって、税金を取られる側と徴収する側に対等な関係性があると考えるのはあまりにナイーブでしょう(たとえ西側諸国の政府は国民のhumble servantだと建前上は言っていたとしても)。財政とは「略取と再分配」なのです。本書の中では「公・共・私のベストミックス」という概念が提唱されていますが、公が過半、いや7割くらいになることをもってベストミックスと呼んでいるのではないかという印象を持ちました。また財政学者である著者が財政のフル活用を主張しても何の驚きもなく、もしそこを主張するのであれば、市場原理主義との比較だけでなく、他の選択肢と比べて財政が格段に良い理由を丁寧に述べるべきでしょう。なぜコミュニタリアニズムよりも良いのか、あるいはシェアリング・エコノミーのように、純粋贈与と市場経済のハイブリッド型のようなスタイルよりもなぜ財政を活用するほうが良いのか。私は個人的には財政よりもシェアリング・エコノミーの発展に期待を持っており、新自由主義を終わらせるのは財政ではなくデジタルテクノロジーだと思っています。
Posted by 
新自由主義は政府にGDPの上昇を至上命令とさせる。そして、GDPは市場の活動によってもたらされるのだから、市場に適さないものまで市場化される。公的な財源によってまかなわれていたことまで、市場へと。それが財政削減へとつながり、福利は縮小し、あまねく行き渡らなくなってしまった。 ...
新自由主義は政府にGDPの上昇を至上命令とさせる。そして、GDPは市場の活動によってもたらされるのだから、市場に適さないものまで市場化される。公的な財源によってまかなわれていたことまで、市場へと。それが財政削減へとつながり、福利は縮小し、あまねく行き渡らなくなってしまった。 そのために、機能不全に陥っている家族と共同体を、セーフティネットとして復権させようとした、そのような能力は、もはやないのに。これはまず、自助・自己責任があって、それに障害がおこると、かつて、そうであったとされているような、家族や共同体という共助が働く、というのは、過去への願望の投影でしかない。当時は「自己責任」などという発想はなかった、にもかかわらず。 「平成30年国民生活基礎調査」では、生活が苦しいのは国民の6割だったが、4.2%しか下層と認識していない。低所得者は貧困になるかもしれないという恐怖から目を背けようと、ギリギリ中流、という幻想にしがみつく、視線をより下層に向けて。切実なのに「反貧困」という言葉は他人事、とやり過ごされるのだ、と指摘する。 そもそも、日本では労働人口にしめる公務員の割合は低く、企業などの労働生産性は低い。企業が多すぎるために、競争による利益の減少があり、人材を必要なところへ配置できなくなってしまっている。つまり、〈政府は互酬や再配分の原理でできている。たとえ収支が赤字になっても、人間の命、くらしのためのサービスを提供する役割を担っている。一方、交換の原理に支えられた企業の目的は、より多くの利潤を手にすることだ。したがって、収支が赤字になれば、サービスの提供を打ちきるのは当然である。次元のちがうふたつの領域をくらべ、公務員の数を減らすイコール効率化と考えるのはあまりにも短絡的である〉、と述べられている。
Posted by 



