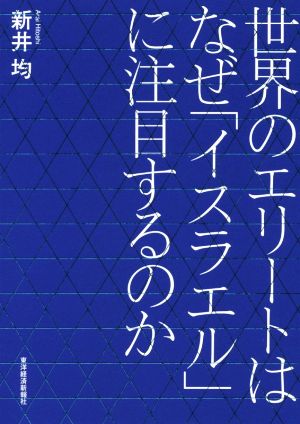
- 中古
- 店舗受取可
- 書籍
- 書籍
- 1209-02-08
世界のエリートはなぜ「イスラエル」に注目するのか
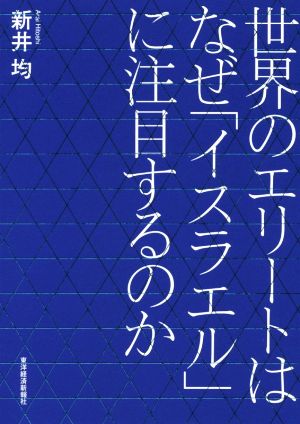
定価 ¥1,760
220円 定価より1,540円(87%)おトク
獲得ポイント2P
在庫わずか ご注文はお早めに
発送時期 1~5日以内に発送

店舗受取サービス対応商品
店舗受取なら1点でも送料無料!
店舗到着予定
2/21(金)~2/26(水)

商品詳細
| 内容紹介 | |
|---|---|
| 販売会社/発売会社 | 東洋経済新報社 |
| 発売年月日 | 2020/05/22 |
| JAN | 9784492503195 |


店舗受取サービス
対応商品
店舗受取なら1点でも送料無料!
さらにお買い物で使えるポイントがたまる
店舗到着予定
2/21(金)~2/26(水)
- 書籍
- 書籍
世界のエリートはなぜ「イスラエル」に注目するのか
商品が入荷した店舗:0店
店頭で購入可能な商品の入荷情報となります
ご来店の際には売り切れの場合もございます
オンラインストア上の価格と店頭価格は異なります
お電話やお問い合わせフォームでの在庫確認、お客様宅への発送やお取り置き・お取り寄せは行っておりません
世界のエリートはなぜ「イスラエル」に注目するのか
¥220
在庫わずか
ご注文はお早めに
商品レビュー
3.8
10件のお客様レビュー
確実に読んで欲しいと書いてあった4章がかなりイマイチだった。『でしょうね』というのが単純な感想。IT分野の功績を多く残しているプログラムであれば、もっとプログラムの内容に突っ込んでITのやってることや活かされ方、教育現場の実態などの素描が描かれていて欲しかった。 たしかに幼き頃の...
確実に読んで欲しいと書いてあった4章がかなりイマイチだった。『でしょうね』というのが単純な感想。IT分野の功績を多く残しているプログラムであれば、もっとプログラムの内容に突っ込んでITのやってることや活かされ方、教育現場の実態などの素描が描かれていて欲しかった。 たしかに幼き頃の習慣やそれを支える教育と文化、プログラムの考えとやり方はいいのだろう。それは結果論から関連性はわかる。じゃあ、因果関係は?おそらくそこまで分析されていないことはわかる。 全体的には、タイトル『世界のエリートは』という主語への観点や見解が抜けてる。じゃあなぜ世界のエリートは移民としてイスラエルでプログラムを受けてはいないのか?他の国での同じプログラムの採用実績や類似事象は?おそらくエリート、というか投資家だろう。最高技術の世界進出の契機や流れは?世界にどう売り出しどう技術を作り出し国がどう関わっているか?IT業界にいる人から見ると本書はその観点で学びを得ない。 全体的に、イスラエルの功績にけっこうページを割いていて示唆に富んでいるが、これは調べればわかる。情報が散らばっていることとなぜ?特に因果関係が薄いのが本書の欠点。われわれ日本人が学ぶべき結論が少し的を外してる気がする。あまりスッと入ってくる内容は少なかった。わたし自身イスラエルに行ったことがあり、世界各国で屈強なイスラエル人に会ってきただけに、本書でイスラエルの良さはわからない。非常に勿体無い。 なにが言いたいのか明確にしてほしかった。タイトルのような聡明は内容はなく、『初学者向けイスラエルの紹介』という概要であればこの本は適切だ
Posted by 
前々から読みたかった本。 イスラエルは技術大国と聞いたことがあったので。 イスラエルの文化や背景、また、著者は日本人なので日本と比較したときのイスラエルの特徴などわかりやすく書かれており、勉強になった。 一国の話なんだけれども、個人に置き換えたときにも当てはまることが書かれてい...
前々から読みたかった本。 イスラエルは技術大国と聞いたことがあったので。 イスラエルの文化や背景、また、著者は日本人なので日本と比較したときのイスラエルの特徴などわかりやすく書かれており、勉強になった。 一国の話なんだけれども、個人に置き換えたときにも当てはまることが書かれていたので、そう言う意味でも勉強になる。(仕事への向き合い方など) 以下、印象的なシーン 1. インテルのプロセッサ「セントリーノ(2003)」 →自動車の変速機からアイデアを得たところがポイント(エンジンの回転数を上げることなく、変速機のギアを切り替える→クロック周波数を変えないまま、処理速度を上げる) 仕組みを応用できることがすごい。 2. 本を与える。親自身が本を読んでいるところを子供に見せる。 →こんな親になりたい。好奇心旺盛な子を育てたい。 3. エリート養成プログラム(表) → 年度に応じて各カテゴリの求められるレベルがわかりやすくまとめられている。こういう表わかりやすいなぁ 4. 日本人は無意識に明日が昨日と大きく変わることはないだろうと考えるが、イスラエルの人々は明日はどうなるかわからないと考える → これ、仕事で上手く考え方として定着させたい。どちらかというとどう相手をその気にさせるかな気がする 5. 肌感覚だが、イスラエルの企業のQAでは、ざっくり70%程度のテストケースでOKであればできたと言う。ソフトウェア開発の基本はdevopsである。 → これ、生産現場とかのソフトウェア開発だと本当に100%求められるから、どんなジャンルに適用するかで変わると思う。 6. もはやハードウェアは、付加価値を生み出すソフトウェアのイネーブラ(手段)であるという認識に立つべきである → 一日本のサラリーマン、エンジニアとしてどうしていくのがいいか、絶賛悩み中です。
Posted by 
・本。親自身が楽しく本を読む様子。本棚には百科事典や地図を。 ・子の自主性を尊重し、何かを押し付けることはしない。 ・様々な体験をさせる。 ・子の意見を聞き、褒める。 意見を聞いてもらえる=自分の価値を認めてもらっている、自身につながる。聞かれたことに答えるためには、自分で考...
・本。親自身が楽しく本を読む様子。本棚には百科事典や地図を。 ・子の自主性を尊重し、何かを押し付けることはしない。 ・様々な体験をさせる。 ・子の意見を聞き、褒める。 意見を聞いてもらえる=自分の価値を認めてもらっている、自身につながる。聞かれたことに答えるためには、自分で考え、自分の言葉で表す必要があり、物事を理解するよい特訓に。(どんな話題でも親子がよく議論を戦わせるのがユダヤ人の家庭らしい) ・言葉と態度で信じていることを示す。 ・子が間違いを起こした場合は論理的に説明して罰を与える。信じることは放任ではない。 ・時期が来たら親離れさせる。 *ジューイッシュ・マザーという言葉があるが、イスラエルの人々は、子どもの教育を学校や塾に任せるのではなく、自身が大きく関わっている。むしろ子どもの教育は国や学校ではなく家庭が行うことと考えている。 親がいかにして子供の能力を引き出すか。 子と向き合う時間をできるだけ作り、様々な感動体験ができるような場に連れ出し、色々な場面で子の意見を引き出すように心がけている。
Posted by 


