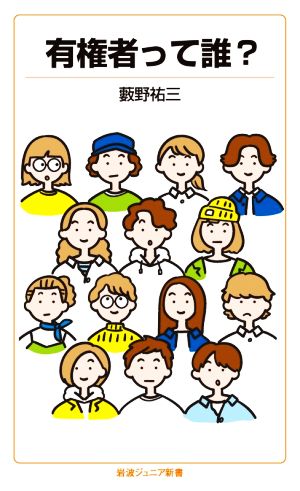
- 中古
- 書籍
- 新書
- 1226-15-01
有権者って誰? 岩波ジュニア新書
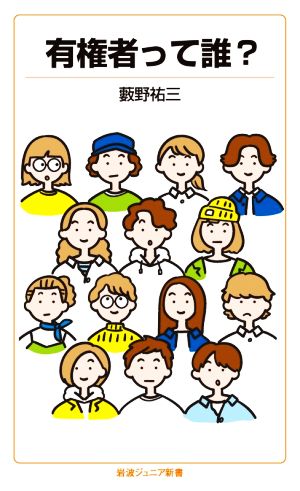
定価 ¥880
605円 定価より275円(31%)おトク
獲得ポイント5P
在庫なし
発送時期 1~5日以内に発送

商品詳細
| 内容紹介 | |
|---|---|
| 販売会社/発売会社 | 岩波書店 |
| 発売年月日 | 2020/04/19 |
| JAN | 9784005009176 |
- 書籍
- 新書
有権者って誰?
商品が入荷した店舗:0店
店頭で購入可能な商品の入荷情報となります
ご来店の際には売り切れの場合もございます
オンラインストア上の価格と店頭価格は異なります
お電話やお問い合わせフォームでの在庫確認、お客様宅への発送やお取り置き・お取り寄せは行っておりません
有権者って誰?
¥605
在庫なし
商品レビュー
4
6件のお客様レビュー
「投票のすすめ」の内容が心に刺さった。 選挙なんて意味ない、行ってもしかたない、自分の1票なんて関係ない、何も変わらないとしたり顔で言う人、思っている人に読んでほしい。1票では変わらないかもしれない。でも、そう思って投じる人が重なっていくと、「微力」にはなるかもしれない。 今回...
「投票のすすめ」の内容が心に刺さった。 選挙なんて意味ない、行ってもしかたない、自分の1票なんて関係ない、何も変わらないとしたり顔で言う人、思っている人に読んでほしい。1票では変わらないかもしれない。でも、そう思って投じる人が重なっていくと、「微力」にはなるかもしれない。 今回の都知事選で、国政選挙も大事だけれど、地方選挙もより私たちの生活に直結していて、こちらもとても大事だなということを改めて考えた。 市議会、都議会、傍聴してみたい。 選挙は投票して終わりではない。そこから始まるのだ。
Posted by 
○新書で「学校生活」を読む① 藪野祐三『有権者って誰?』(岩波ジュニア新書、2020年) ・分 野:「学校生活」×「社会を読む」 ・目 次: はじめに 第1章 有権者には4つのタイプがある 第2章 浮動票という言葉が使われた時代があった 第3章 無党派層が現代日本の政...
○新書で「学校生活」を読む① 藪野祐三『有権者って誰?』(岩波ジュニア新書、2020年) ・分 野:「学校生活」×「社会を読む」 ・目 次: はじめに 第1章 有権者には4つのタイプがある 第2章 浮動票という言葉が使われた時代があった 第3章 無党派層が現代日本の政治を支配している 第4章 有権者をとりまく社会は流動化している 第5章 選挙の前に足元の社会を知る あとがき ・総 評 本書は、日本の有権者の多くが「無党派層」(=支持する政党が固定化していない人たち)になってしまった経緯について分析した本です。著者は現代政治分析を専門とする研究者で、九州大学名誉教授などを歴任している人物です。 近年、選挙権年齢が「18歳以上」に引き下げられる一方で、特に若者層の投票率の低さが大きな議論になっています。本書は、単に「投票に行くべき」と主張するのではなく、なぜ、私たちが選挙に行かなくなってしまったのかという“理由”に注目している点がユニークと言えます。この本を読んで面白いなと思った点を、以下の3点にまとめます。 【POINT①】なぜ、私たちは選挙に行かないのか?① —— 政治の視点から考える 無党派層が増えたのは、バブル経済が崩壊した1990年以降と言われています。それまでは好景気を背景に政治も安定し、少数の政党(自民党や社会党など)が議席を分け合っていたため、有権者も選挙の争点によって政党を選択することはありませんでした。しかし、バブル崩壊後の「平成不況」下では、多くの新党が登場しては集合離散を繰り返す一方で、不況による財政難で大胆な予算措置が採れず、各政党が生活問題や就職問題について「明確な政策の争点」を打ち出せませんでした。その結果として「どの政党を支持しても結果はそれほど変わらないという意識」が広がり、無党派層が増加したと著者は指摘しています。 【POINT②】なぜ、私たちは選挙に行かないのか?② —— 社会の視点から考える 無党派層が増えた背景には、社会の「個人化」の流れがあります。従来の政治は、企業や家庭、地域といった「組織」が抱える問題の解決を重視してきました。一方で、現代では、終身雇用の崩壊や共働き家庭の増加、さらには進学や就職を機とした居住地の流動化などにより、そうした「組織」から離れた(はじき出された)人々が増加しています。しかし、こうした「個人化した人々」の利益を集約して政治の場に運ぶ組織がないため、政治も「個人が抱えている個別の問題」に対処できずにいます。その結果、政治に「自分たちの問題を解決する力がない」という意識が強くなり、無党派層が拡大したと著者は指摘しています。 【POINT③】どうしたら、私たちは選挙に行くようになるのか? 今後、私たちが持つことになる選挙権の意義を理解するためには、社会の「ひずみ」を知ることが重要だと言います。まずは自分の住む地域の人口構成から都市構造や産業などを含めた情報を調べ、その足元を少し注意してみることで「ひずみ」に気づくことができます。具体的には、地元で活動しているNPO活動に参加したり、地方議会を傍聴したりすることを著者はオススメしています。こうして知った「ひずみ」を解決したいと思った時、私たちは“有権者”として、その問題を取り組んでくれる政治家を選ぶという役割を担うことができると著者は指摘しています。 本書では、私たちが、政治に関心を持てずに「無党派層」へなってしまう理由を分かりやすく解説しています。ただし、著者はこうした状況を諦めるのではなく、消費税が導入された1990年の総選挙や、政権交代が実現した2009年・2012年の総選挙などを例に、有権者の「心を一突きする動機」さえあれば、政治は大きく変わると指摘しています。そのためには、多くの有権者の心と心を通わせる「ハート・ワーク(感動の伝達)」が必要であり、まずは自分たちの住む地域の課題を知ることが、その第一歩となります。政治ってよく分からないし、18歳になっても面倒だから選挙には行かないな...と思っている人にこそ、読んで欲しい一冊です。 (1464字)
Posted by 
図書館のティーンズコーナーに置いてあった。選挙特集って珍しいなと思って借りてみた。 自社さ連立政権の経緯など簡単に説明してくれてよかった。支持政党あるが投票に行かない浮動票、消費税導入で自民党から離れる支持者。増える無党派層。経団連や労働組合などこれまでの利益団体に当てはまらない...
図書館のティーンズコーナーに置いてあった。選挙特集って珍しいなと思って借りてみた。 自社さ連立政権の経緯など簡単に説明してくれてよかった。支持政党あるが投票に行かない浮動票、消費税導入で自民党から離れる支持者。増える無党派層。経団連や労働組合などこれまでの利益団体に当てはまらない個人化する社会。 自分は消費者としての有権者、常連としての有権者ってところかな。地元のこと(県と市の人口、基幹産業)知るところから始めて、市民としての有権者に近づいていきたいと思った。
Posted by 



