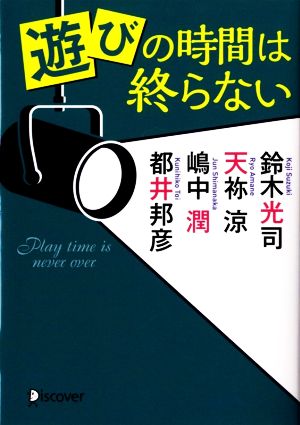
- 中古
- 書籍
- 文庫
- 1225-03-00
遊びの時間は終らない
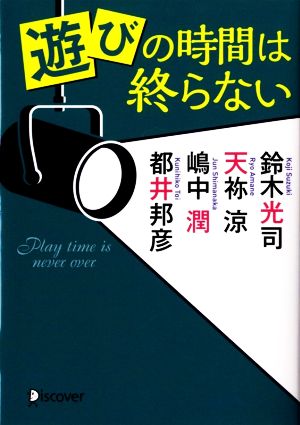
定価 ¥880
220円 定価より660円(75%)おトク
獲得ポイント2P
在庫なし
発送時期 1~5日以内に発送

商品詳細
| 内容紹介 | |
|---|---|
| 販売会社/発売会社 | ディスカヴァー・トゥエンティワン |
| 発売年月日 | 2019/12/22 |
| JAN | 9784799325797 |
- 書籍
- 文庫
遊びの時間は終らない
商品が入荷した店舗:0店
店頭で購入可能な商品の入荷情報となります
ご来店の際には売り切れの場合もございます
オンラインストア上の価格と店頭価格は異なります
お電話やお問い合わせフォームでの在庫確認、お客様宅への発送やお取り置き・お取り寄せは行っておりません
遊びの時間は終らない
¥220
在庫なし
商品レビュー
3
4件のお客様レビュー
都井邦彦著「遊びの時間は終らない」とそれにちなんだ作品のアンソロジーだそうで表題作は確かに楽しかったのですが他の作品はそれほどの爽快感がありませんでした。 ■心覚えのための簡単なメモ [▽]鈴木光司「生きる時間は終わらない」/脚本家、スランプ、樹海取材、自殺者、遺留品、ラブド...
都井邦彦著「遊びの時間は終らない」とそれにちなんだ作品のアンソロジーだそうで表題作は確かに楽しかったのですが他の作品はそれほどの爽快感がありませんでした。 ■心覚えのための簡単なメモ [▽]鈴木光司「生きる時間は終わらない」/脚本家、スランプ、樹海取材、自殺者、遺留品、ラブドール。 [△]天祢涼「遊びの時間は終わっても」/炎上、特定厨、連続殺人者、モザイクアプローチ、記号化。 [△]嶋中潤「遊びの時間が凍りつく」/ロシア、宇宙開発、モスクワ、蚤の市、ブランのタイル、詐欺に引っ掛かりやすいオーラ、地下鉄駅。 [○]都井邦彦「遊びの時間は終わらない」/銀行強盗対策訓練、犯人役刑事の予定外の行動、解決できない警察の焦り、大にぎわいの吉祥寺、日本中にテレビ中継、終われない訓練。
Posted by 
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
タイトル作『遊びの時間は終らない』のトリビュート作品集。表題作含む4篇のうち3篇が本書のための書き下ろしという豪華仕立て。3篇いずれもどんでん返し系。 私は表題作の事は知らずに読んだが何ら支障なし。 〈生きる時間は終らない〉 『リング』の鈴木光司先生という先入観からゴリゴリのホラーなのかと思いきや徐々に話の方向がおかしな方にズレていく。バスルームのドアがそろりそろり開くシーンの緊張感が半端じゃない。 明日の事も見えていなかった隆と西野が3ヶ月前の出来事を境にぐるりと前向きになる結末が心地良い。 〈遊びの時間は終っても〉 ネット探偵モノと呼べるミステリー。前半では絶賛炎上中の「ギュー子」を特定すべく主人公は捜査を開始するが、調査を進めるうちに事態は急転し…。コンパクトながら綺麗に伏線が拾われていくカタルシスがたまらん。 〈遊びの時間が凍りつく〉 「ロシア」という舞台設定から既に読者は術中に嵌っている…と言いたいが、持っていき方がやや強引だったかなと。というか、そもそも本作は『天穹のテロリズム』という別作品(私は未読)のスピンオフであるからして、主人公・青木のキャラがこれで正しいのかの判断が付きかねる。一見クールだけど実は間抜け、という二枚目半としては正しいのかも。 〈遊びの時間は終らない〉 直しが入っているようだが、初出が1984年というのが信じられないくらい古びない作品。今読んでも違和感が無いどころか、組織に於ける事なかれ主義だとか上層の人間の責任転嫁体質だとか隠蔽気質は何も変わってはいない。問題が起こるとすぐにリーダーを取っ替えて解決を図ろうとする点も全く一緒。失敗を経験に換えて乗り越える、みたいな思想が無いんだよな。 大衆に迎合し、且つ小事を大事に捉えるあまりどんどんおかしな事態になっていく様は、仕事の名を借りた’ごっこ遊び’に成り果てる。風刺に満ちた一作。 幕の内弁当みたいな、面白い作品集だったと思う。 1刷 2021.10.19
Posted by 
タイトルが面白い。 表題作、面白いと思いつつも何となくすっきりしない。 映画化されたというが一度観てみたい。
Posted by 



