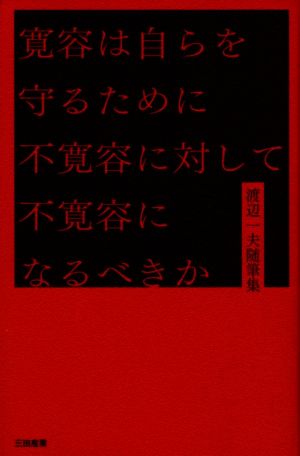
- 中古
- 書籍
- 書籍
- 1220-05-08
寛容は自らを守るために不寛容に対して不寛容になるべきか 渡辺一夫随筆集
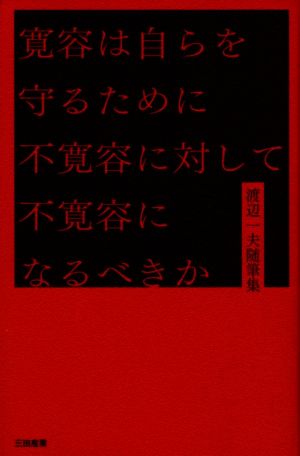
定価 ¥2,200
1,980円 定価より220円(10%)おトク
獲得ポイント18P
在庫なし
発送時期 1~5日以内に発送

商品詳細
| 内容紹介 | |
|---|---|
| 販売会社/発売会社 | 三田産業/トランスビュー |
| 発売年月日 | 2019/11/18 |
| JAN | 9784991006623 |
- 書籍
- 書籍
寛容は自らを守るために不寛容に対して不寛容になるべきか
商品が入荷した店舗:0店
店頭で購入可能な商品の入荷情報となります
ご来店の際には売り切れの場合もございます
オンラインストア上の価格と店頭価格は異なります
お電話やお問い合わせフォームでの在庫確認、お客様宅への発送やお取り置き・お取り寄せは行っておりません
寛容は自らを守るために不寛容に対して不寛容になるべきか
¥1,980
在庫なし
商品レビュー
4.5
2件のお客様レビュー
ある書籍で紹介されていたので、タイトルに惹かれて読んでみました。渡辺一夫氏はこれまで存じ上げなかったのですが、仏文の大家で大江健三郎氏のお師匠さんだそうです。 「寛容の武器としては説得と自己反省」しかなく、「常に無力であり、敗れ去るもの」ながら、不寛容に報いるのに不寛容とな...
ある書籍で紹介されていたので、タイトルに惹かれて読んでみました。渡辺一夫氏はこれまで存じ上げなかったのですが、仏文の大家で大江健三郎氏のお師匠さんだそうです。 「寛容の武器としては説得と自己反省」しかなく、「常に無力であり、敗れ去るもの」ながら、不寛容に報いるのに不寛容となることは「寛容の自殺」とあります。 カエサルは、「寛容」を国是とし、敵や異民族も受け入れたそうですが、これに注意されると以下のように語ったと言われています。 私が自由にした人々が 再び私に剣を向けることになるとしても そのようなことには 心をわずらわせたくない 何ものにもまして 私が自分自身に課しているのは 自らの考えに忠実に生きることである だから他の人々も そうであって当然と思う 結局は、不寛容な人に暗殺され、寛容は「敗れ去る」結果であったということでしょうか。今も、批判・非難という不寛容が飛び交っていますが、静かに説得という武器で応戦するしかないのでしょう。 本書は、随筆集となっていますが、最後の「偽善の勧め」も良かったと思います。偽善者となって、八方美人ではなく、「千方美人、万方美人、億方美人、兆方美人」になることを勧めています。結局、偽善も極めれば、完璧な善になるということ。こうした論調は、初めてでしたので掲載させていただきます。
Posted by 
採用時、当時の理事から「仏文科卒業生なのに読んでいないとは」とお叱りを受けた渡辺先生の本をようやく読めた。 岩波文庫版と迷って、初めて聞く出版社の本書を選んだが、内容は非常に読みやすかった。 解説などが一切ないのでこの出版社の編集の意図がよくわからないが、渡辺先生の書かれたものの...
採用時、当時の理事から「仏文科卒業生なのに読んでいないとは」とお叱りを受けた渡辺先生の本をようやく読めた。 岩波文庫版と迷って、初めて聞く出版社の本書を選んだが、内容は非常に読みやすかった。 解説などが一切ないのでこの出版社の編集の意図がよくわからないが、渡辺先生の書かれたもののうち、個別の作家や作品についての文学的な考察などではなく、一般向けを想定してできるだけ平易な文章で書かれたエッセイを集成したものと思われる。 理解が間違っているかもしれないが、以下のような内容であった: ・文学者や人文学的な学問に携わる者でも、政治的に無関心であることは、無責任である ・寛容は不寛容に対してもなお寛容であるべきである ・「教養」は、ばらばらの知識の豊富さではなく、それらを関連づけ、またその結果として他者の反応を予想したり思いやったりすることにつなげられなければならない。 等。 また、「新卒業生の1人への手紙」が特に心に残った。自分自身、学力的に不足していると感じて就職したが、同じように大学院に進学を諦めた卒業生への言葉と思われる章だった。先生は就職後にも「文学を棄てまいとすること」ができると説いており、それは必ずしも文学をものしたりすることを続けるという意味ではなく、もっと本質的には「機械のような秀才や、機械のような超人よりも…、誤りを正直に自覚し、迷いつつも進み、人生に苦しみ、…なおも、人生を惜しみ、これを愛し、…常に自戒できるような弱い人間たちで占められていたほうが、よい」ということなのだとおもった。 また、文学部が大学の中で占める位置付けに関する文章も、面白かった。
Posted by 



