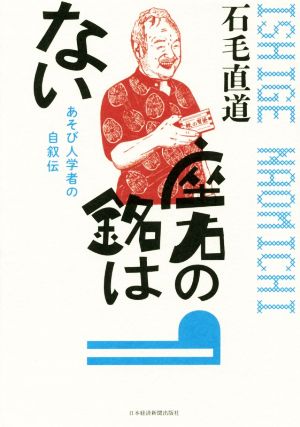
- 中古
- 書籍
- 書籍
- 1206-07-00
座右の銘はない あそび人学者の自叙伝
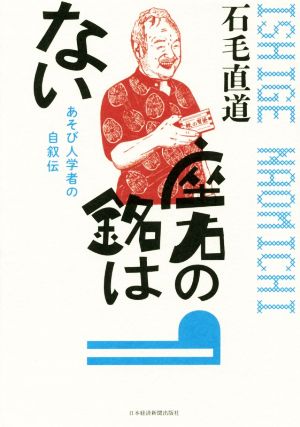
定価 ¥1,980
770円 定価より1,210円(61%)おトク
獲得ポイント7P
在庫わずか ご注文はお早めに
発送時期 1~5日以内に発送

商品詳細
| 内容紹介 | |
|---|---|
| 販売会社/発売会社 | 日本経済新聞出版社 |
| 発売年月日 | 2019/07/17 |
| JAN | 9784532176693 |
- 書籍
- 書籍
座右の銘はない
商品が入荷した店舗:0店
店頭で購入可能な商品の入荷情報となります
ご来店の際には売り切れの場合もございます
オンラインストア上の価格と店頭価格は異なります
お電話やお問い合わせフォームでの在庫確認、お客様宅への発送やお取り置き・お取り寄せは行っておりません
座右の銘はない
¥770
在庫わずか
ご注文はお早めに
商品レビュー
3
2件のお客様レビュー
2017年11月23日の日経新聞朝刊の「私の履歴書」の魚醤は稲作文化と結びついている、即ち田んぼの淡水魚の小魚から魚醤を作るとの記載を読み、吃驚して著者の「日本の食文化史」を読んでいる。 先日、本屋の平台で本書をみつけ、「お、石毛先生の本」と購入。 日経の「私の履歴書」の連載を...
2017年11月23日の日経新聞朝刊の「私の履歴書」の魚醤は稲作文化と結びついている、即ち田んぼの淡水魚の小魚から魚醤を作るとの記載を読み、吃驚して著者の「日本の食文化史」を読んでいる。 先日、本屋の平台で本書をみつけ、「お、石毛先生の本」と購入。 日経の「私の履歴書」の連載を纏め直したものと、読み始めて気付く。まあ、連載時は上の魚醤の話しかチャンと読んでないから文句はない。 中学生から考古学少年となり、「梅干しと日本人」の樋口清之の知己を得て、発掘に参加する。少年時代から物怖じしない性格で、浪人時代は「騎馬民族王朝制服説」の江上波夫の研究所の出入りする。 謦咳に触れた恩師達は、京大入学後の考古学教室や探検部に属してから更に凄いことになってゆく。 「棲み分け理論」や京大サル学を築いた今西錦司、民博初代館長となる梅棹忠雄、「KJ法」の川喜多二郎、「照葉樹林文化論」の中尾佐助、中国史の貝塚茂樹、仏文学者の桑原武夫、サル学の井谷純一郎と浅学の僕でも名を知っている人達が出てくる。 う~ん。京大、凄いなあ。 学者以外の繋がりで面白かったのは、万博プロデューサーの岡本太郎と小松左京のこと。万博のテーマ館に人類の根源的なエネルギーを現そうと、諸民族の神像と仮面を展示を計画し、著者たちが各地に収集に派遣される。 個人的なことを云うと、大阪で6年間単身生活を送っていて、万博公園内の国立民族学博物館は何度も行っていて、いつも3~4時間ドップリ楽しんでいる。万博とみんぱくの関係をが初めて知ることが出来た。 小松左京については、たぐいまれな独創力と構想力を備えて、考えたことを実現できる天才として梅棹忠雄と並び称されている。僕の手元にとりみきの「メカ豆腐の逆襲」があるんだけど、確かに小松さんの守備範囲はとんでもないなあ。 著者が考古学から民俗学に移り、更に食文化に研究対象を絞って行く辺りやみんぱくで「石毛クッキングスクール」を開いたこと等、探検や食文化調査の興味深いエピソード満載だった。 著者の本や梅棹忠雄の本を探してみようかな。
Posted by 
石毛さんというと、梅棹忠夫さんの弟子という感じがする。実際そうなのだろうが、あまりに梅棹さんが偉大なためにどうしても石毛さんの存在が霞んでしまう。その意味で、石毛さんが食文化の分野を切り開いたことはよかった。石毛さんといえば食文化、なんでも食う人というイメージができあがった。それ...
石毛さんというと、梅棹忠夫さんの弟子という感じがする。実際そうなのだろうが、あまりに梅棹さんが偉大なためにどうしても石毛さんの存在が霞んでしまう。その意味で、石毛さんが食文化の分野を切り開いたことはよかった。石毛さんといえば食文化、なんでも食う人というイメージができあがった。それでもなんでも好きこのんで食べたのではなく、その場の雰囲気で食べざるをえなかったことも多かったようだ。そもそも、石毛さんは考古学の出身で石器に関する論文を卒論に書いている。しかも、それは専門誌に二回にわたって掲載された。石毛さんはその後フィールド調査を通し、民族学へ関心が移っていく。石毛さんはフィールドが好きで、最初就職した甲南大学も数年でやめてしまう。それはそうだろう。ふつうに大学の教師をしていては外へ出ることは難しい。石毛さんは同時に管理職がきらいで、教授にもなりたくなかったそうだが、業績はあげていて、しかも、なれ寿司だったか魚醤の研究で学位までとってしまった。(この本は図書館から借りて見たことがあるが、買おうという気にはなれなかった。)そのため、梅棹さんのつぎの民博の館長にされてしまった。管理職はだめと言いつつも、石毛さんはここで民博の存在を守るために総理にまで会いに行ったりしている。石毛さんは食べることも好きだが、たいへんな飲んべえらしい。にもかかわらず80を超す長寿である。石毛さんはとにかく好きなこと、おもろいことをやり続けた。しかし、そんな石毛さんにも一つ危険なことがあった。それは生涯にわたり何度も骨折をしていることである。人間はなんど骨折しても大丈夫なのだろうか。まあ、今は石毛さんの健康長寿を祈りたい。
Posted by 



