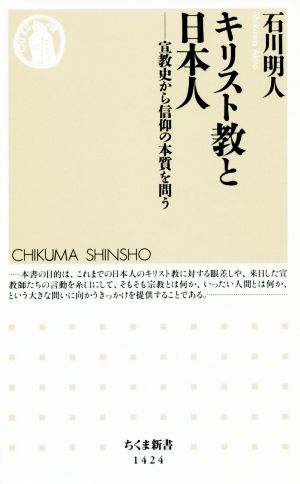
- 中古
- 書籍
- 新書
- 1226-29-02
キリスト教と日本人 宣教史から信仰の本質を問う ちくま新書
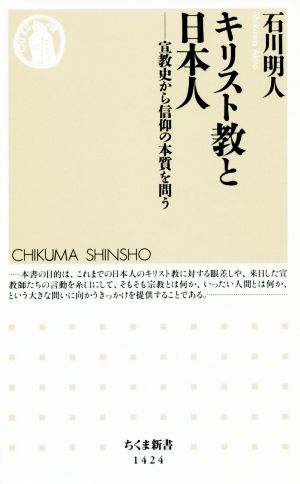
定価 ¥990
550円 定価より440円(44%)おトク
獲得ポイント5P
残り1点 ご注文はお早めに
発送時期 1~5日以内に発送

商品詳細
| 内容紹介 | |
|---|---|
| 販売会社/発売会社 | 筑摩書房 |
| 発売年月日 | 2019/07/05 |
| JAN | 9784480072344 |
- 書籍
- 新書
キリスト教と日本人
商品が入荷した店舗:0店
店頭で購入可能な商品の入荷情報となります
ご来店の際には売り切れの場合もございます
オンラインストア上の価格と店頭価格は異なります
お電話やお問い合わせフォームでの在庫確認、お客様宅への発送やお取り置き・お取り寄せは行っておりません
キリスト教と日本人
¥550
残り1点
ご注文はお早めに
商品レビュー
4
8件のお客様レビュー
めちゃくちゃためになった 何がって言うと、日本キリスト教史が分かりやすく説明されてるのはもちろん、当時活躍した宣教師だったり、信仰とはなにか?宗教とはなにか?っていうのを莫大な先行研究から考察してること キリスト教とはなにかとか日本人とどういう風に関わってきたのかを知りたいなら...
めちゃくちゃためになった 何がって言うと、日本キリスト教史が分かりやすく説明されてるのはもちろん、当時活躍した宣教師だったり、信仰とはなにか?宗教とはなにか?っていうのを莫大な先行研究から考察してること キリスト教とはなにかとか日本人とどういう風に関わってきたのかを知りたいなら最高の1冊だと思う
Posted by 
わたしはイエスがわからない。というか宗教がわからない。宗教を「信じる」気持ちがわからない。宗教を信じるひとは、死んだのに生き返ったとか、海を割ったとか、そういう話を本気で「信じて」いるのだろうか? そういう奇跡を起こした(ということになっている)人が言うことだからと、無批判に受け...
わたしはイエスがわからない。というか宗教がわからない。宗教を「信じる」気持ちがわからない。宗教を信じるひとは、死んだのに生き返ったとか、海を割ったとか、そういう話を本気で「信じて」いるのだろうか? そういう奇跡を起こした(ということになっている)人が言うことだからと、無批判に受け入れて「信じて」いるのだろうか? 不思議でしょうがない。だがそういうことを敬虔な信者に直接根掘り葉掘り聞くと怒られそうなので、本を読む。だが、こういう素朴な疑問に答えてくれる本にはまだ出会っていない。 本書は冒頭で「宗教を信じるとはどういうことなのだろうか。(中略)実は、こういった問いそれ自体が、本書の究極的なテーマである」と謳っている。しかも筆者はキリスト教徒だという。お、これは明確な答えを教えてくれるかも、と期待して読んだ。 前半は有名なフランシスコ・ザビエルも登場する、戦国時代日本への布教の歴史。教科書ではさらっと流されるが、宣教師は貿易の、ひいては武器を持ち込んで武装を強化することで藩同士の戦いに関与する橋頭堡でもあったんだな。 キリスト教は平和主義、博愛主義みたいに言われることがあるが(なんじ右の頬を打たれば左の頬を差し出せ)、キリスト教徒でも殴られてこっちもどうぞ、という人がそうそういるとは思えない。大統領がバイブルに手を置いて宣誓を行うアメリカなんか、しょっちゅう戦争している。それでも彼らがキリスト教徒だとすれば、キリスト教徒の定義にはそうとう幅があると思われる。 いよいよ後半は「信じるとはどういうことか」に触れられていくが、残念ながらここでも明確な答えは出ない。わかったのは、信仰というのは信じる/信じないのどちらかというほど簡単ではない、ということだ。マザー・テレサは書簡の中で「わたくしの信仰はなくなりました」と書いているそうだが、列聖されたほどのマザーテレサすら揺らぐ「信仰」とはどういうものなのか。いよいよわからない。ぼくは正月には近所の神社に初詣に行くし、法事があれば線香の一つも上げるわけだが、それだって至極いい加減な神道信者、仏教徒と言えるのかもしれない。 本書に、各界の有名人に宗教について聞いた本を引用している部分がある。その中で2名、高村薫と立花隆がキリスト教または宗教全体について懐疑的な考えを述べているそうだ。立花隆は「宗教を信じる人ってどこかおかしいんじゃないかと思っています(笑)」という身も蓋もないコメントを残していて、ぼくはそこまでは言わないけど、でも宗教を信じる人の気持ちがわからないのは同じだ。信じる人はどうして信じているのだろう? 信じられるのだろう? キリスト教、または宗教を懐疑的に考えているのが2名だとすれば、残りの人達は宗教を肯定的に考えているということで、読みたいのはむしろそっちだ。と、ここまで考えて気づいた。引用されているこの文章のもとの本を読めばいいんだ。 というわけで、早速「私と宗教」という本を読むことにした。
Posted by 
戦国時代のキリスト教伝来から、禁教時代を経て明治に入って再び布教に訪れた宣教師たちの様子や、彼らから見たキリスト教に対する日本人の様子、そして実際に日本内外でキリスト教に触れた人々の教えへの姿勢を通し、「信仰とは一体何か?」を探る。 キリスト教から見た日本史が解説されているほ...
戦国時代のキリスト教伝来から、禁教時代を経て明治に入って再び布教に訪れた宣教師たちの様子や、彼らから見たキリスト教に対する日本人の様子、そして実際に日本内外でキリスト教に触れた人々の教えへの姿勢を通し、「信仰とは一体何か?」を探る。 キリスト教から見た日本史が解説されているほか、一般的にキリスト教への〝信仰が篤い〟とされている人々も、神や教えに対して疑問を持つという点が興味深かった。
Posted by 



