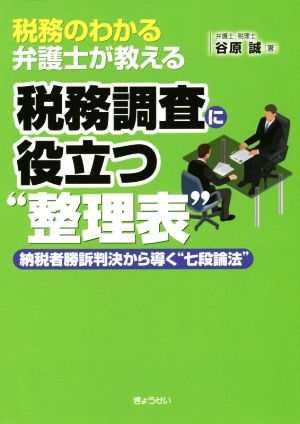
- 中古
- 店舗受取可
- 書籍
- 書籍
税務のわかる弁護士が教える税務調査に役立つ“整理表" 納税者勝訴判決から導く“七段論法"
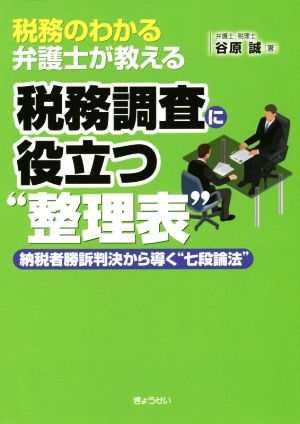
定価 ¥2,420
1,210円 定価より1,210円(50%)おトク
獲得ポイント11P
在庫わずか ご注文はお早めに
発送時期 1~5日以内に発送

店舗受取サービス対応商品
店舗受取なら1点でも送料無料!
店舗到着予定
7/2(火)~7/7(日)

商品詳細
| 内容紹介 | |
|---|---|
| 販売会社/発売会社 | ぎょうせい |
| 発売年月日 | 2019/05/19 |
| JAN | 9784324106464 |
- 書籍
- 書籍
税務のわかる弁護士が教える税務調査に役立つ“整理表"
商品が入荷した店舗:0店
店頭で購入可能な商品の入荷情報となります
ご来店の際には売り切れの場合もございます
お客様宅への発送や電話でのお取り置き・お取り寄せは行っておりません
税務のわかる弁護士が教える税務調査に役立つ“整理表"
¥1,210
在庫わずか
ご注文はお早めに
商品レビュー
2
1件のお客様レビュー
本書では、税務調査において課税庁と納税者(税理士)との間で法律解釈・事実認定・法適用などで見解の相違が生じた場合に、その見解の相違を解消すべく有効な交渉方法が解説されている。税務調査で課税庁との間で見解の相違が生じた場合、えてして口頭での議論に終始しがちであるが、双方の主張を整理...
本書では、税務調査において課税庁と納税者(税理士)との間で法律解釈・事実認定・法適用などで見解の相違が生じた場合に、その見解の相違を解消すべく有効な交渉方法が解説されている。税務調査で課税庁との間で見解の相違が生じた場合、えてして口頭での議論に終始しがちであるが、双方の主張を整理した「整理表」を作成した上で、「納税者主張整理表」及び証拠書類を作成し、提出することは非常に有効な交渉方法であると提案している。多数の著名な裁判例を題材にしてこの「納税者主張整理表」の作成例を示しているあたり大変な意欲作と言える。税務調査の対応方法について検討中の税理士には一読の価値がある書籍である。 P4 2 ある税務調査の事例(その2) Aさんは、納税者X社の社内において、顧客データの入力業務を行っていました。契約書は締結していませんが、納税者は、報酬を外注費として支払い、Aさんも事業所得として確定申告をしていました。税務調査において、調査官が、この外注費について指摘しました。 調査官 「Aさんへの支払が外注費になっていますが、契約書を見せてください」 納税者 「契約書は締結していません」 調査官 「第三者に外注するのに、なぜ契約書を締結しないのですか?」 納税者 「支払条件については、メールが残っています」 調査官 「Aさんへの報酬は、どのように決めていますか?」 納税者 「タイムカードで業務時間を把握し、時間単位で支払っています」 調査官 「タイムカードで時間管理をしているのですか?それでは外注とは言えませんから、給与ですね」 納税者 「でも、Aさんは、事業所得として確定申告をしていますよ」 調査官 「それが間違っているのです。契約書もなく、時間管理されているのですから、外注ではありません」 納税者 「作業をするパソコンは、Aさんが持ち込んでいます。また、社会保険にも加入していませんし、来る時間や帰る時間は自由です。他の従業員とは明らかに違います」 調査官 「明らかに違うなら、なぜ、その条件を契約書にしないのですか?また、時間が自由ならタイムカードで管理する必要はないでしょう。この点は、どう説明しますか?」 納税者 「契約書がなくても、問題が生じたことはありません。タイムカードを打刻するのは、いつ会社に来て、何時間作業をしていただいたか把握するためです。では、今後はタイムカードは廃止します。それなら、外注費でいいですか?」 調査官 「今後については、結構です。しかし、これまでについては、タイムカードで時間管理していた以上、外注費とは認められません。いいですね」 税務調査で、個人に支払う外注費が外注費か給与かで争われることは多いと思われます。ここでも、調査官は、Aさんに支払っている外注費が給与ではないか、と質問を重ねてきて、最後は給与であると決めつけてきました。 しかし、このまま更正に至ると、誤った更正になる可能性があります。なぜなら、本件税務調査におけるやり取りは、あたかも外注費であることを納税者が立証しなければ給与として認定されることを前提に進められているためです。後で詳しく説明しますが、課税要件事実に該当する事実については、国に立証責任があり、国が立証できない場合には、更正は違法となり、取消されることになります。 しかし、質問検査は、調査官が質問し、納税者が回答する、という会話構造により、立証責任が逆転し、あたかも納税者が課税要件事実に該当しないことを立証しなければならないような質疑になってしまいがちです。 したがって、納税者側としては、常に立証責任を意識し、調査官にその旨指摘し、両者の共通認識として、立証責任が国にあることを前提として税務調査を進めていくことが大切です。
Posted by 

