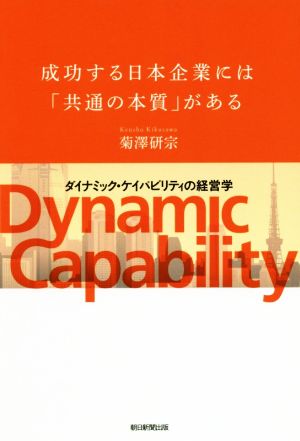
- 中古
- 書籍
- 書籍
- 1209-02-02
成功する日本企業には「共通の本質」がある ダイナミック・ケイパビリティの経営学
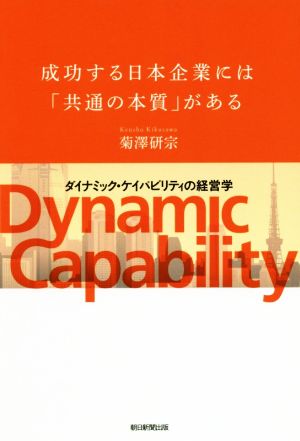
定価 ¥1,760
1,375円 定価より385円(21%)おトク
獲得ポイント12P
残り1点 ご注文はお早めに
発送時期 1~5日以内に発送

商品詳細
| 内容紹介 | |
|---|---|
| 販売会社/発売会社 | 朝日新聞出版 |
| 発売年月日 | 2019/03/27 |
| JAN | 9784023317703 |
- 書籍
- 書籍
成功する日本企業には「共通の本質」がある
商品が入荷した店舗:0店
店頭で購入可能な商品の入荷情報となります
ご来店の際には売り切れの場合もございます
オンラインストア上の価格と店頭価格は異なります
お電話やお問い合わせフォームでの在庫確認、お客様宅への発送やお取り置き・お取り寄せは行っておりません
成功する日本企業には「共通の本質」がある
¥1,375
残り1点
ご注文はお早めに
商品レビュー
4
11件のお客様レビュー
ダイナミック・ケイパビリティ、初耳だが非常に分かりやすく解説されていた。実例を挙げつつ、理論の背景も含めて説明されていて腑に落ちる。 米国流の株主主権論は放棄せよ、との提言だが、「会社は株主のもの」と中学の社会でも習った記憶があり、バブル経済崩壊後は日本政府がかなり導入に力を入れ...
ダイナミック・ケイパビリティ、初耳だが非常に分かりやすく解説されていた。実例を挙げつつ、理論の背景も含めて説明されていて腑に落ちる。 米国流の株主主権論は放棄せよ、との提言だが、「会社は株主のもの」と中学の社会でも習った記憶があり、バブル経済崩壊後は日本政府がかなり導入に力を入れていたと痛感した。大学の講義でも株主主権論が当たり前みたいになっている風潮があったが、MBAでも未だにそうなっているとのこと。当時中学生ながらに違和感を感じていたが、本書でモヤモヤがスッキリした。
Posted by 
日本企業の成功の秘訣にダイナミック・ケイパビリティがあるが、日本ではなかなか浸透していない。変化対応的な自己変革能力のこと。日本人は真面目というか固いというか、集団から逸脱し難い同調圧力的傾向があり、イノベーションのジレンマに陥りやすい。だからこそ、意識的にもこの概念を実践してい...
日本企業の成功の秘訣にダイナミック・ケイパビリティがあるが、日本ではなかなか浸透していない。変化対応的な自己変革能力のこと。日本人は真面目というか固いというか、集団から逸脱し難い同調圧力的傾向があり、イノベーションのジレンマに陥りやすい。だからこそ、意識的にもこの概念を実践していく必要があるというのが著者の主張だ。 事例を挙げながら、分かりやすく解説される。学びが多い。コダックはデジタルカメラの技術を開発していたが、デジタルカメラに移行することによって利益が減少するという状態にあった。富士フイルムも同様の状況にあったが、二社の明暗を分けたものは何か。他にも、任天堂とソニーの攻防について。 なるほどなと思ったのは、日本企業の変遷。1980年代の日本企業の強さの源泉は、ダイナミック・ケイパビリティ。しかしバブル経済崩壊後、日本企業をめぐって多くの不祥事や不正が明らかになり、その経営手法が厳しく批判された。その後日本企業は財務構造的にも弱体化したのだという。 特に最近の日本の製造業のデータの改ざんと言う不祥事。これはアメリカ流の株主主権論に基づく市場ベースのマネジメントに対して、日本の伝統的な組織ベースの生産システムとのミスマッチが限界に達していることの証左。 株主利益を重視するアメリカ流の経営パラダイムへとシフトせざるをえなくなった。対して、日本は人間組織的な生産システム。この2つが宥和的に結びつき、生産現場が合理的に不正を生み出さざるを得ないような状況に追い込まれているように思える。神戸製鋼や東洋ゴムは、経営陣たちの厳しい要求に対して現場が関係各所に迷惑をかけないように忖度したのだろう。これは人間関係上の取引コストが非常に高いためであって、企業の現場では合理的な判断だったと考えられる。 このような不正行為は確かに上からの命令に従った行為ではない。首謀者が不明な極めて日本的な不正。職務転換や配置転換で、新任者がこの伝統的な不正を認識していたにもかかわらず是正できなかったのも、それらを是正するためにいろんな人たちと交渉し説得する取引コストがあまりに大きかったため。彼らにとっては合理的に維持してきた結果。構造的、不条理に陥っている。 これらの理論は著者の『組織の不条理』でも述べられれため合わせて読むとより理解しやすい。取引コストの概念である。 取引コストを下げるためには、飲み会、社内イベント、上層部が現場に足を運ぶことが重要。しかし根本的な解決にはならない。株主主権論とのミスマッチを解消する必要がある。アメリカのような、ダイバーシティーの国では有効。共通のパラダイムの必要性があり同一化するために最もわかりやすい統一基準はドルであり利益だからだ。日本にはミスマッチである。 長くなるのでこの程度にするが、日本企業に必要な概念を、著者の研究の解説によって示唆する良著。少なくとも私には有益だった。
Posted by 
組織の不条理を読んだ後にこちらも読ませていただきました 人間の限定合理性を前提に 批判を受け入れる組織であること 垂直的な方向の大切さを感じた
Posted by 



