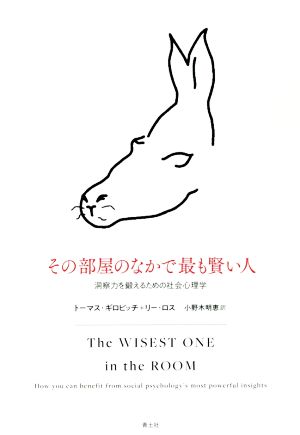
- 中古
- 書籍
- 書籍
- 1206-06-03
その部屋のなかで最も賢い人 洞察力を鍛えるための社会心理学
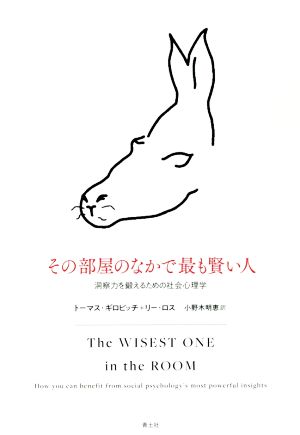
定価 ¥2,420
385円 定価より2,035円(84%)おトク
獲得ポイント3P
在庫わずか ご注文はお早めに
発送時期 1~5日以内に発送

商品詳細
| 内容紹介 | |
|---|---|
| 販売会社/発売会社 | 青土社 |
| 発売年月日 | 2018/12/22 |
| JAN | 9784791771325 |
- 書籍
- 書籍
その部屋のなかで最も賢い人
商品が入荷した店舗:0店
店頭で購入可能な商品の入荷情報となります
ご来店の際には売り切れの場合もございます
オンラインストア上の価格と店頭価格は異なります
お電話やお問い合わせフォームでの在庫確認、お客様宅への発送やお取り置き・お取り寄せは行っておりません
その部屋のなかで最も賢い人
¥385
在庫わずか
ご注文はお早めに
商品レビュー
4
13件のお客様レビュー
「その部屋のなかで最も賢い人」って何だろう。 訳者があとがきで書いているのは「賢い人」という原文の意味は、wisdom(賢さ、賢明さ、知恵)であると。知識(knowledge)、洞察(insight)、判断(judgment)を含む概念であり、いわゆる知能や頭脳の明断さではなく、...
「その部屋のなかで最も賢い人」って何だろう。 訳者があとがきで書いているのは「賢い人」という原文の意味は、wisdom(賢さ、賢明さ、知恵)であると。知識(knowledge)、洞察(insight)、判断(judgment)を含む概念であり、いわゆる知能や頭脳の明断さではなく、人に対する洞察力があり、日常生活や人生の重要な局面において賢明な判断をできるという能力を指すのだという。 賢い人の概念をデフォルメ化(幼稚化)すれば、凄いやつと言い換えられるので、この点は<凄いやつと凄くないやつ>という対立軸で整理ができるとして、私はどちらかというと「その部屋の中で」という、前提条件が気になった。それって、井の中の蛙みたいにも読めるし、裸の大将にも見える。偏差値の低い学校でのできるヤツ、と偏差値の高い学校でのできないヤツは、学力はそれほど変わるわけではないが、自己効力感が異なり、前者は若干傲慢な所がある。こういうのを「井の中の蛙」というのだろうが、「その部屋のなかで」という表現にも何かしらそうした皮肉を感じる。 本書で述べられるのは、バイアスを取り払ったところにある〝思考の罠”にとらわれない考え方だ。行動経済学、心理学的なアプローチで、人間心理の面白さを紹介していく。 例えば、学生たちに提示されたゲームの名前。学生の半分には、「コミュニティ・ゲーム」と伝え、残り半分には「ウォールストリート・ゲーム」と伝えたところ、ルールは同じでも、コミュニティ・ゲームと伝えた場合に学生同士が協力する頻度がおよそ二倍になったらしい。人は言葉の印象に操作されやすい、という例だ。 他にも、ホラー映画を見た後と ロマンチックコメディの映画の後で、夜道を歩く際の気分が変わる。当たり前にも聞こえるが。心理学者では「プライミング」効果と呼ぶらしいが、人間は、その前に見た映画にも暫く左右される。カンフー映画を見て、アチョーと強くなった気持ちになったり。 で、こうした人間の原理を知ることで、極力、シラフでものを考えられる人間が賢いのだと。つまり「その部屋」とは、こうした自らに影響する環境因子の囲いという気がした。そして、その中で賢いというのは、wisdomよりも、self-righteousness(独善)なのかもしれないな、と。
Posted by 
最も「賢明」な振る舞いのできる人になるにはどうすればよいか? 賢さ、賢明さはいわゆる単なる知識やIQといった知性とは異なる。 IQが飛び切り高い天才でもその人間性ゆえに集団の中で孤立してしまう事が起こり得るが、賢明な人物は集団の中でいかに振舞うべきかを心得ており、単に権威により人...
最も「賢明」な振る舞いのできる人になるにはどうすればよいか? 賢さ、賢明さはいわゆる単なる知識やIQといった知性とは異なる。 IQが飛び切り高い天才でもその人間性ゆえに集団の中で孤立してしまう事が起こり得るが、賢明な人物は集団の中でいかに振舞うべきかを心得ており、単に権威により人を動かすのでなく、人の心の動かし方を知っている。 そのようなEQに近い側の知的行動について、分類、分析している本。 問うている事は有意義だが、ちょっと過剰にボリュームが多くて、読むのが大変だったし、周辺情報が多すぎて本筋を見失うことが度々あった。 また、周辺情報もアメリカの話ばかりで、日本人の私にはピンと来るものが少なかった。(著者がアメリカ人なので当然ではあるが) 都度、まとめなどがあればよかったのだが。。 本書で繰り返し言われていたことは、 私たちの見方や考え方は無意識のうちに所属や文化に大きく左右されている。 だから、そのようなバイアスに左右されてしまうものだという前提から始めるべきだというもの。 本論は読むのは大変だったが、時々差し込まれる偉人の逸話は面白かった。
Posted by 
その部屋の中で最も賢い人The Wisest one in the Room というタイトルに魅かれて手に取ったものの、大著のわりによく知られたエピソードの引用も多いし訳文もちょっと厳しい・・・ P11 知能とは、利用できる情報を取り入れて、それを効果的に処理するー論理的に考え...
その部屋の中で最も賢い人The Wisest one in the Room というタイトルに魅かれて手に取ったものの、大著のわりによく知られたエピソードの引用も多いし訳文もちょっと厳しい・・・ P11 知能とは、利用できる情報を取り入れて、それを効果的に処理するー論理的に考えて確かな結論を導く―というものである。これはまさに賢さの一要素だ。しかし賢い人は、これだけにはとどまらない。手に入る情報を利用する以上のことをするのだ。賢明さには、手に入る情報が、目の前の問題を解くには不十分であるということを見抜く力も関係してくる。今は正しいことであっても、その先には全く違って見えるかもしれないということを理解する力も含まれるのだ。 P41 自分自身の見解と、自分とは意見の異なる人の見解との隔たりが最も著しい時に、素朴な現実主義の及ぼす影響が最大になる。 P50 部屋の中で最も賢い人は、とりわけ争いが頂点に達したときに、こうしたいら立ちの矛先を向けられることになる。 P150 嫌なことをするためにもらう金額が低いほど(故に感じる不協和が大きくなる)結局のところそのことは、本当はさほど嫌なことではないと結論付ける傾向が高まるというものだ。 P227 体験は持続するだけではない。最高の要素を飾りたて、最悪の要素を軽視するにつれ、時の経過とともに良くなっていくことが多いのだ。【中略】(最悪だったキャンプの思い出が)時とともに、そして語ったり回想したりする間に「最悪のキャンプ」ではなく「とても愉快な最悪のキャンプ」になっていく。 P338 マンデラのとった大小さまざまな行動は、アフリカーナ人たちに、彼らが足を踏み入れようとしている新しい世界がどのようなものであるかについて、安心できる見通しを与えた。競技場に行ったりテレビで試合を観たり、翌週に職場で試合について話をしたりと、普段してきたように振る舞える環境を作ることによって、マンデラは、白人の南アフリカ人たちに、耐えられる未来、さらには個人の生活の質という点で(国がどのように運営されるかという点ではなく)かなり普通の未来という見通しを提示したのだ。
Posted by 



