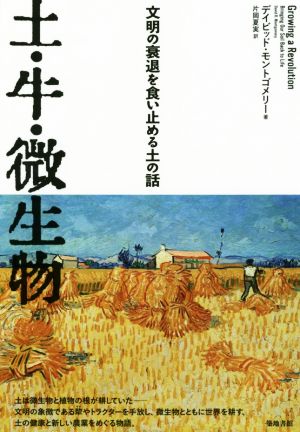
- 中古
- 書籍
- 書籍
- 1212-01-06
土・牛・微生物 文明の衰退を食い止める土の話
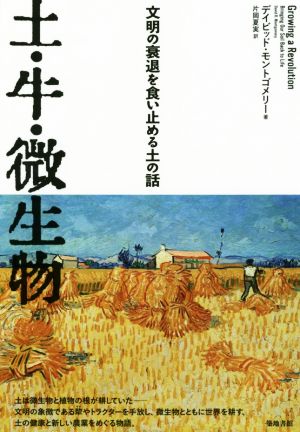
定価 ¥2,970
2,475円 定価より495円(16%)おトク
獲得ポイント22P
在庫なし
発送時期 1~5日以内に発送

商品詳細
| 内容紹介 | |
|---|---|
| 販売会社/発売会社 | 築地書館 |
| 発売年月日 | 2018/08/31 |
| JAN | 9784806715672 |
- 書籍
- 書籍
土・牛・微生物
商品が入荷した店舗:0店
店頭で購入可能な商品の入荷情報となります
ご来店の際には売り切れの場合もございます
オンラインストア上の価格と店頭価格は異なります
お電話やお問い合わせフォームでの在庫確認、お客様宅への発送やお取り置き・お取り寄せは行っておりません
土・牛・微生物
¥2,475
在庫なし
商品レビュー
4.8
5件のお客様レビュー
結論からいえば、今年から自分の耕作地はすべて不耕起でいってみよう思っている。移住から7年、現在の居住地に定着してから4年が過ぎたが、これまでの経験から、著者のいう三原則①土壌の撹乱を最小限にする、②被覆作物(あるいは”雑草”)で土壌を常に覆う、③多様な輪作の導入すれば、十分に農作...
結論からいえば、今年から自分の耕作地はすべて不耕起でいってみよう思っている。移住から7年、現在の居住地に定着してから4年が過ぎたが、これまでの経験から、著者のいう三原則①土壌の撹乱を最小限にする、②被覆作物(あるいは”雑草”)で土壌を常に覆う、③多様な輪作の導入すれば、十分に農作物の収穫が可能な生物的肥沃さ(有機物の分解/代謝能力の高さ)が備わる潜在能力が、この中山間地の大地にはある、と今では確信している。 いずれにせよ世界の炭素排出量の15%を占めるといわれる農業において、地域の有機資源を最大限利用して化成肥料に代替し、耕起を最小限にして化石燃料の消費を抑える低投入型の営農スタイルの確立は必須である(いわゆる「環境保全型農業」ともいうか)。 ただし、大事なのは「不耕起でなければならない」のではなく「不耕起でも同様の収穫が見込める」ということを証明してみせること。もちろん痩せた土地であっても耕起によって物理性を改善し、無機肥料の施用によって十分な収穫量を上げることはできるだろう。そこで、生物学的な肥沃さを持った土地であれば、低投入型で同様の収量を見込めるとしたら? ホップ栽培に関していえば、多年草であるということもあって、基本的には不耕起、被覆植物によるマルチ+堆肥投入のみで栽培ができている。適当な排水ができれば、有機物の代謝のサイクルは十分に回すことができる感じている。 ユストゥス・フォン・リービッヒからアルバート・ハワード、そして福岡正信と山下一穂、さらにゲイブ・ブラウン「土を育てる(2022, NHK出版)」まで。先人たちの経験値と現場観察から導かれた知見が、見事に重なって見えてきている。 あとの成否は自分の観察眼と管理技術を磨くこと。失敗しても、やめるまでは失敗ではない。持続可能な農村コミュニティのために。今年もまた、農繁期を前に一層わくわくしてきた。良い本でした。
Posted by 
ブログで紹介 https://www.salon-shiroineko.com/entry/2018/11/23/201334
Posted by 
環境保全型農業という農法を未だ知らない全ての農業従事者並びに、農業大学校、農学部で是非読んでほしい、読まなければならない一冊。 もちろん、農家だけでなく、そういうものが環境への影響を減らすのだということを知るためにも消費者の方には飛ばし読みでもいいので目を通して頂きたいと感じた...
環境保全型農業という農法を未だ知らない全ての農業従事者並びに、農業大学校、農学部で是非読んでほしい、読まなければならない一冊。 もちろん、農家だけでなく、そういうものが環境への影響を減らすのだということを知るためにも消費者の方には飛ばし読みでもいいので目を通して頂きたいと感じた。 この本を通して、農業は頭で考えて実行できる部分もあるけれど、やはり愚者の職業で、経験しながら学びながら、行わなければならないものの一つであることを再確認した。
Posted by 



