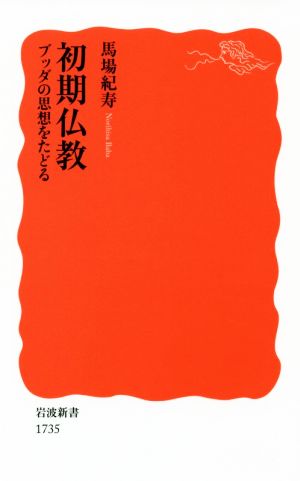
- 中古
- 書籍
- 新書
- 1226-29-01
初期仏教 ブッダの思想をたどる 岩波新書
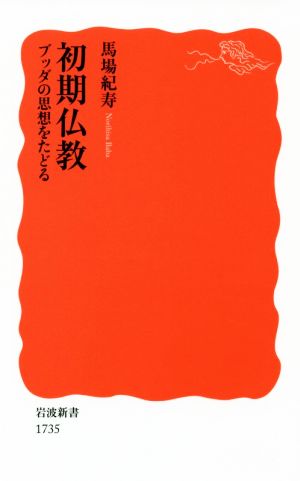
定価 ¥1,056
605円 定価より451円(42%)おトク
獲得ポイント5P
在庫なし
発送時期 1~5日以内に発送

商品詳細
| 内容紹介 | |
|---|---|
| 販売会社/発売会社 | 岩波書店 |
| 発売年月日 | 2018/08/22 |
| JAN | 9784004317357 |
- 書籍
- 新書
初期仏教 ブッダの思想をたどる
商品が入荷した店舗:0店
店頭で購入可能な商品の入荷情報となります
ご来店の際には売り切れの場合もございます
オンラインストア上の価格と店頭価格は異なります
お電話やお問い合わせフォームでの在庫確認、お客様宅への発送やお取り置き・お取り寄せは行っておりません
初期仏教 ブッダの思想をたどる
¥605
在庫なし
商品レビュー
4
17件のお客様レビュー
仏教の本質理解: ブッダの教えの核心を理解し、初期仏教の思想を正確に把握することの重要性。 輪廻と業の理解: 「輪廻」と「業」の概念が仏教の教えにおいてどれほど重要であるかを強調。 経典の解釈: 上座部仏教の経典が持つ多様性と、それぞれの経典が伝えるメッセージの解釈の重要性。...
仏教の本質理解: ブッダの教えの核心を理解し、初期仏教の思想を正確に把握することの重要性。 輪廻と業の理解: 「輪廻」と「業」の概念が仏教の教えにおいてどれほど重要であるかを強調。 経典の解釈: 上座部仏教の経典が持つ多様性と、それぞれの経典が伝えるメッセージの解釈の重要性。 歴史的背景の考慮: ブッダの教えが生まれた歴史的、社会的背景を考慮することで、教えの理解が深まること。 実践の重要性: 理論だけでなく、実践を通じて仏教の教えを生活に取り入れることの重要性。 現代への適用: 初期仏教の教えが現代社会においても有用であることを示し、現代人にとっての意義を考察。 倫理的視点: 仏教の教えが持つ倫理的な側面を強調し、個人と社会の調和を目指すことの重要性。 個人の内面的な成長や社会的な調和を促進するための実践的な指針
Posted by 
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
この本を読んで私が一番印象に残っているのは中村元先生の説が最新の研究においては否定されているという点でした。 もちろん、中村元先生の説く仏教が全て誤っていたというわけでは当然ないのですが、最新の研究によるならば、かつてよりも随分と違った仏教が私達の前に開かれているということになるでしょう。中村元先生の説といえども無批判に受け取ることはできないということにハッとする思いになりました。と同時に学問はこうして進んでいくのだとしみじみする気持ちにもなりました。 他にも、この本では最新の研究をふまえて、当時のインド社会とブッダの関係を見ていくことができます。後半ではブッダの思想そのものも解説されますので、初期仏教の全体像を掴むためにもおすすめです。
Posted by 
近年の研究を踏まえた初期仏教についての解説 古代インドやスリランカの文献学の研究が進んでいるということ非常に驚く。 それまでの前提が変わることになるが、前の前提のまま大きなものを構築していった人達には読み辛いかもしれない。
Posted by 



