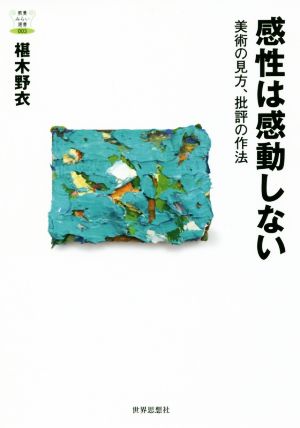
- 中古
- 書籍
- 書籍
- 1219-06-00
感性は感動しない 美術の見方、批評の作法 教養みらい選書003
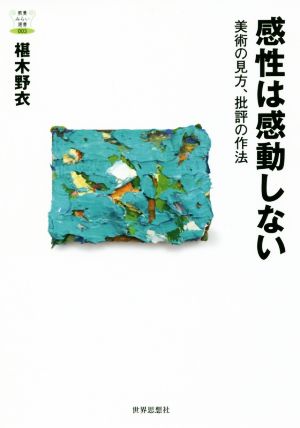
定価 ¥1,870
1,100円 定価より770円(41%)おトク
獲得ポイント10P
残り1点 ご注文はお早めに
発送時期 1~5日以内に発送

商品詳細
| 内容紹介 | |
|---|---|
| 販売会社/発売会社 | 世界思想社 |
| 発売年月日 | 2018/07/01 |
| JAN | 9784790717133 |
- 書籍
- 書籍
感性は感動しない
商品が入荷した店舗:0店
店頭で購入可能な商品の入荷情報となります
ご来店の際には売り切れの場合もございます
オンラインストア上の価格と店頭価格は異なります
お電話やお問い合わせフォームでの在庫確認、お客様宅への発送やお取り置き・お取り寄せは行っておりません
感性は感動しない
¥1,100
残り1点
ご注文はお早めに
商品レビュー
3.6
13件のお客様レビュー
美術の見方なのかと思ったら、色々徒然なるままに書き綴った一冊。 でもタイトルの「感性は感動しない」という言葉の意味が腑に落ちた。
Posted by 
大学図書館で借りて読んだ 内容は忘れたけど、読みたいと思った理由は、自分が感性を大切にするタイプだけど、タイトルは「感性は感動しない」…、するもんじゃん?って思ったから。 ただ、展示会で感性をあまり使わなくなってしまったような気がする、キャプションとかの「情報」だけを頼りに作品を...
大学図書館で借りて読んだ 内容は忘れたけど、読みたいと思った理由は、自分が感性を大切にするタイプだけど、タイトルは「感性は感動しない」…、するもんじゃん?って思ったから。 ただ、展示会で感性をあまり使わなくなってしまったような気がする、キャプションとかの「情報」だけを頼りに作品を見るようになってきている。 例えば、絵を見ながら、〇〇技法とか〇〇主義があるのかな〜とか予想してからキャプションで答え合わせしたり…(最近これハマってる) 芸術の楽しみ方迷走中 そこが楽しいんですが。 再読希望
Posted by 
美術批評家による随筆集。美術や音楽に関することから日常のくだらないことまで色々書いているけれど、特に印象に残ったのは次の2つ。 1つ目は、冒頭の「感性は感動しない」で書かれている、美術作品を「まとまり」として見るということ。絵や彫刻を見るとき、作品になにか始まりや終わりがあるん...
美術批評家による随筆集。美術や音楽に関することから日常のくだらないことまで色々書いているけれど、特に印象に残ったのは次の2つ。 1つ目は、冒頭の「感性は感動しない」で書かれている、美術作品を「まとまり」として見るということ。絵や彫刻を見るとき、作品になにか始まりや終わりがあるんじゃなくて、目の前には当の作品という「かたまり」そのものだけがあって、それを総体として捉えるべきだとしている。そのときに感じるのはどんなくだらないことでもよいとのこと。作者がどういう背景で描いたものだとか、どういう技法を使っただとかは二の次であって、自分のそれまでの経験やそのときの感情(というこれらの総体もかたまり)が作品というかたまりをどう処理するかを感じよう、ということらしい。ただ、批評するときというのはこのかたまりとの出会いを言葉にする必要があるので、かたまりについて感じたことをじっくり醸成していく過程が必要だという。鑑賞する先にはその感動に集中し、アウトプットまでの間にそれらの感動を噛み砕け、という風にも受け取ることができる考え方で、面白いなと感じた。 2つ目は、音楽と美術の違いについて。上で書いたように、美術作品というのはモノとして存在するのであって、それは鑑賞者がいようがいまいが関係ない(だれかが作り終えた段階で既にモノになっている)。でも、音楽というのは「再生」されて初めて作品になるという。しかも、その再生のされ方は何でも良くて、プレイヤーで再生するとか、頭の中にメロディがこびりつくとかでも良く、鑑賞者が存在していて初めて成り立つようなアートであるという点で、美術との違いがあるということを強調している。 さらに、音楽そのものが「再生されたがっている」(そして音楽の中毒性というのもこの性質に根ざしている)という若干オカルトぽいことまで言っており、(音楽にそのような主体性があるかまでは確かめようがないけれど)言わんとしたいことはとてもわかる。とすると、本当のヒット曲というのは、ヒットチャートやYouTubeでの再生回数だけじゃ測れない気もする。仮に、曲がヒットする、ということが、如何に人をその曲の中毒症状に陥らせたかと同価とするのなら、もっと日常のどうでもいい場面で口ずさんでる意外な曲が、真のヒット曲の座を手に入れるのかもしれない。
Posted by 



