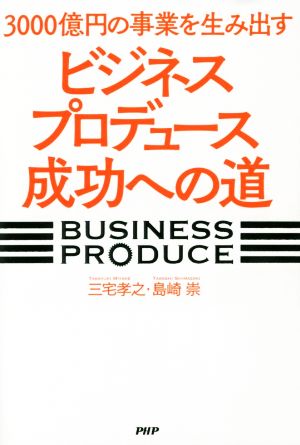
- 中古
- 店舗受取可
- 書籍
- 書籍
- 1209-02-02
3000億円の事業を生み出す「ビジネスプロデュース」成功への道
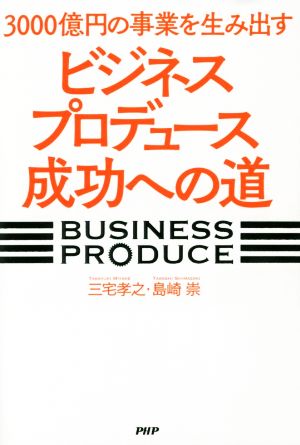
定価 ¥1,980
1,155円 定価より825円(41%)おトク
獲得ポイント10P
在庫あり
発送時期 1~5日以内に発送

店舗受取サービス対応商品【送料無料】
店舗受取なら1点でも送料無料!
店着予定:1/22(木)~1/27(火)
店舗到着予定:1/22(木)~1/27(火)
店舗受取目安:1/22(木)~1/27(火)
店舗到着予定
1/22(木)~1/27

店舗受取サービス対応商品
店舗受取なら1点でも送料無料!
店舗到着予定
1/22(木)~1/27(火)

商品詳細
| 内容紹介 | |
|---|---|
| 販売会社/発売会社 | PHP研究所 |
| 発売年月日 | 2017/05/13 |
| JAN | 9784569836065 |


店舗受取サービス
対応商品
店舗受取なら1点でも送料無料!
さらにお買い物で使えるポイントがたまる
店舗到着予定
1/22(木)~1/27(火)
- 書籍
- 書籍
3000億円の事業を生み出す「ビジネスプロデュース」成功への道
商品が入荷した店舗:0店
店頭で購入可能な商品の入荷情報となります
ご来店の際には売り切れの場合もございます
オンラインストア上の価格と店頭価格は異なります
お電話やお問い合わせフォームでの在庫確認、お客様宅への発送やお取り置き・お取り寄せは行っておりません
3000億円の事業を生み出す「ビジネスプロデュース」成功への道
¥1,155
在庫あり
商品レビュー
4
8件のお客様レビュー
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
産業創造のビジネスプロデュース本の第二弾。 事業構想策定とブックと回収エンジン設計にフォーカスした本とのこと。 メモ ・大企業で事業創造がうまくいかない理由 圧倒的な経験不足 関係者全員の本気度不足 劇的な変化を理解できていないこと ・かつての事業創造は成長市場への参入が主だった。 現在はどこも成熟化し、産業が交わったところにできる新たな産業が事業創造の対象となる。 ・ビジネスにはフックと回収エンジンが本来セット。 自動車の場合は国が道路を準備してくれたからこそ、回収エンジンのみで成り立った。新しいビジネスではフックも自分達でつくっていく必要があるのではないか。 ・フックと回収エンジンでは基本的には回収エンジンから考えるべき ・強みや差別性はフックに活用した方がパワーを発揮する ・回収エンジンのスクリーニング基準 収益性の高い事業か。人工ビジネスより固定費ビジネスが向いている。鉄道・広告、、、 大きくなりうる要素があるか。恒常性や普遍性の高さ フックとつなぎこめるか。顧客を回収エンジンに自然と流せるか ・構想の定義 どの社会課題をきりとって解決するのかが明確な取り組みになっていること その解決による社会的なインパクトが市場規模として概算されていること 各プレイヤーのビジネスモデルがある程度の相互関係を持ちながら全体としての整合性を満たした形で表現されていること ・筋の良い妄想を生み出すたむに必要な能力 物事を人よりも深く掘り込んで考えられること 多様な客観的視点を高い視座で取捨選択して取り組むことができること ・深く掘り下げるポイントは知識の絶対量 ・多様な客観的視点をもつコツ 別人格になりきってみる。 幽体離脱 視座が高くて鋭い人に議論を手伝ってもらう ・
Posted by 
ビジネスを立ち上げ利益を出すまでの過程が、具体例とともに事細かに記載されていた。 ビジネスの成功部分だけではなく、どんな場面でプロジェクトが立ち行かなくなるのか、頓挫してしまうのかなど、実際の仕事で見られる失敗事例も紹介していた ビジネスデベロップメントという言葉は抽象的なイメ...
ビジネスを立ち上げ利益を出すまでの過程が、具体例とともに事細かに記載されていた。 ビジネスの成功部分だけではなく、どんな場面でプロジェクトが立ち行かなくなるのか、頓挫してしまうのかなど、実際の仕事で見られる失敗事例も紹介していた ビジネスデベロップメントという言葉は抽象的なイメージしか持っていなかったが、現代のグローバルから見た日本の産業衰退において必須の役割であり、今後このような人材になる必要があると考えさせられた
Posted by 
ビジネス書の場合、前作の続編と言うと普通は「半分くらい前作の話」なのだけど、本書はそんなことはない。 前半に前作のダイジェストが掲載されているが、せいぜい10%くらいか。 後はほとんど新規で追加した考え方だ。 前作の発行が2015年。本作は2017年。 わずかに2年間の違いではあ...
ビジネス書の場合、前作の続編と言うと普通は「半分くらい前作の話」なのだけど、本書はそんなことはない。 前半に前作のダイジェストが掲載されているが、せいぜい10%くらいか。 後はほとんど新規で追加した考え方だ。 前作の発行が2015年。本作は2017年。 わずかに2年間の違いではあるのだが、この2年間で社会の流れが大きく変わったのを感じたのだろう。 前作ではまだそこまで主流でなかった「サービス提供ビジネス」。 これを本作では全面的に持ってきている。 2017年という発行年代を考えると著者の目線がきちんと未来を見据えているのを感じる。 今読んでも十分に通用するし、自分に置き換えて会社を見てみても、かつての古いビジネスモデルからいまだに脱却できずに苦しんでいる。 デジタルトランスフォーム、コーポレートトランスフォーム、UIUXなんて言われ始めたのはまさに2017年過ぎからじゃないだろうか。 本書ではこれら単語は出て来ないが、実際にストーリーの中には上手に組み込まれている。 新規事業と言いながら、どうやって会社自体を変革するのか。 その過程が架空のストーリーの中でありありと描かれている。 架空と言いながらも、実際に著者の体験談なのだろうから、半分以上本当の話なのではないだろうか。 それぐらいこのフィクションストーリーにはリアリティがあり、説得力もあった。 アルファGoが囲碁世界一を破ったのが2016年くらいか。 Netflix・Amazon Prime Videoの日本上陸が2016年。 つまりAIという言葉と、サブスクというビジネスモデルが一般化しだしたのが2016年頃ということなのだろう。 今までの製造販売モデルを行っている会社は、どうやってサービス提供のサブスクモデルに切り替えていくのか。 しかも単純なビジネスモデルの変化なのではなく、ポイントがデジタル化なのだ。 これには当然前述のAI活用も含まれる。 つまりデータ収集、解析がキモの部分なのだ。 このデジタル変革は古い考え方の会社ほど多量の血を流すこととなる。 しかも、これらは今までに社内全く存在しない考え方なので、言葉で説明するだけではその内容が非常に分かりづらい。 元々この分野を勉強しているならまだしも、全く不勉強だった人にとっては、サービス提供ビジネスという方向に足を踏み出す理由が分からないだろう。 本書でも新規事業メンバーが集まって最初話し合いをするが、すぐに煮詰まる場面がある。 その後にとにかくメンバーで読書をするのが印象的だ。 一人につき数十冊。関連書籍を読み漁って知識をインプットする。 そうなのだ。いきなりアウトプットを求めても無理なのだ。 まずは大量のインプットをしてからでないと、アウトプットの質は担保できない。 一旦それぞれの知識レベルを上げておいて、そして議論によってその質を平準化していく。 なかなかこれだけでも難しい作業だろう。 「なぜ今までのままではダメなのか」 いくら経営やコンサルが声高に言っても、現場には響かない。 自ら気が付いて、自分たち自身を変革していくからこそ、血が流れても骨で立てるのだ。 この「DX&サービス提供サブスクモデル」は、社内の一部署で完結する話では決してない。 そもそも全社に影響するし、企業文化の根底から覆ることとなるのだ。 それが結果的にCXということになるのだが、このフィクションストーリーをどう読むだろうか。 さすが現職コンサルタントが執筆しただけあって、「コンサルをこうやって使ってほしい」という側面としても描かれている。 ここはやはり前作含め2冊とも読んだ方がいいし、順番もこの順で読むことをお勧めしたい。 (2021/2/8)
Posted by 


