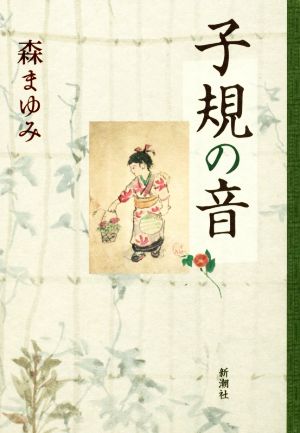
- 中古
- 書籍
- 書籍
- 1220-02-08
子規の音
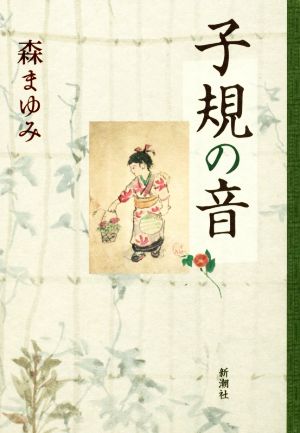
定価 ¥2,310
550円 定価より1,760円(76%)おトク
獲得ポイント5P
在庫なし
発送時期 1~5日以内に発送

商品詳細
| 内容紹介 | |
|---|---|
| 販売会社/発売会社 | 新潮社 |
| 発売年月日 | 2017/04/01 |
| JAN | 9784104100040 |
- 書籍
- 書籍
子規の音
商品が入荷した店舗:0店
店頭で購入可能な商品の入荷情報となります
ご来店の際には売り切れの場合もございます
オンラインストア上の価格と店頭価格は異なります
お電話やお問い合わせフォームでの在庫確認、お客様宅への発送やお取り置き・お取り寄せは行っておりません
子規の音
¥550
在庫なし
商品レビュー
3.3
4件のお客様レビュー
「子規の音」森まゆみ著、新潮社、2017.04.25 397p ¥2,268 C0095 (2024.06.30読了)(2024.06.21拝借) 【目次】 はじめに 一 松山の人―慶応三年~明治十六年 二 東京転々―明治十六~十九年 三 神田界隈―明治二十年 四 向島月香楼―...
「子規の音」森まゆみ著、新潮社、2017.04.25 397p ¥2,268 C0095 (2024.06.30読了)(2024.06.21拝借) 【目次】 はじめに 一 松山の人―慶応三年~明治十六年 二 東京転々―明治十六~十九年 三 神田界隈―明治二十年 四 向島月香楼―明治二十一年 五 本郷常盤会寄宿舎―明治二十二年 六 ベースボールとつくし採り―明治二十三年 七 菅笠の旅―明治二十四年 八 谷中天王寺町二十一番地―明治二十五年 九 下谷区上根岸八十八番地―明治二十五年 十 神田雉子町・日本新聞社―明治二十六年 十一 その人のあしあとふめば風薫る―明治二十六年夏 十二 はて知らずの記 宮城編―明治二十六年夏 十三 はて知らずの記 仙台・山形編―明治二十六年夏 十四 はて知らずの記 最上川・秋田編―明治二十六年夏 十五 「小日本」と中村不折―明治二十七年 十六 根岸農村風景―明治二十七年後半 十七 日清戦争従軍―明治二十八年 十八 神戸病院から須磨保養院―明治二十八年夏 十九 虚子と碧梧桐そして虹録―明治二十九年 二十 海嘯 三陸大津波―明治二十九年 二十一 「ほととぎす」創刊―明治三十年 二十二 短歌革新―明治三十一年 二十三 隣の女の子―明治三十二年 二十四 和歌に瘦せ俳句に痩せぬ夏男―明治三十三年 二十五 八石教会―明治三十四年 二十六 へちま咲く―明治三十五年 あとがき 参考文献 ☆関連図書(既読) 「仰臥漫録」正岡子規著、岩波文庫、1927.07.10 「松蘿玉液」正岡子規著、岩波文庫、1984.02.16 「坂の上の雲(一)」司馬遼太郎著、文春文庫、1978.01.25 (アマゾンより) 子規を読むことは、五感の解放である――。生誕150年のいま読むべき力作評伝。三十代前半で病に伏した正岡子規にとって、目に映る景色は根岸の小さな家の、わずか二十坪の小園だけだった。動くことのできない子規は、花の色や匂い、風の動きや雨音などで五感を極限まで鍛え、最期まで句や歌を作り続けた。幕末の松山から明治の東京まで足跡を丹念に辿り、日常の暮らしの中での姿を浮かび上がらせた新しい子規伝。
Posted by 
ザクザクとした短めの一文が連なる文章で、その一文にやたら知識が詰込まれている為、読むのに非常に時間がかかってしまった一冊。著者の本は初めてなのですが、この調子で鴎外だとか漱石も書かれているのなら、相当覚悟して取り掛からねば。片手間に読める代物では無かったです。 しかし著者の執念...
ザクザクとした短めの一文が連なる文章で、その一文にやたら知識が詰込まれている為、読むのに非常に時間がかかってしまった一冊。著者の本は初めてなのですが、この調子で鴎外だとか漱石も書かれているのなら、相当覚悟して取り掛からねば。片手間に読める代物では無かったです。 しかし著者の執念と云うか、熱心と呼ぶには重たすぎる取材力と膨大な知識。生まれ育った土地が舞台であるのも背を押しているのでしょうが、この濃密さは脱帽です。むしろもう少し書くべきだった位のあとがきにも驚きです。 子規の絵や、周囲を取り巻く環境、人の写真が載っているのが嬉しかったです。
Posted by 
子規を読むことは五感の解放である…この帯に惹かれて手にしてみたのだけど。確かに森まゆみさんはすごい。膨大な資料、文献を読み込んでの執筆だということは想像に難くない。けど、知識をあれもこれも詰め込んで備忘録的な面が否めなくて・・もう少し整理されたものを読みたかったというのが正直な...
子規を読むことは五感の解放である…この帯に惹かれて手にしてみたのだけど。確かに森まゆみさんはすごい。膨大な資料、文献を読み込んでの執筆だということは想像に難くない。けど、知識をあれもこれも詰め込んで備忘録的な面が否めなくて・・もう少し整理されたものを読みたかったというのが正直な感想。なので☆二つ。 ただ、それだけに細かな史実に関しては、へぇ~ということも山ほどあった。 愛媛出身の男子学生が東京などに進学するための学生寮。その前身が常磐会寄宿所で、伊予松山藩主久松家が旧藩の優れた若者を育成するためにつくった合宿所。明治21年に正岡子規が入っている。 この常磐会寄宿所、実は坪内逍遥が掛川藩の人に頼まれて学生の監督を引き受け3年ほど住んだあと、久松家が買い受けた・・そうな。ちなみに明治16年の地図を見ると「茶畑」だった、とか。 トルコが親日であることの根の一つにあげられる紀伊半島沖で座礁したエルトゥールル号事件。救助された乗組員を日本の軍艦がトルコ・イスタンブールまで送り届けたのは存じてましたが、その軍艦に秋山真之が乗り込んでいて、「世界は広くてよほど狭い」と思った、とか。 生誕150年を迎え、私の中で正岡子規がとてもホッとな今、細々とした知識の木の幹が太くなり、枝ぶりも随分広げてくれた一冊ではありました。
Posted by 



