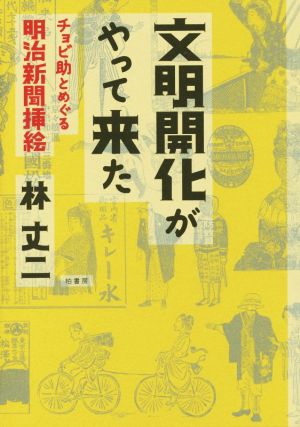
- 中古
- 店舗受取可
- 書籍
- 書籍
- 1216-01-10
文明開化がやってきた チョビ助とめぐる明治新聞挿絵
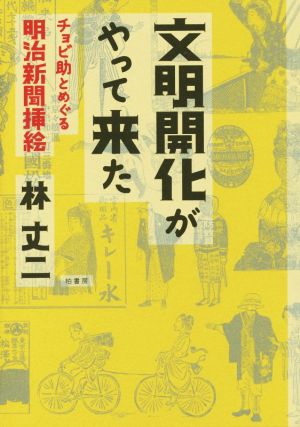
定価 ¥1,980
770円 定価より1,210円(61%)おトク
獲得ポイント7P
残り1点 ご注文はお早めに
発送時期 1~5日以内に発送
店舗受取サービス対応商品【送料無料】
店舗到着予定:3/1(日)~3/6(金)

店舗受取サービス対応商品
店舗受取なら1点でも送料無料!
店舗到着予定
3/1(日)~3/6(金)

商品詳細
| 内容紹介 | |
|---|---|
| 販売会社/発売会社 | 柏書房 |
| 発売年月日 | 2016/10/01 |
| JAN | 9784760147403 |
- 書籍
- 書籍
文明開化がやってきた
商品が入荷した店舗:0店
店頭で購入可能な商品の入荷情報となります
ご来店の際には売り切れの場合もございます
オンラインストア上の価格と店頭価格は異なります
お電話やお問い合わせフォームでの在庫確認、お客様宅への発送やお取り置き・お取り寄せは行っておりません
文明開化がやってきた
¥770
残り1点
ご注文はお早めに
商品レビュー
4
6件のお客様レビュー
明治時代の新聞挿絵等から当時の時流を読み解く雑学モノ。新聞小説の挿絵ならばまだ分かるけど、記事そのものに挿絵?…そうか、今の写真の代わりかぁ!と納得。浮世絵っぽい絵柄が面白いし、概して読みづらい広告も良い味出してる。文明開化、西洋化の勢いに必死に乗り遅れまいとする世情がよく分かる...
明治時代の新聞挿絵等から当時の時流を読み解く雑学モノ。新聞小説の挿絵ならばまだ分かるけど、記事そのものに挿絵?…そうか、今の写真の代わりかぁ!と納得。浮世絵っぽい絵柄が面白いし、概して読みづらい広告も良い味出してる。文明開化、西洋化の勢いに必死に乗り遅れまいとする世情がよく分かるし、なかなか読み応えのある1冊です。当時の女学生が"海老茶式部"と仇名されてたのがカッコ良くて面白いなぁと思いました。
Posted by 
エッセイストであり明治文化研究家による、明治時代の新聞挿絵の説明本。学者というよりマニアが書いているような内容で、体型的にまとまっているわけではなく、思いつきで書き進めているようであるが、詳細な分析がなされており、面白い。参考になった。
Posted by 
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
これは助かる。 時代小説を読んでいて、情景が浮かばないことがままあるもの。 たまに100歳以上の長寿の方がいらっしゃいますが、明治って100~150年位前の出来事。 なのにもう、別世界のように理解に乏しくなってしまっている。 明治20年ごろも日本は健康ブームだったそうで、当時はふっくらしていることが健康の証と、飲み物に砂糖を入れることが流行ったんですって。 だからこの挿絵では、砂糖壺が描かれているわけです。 はたして飲んでいたのはコーヒーか、紅茶か、それともチャクレッか? チャクレッまたはチョコラアトとはもちろん飲み物としてのチョコレートのこと。ハイカラですなあ。 明治の男性はちょん髷を切って頭が寂しくなったせいか、よく帽子をかぶっていたとか、防寒を兼ねて着物の中にシャツを着るのが流行ったとか、着物は袖や裾を押さえなければならないことが多いので、片手が使えない分、日本人はよく口でものをくわえるとか、目の付け所も面白いです。 そして妙に、貧乏人や病人や犬がリアルなんですね。 これは身近によく見かけることがあったからなのでしょうか。 “貧乏にも度はあるが、わずかなゆとりがあれば生活を楽しみたいと思うのは世の常。人の常。貧乏はしていても、気持ちは豊かに暮らしたい。” 着物が破れたら接ぎを当て、隙間風を防ぐため、または火鉢のひびをふさぐためにペタペタと反故紙を貼り、衝立代わりの屏風が破れれば人気役者の浮世絵を貼り、口の欠けた土瓶でお茶を入れ、おひつを机代わりに勉強する。 周りもみんな貧乏だったから、貧乏に悲壮感があまりない。 そして明治は今よりもはるかに銃社会。 明治元年から一年間で日本に陸揚げされたピストルは1万5千挺だったとか。 新聞に銃販売の広告も出ていました。 個人情報の概念のない時代、自転車盗難事件の記事が出た。 “上野の音楽学校へお通いなさる自転車嬢にたけ子(十九歳)とおっしゃる本郷弓町一丁目八番地の某氏の令嬢がある。” 父上の部分だけが伏せてあってもバレバレじゃろう。 娘に自転車を買い与えて音楽学校に入れるなんて上流社会の人であろうから、きっとなんらかの忖度があったのだろうけど。(正しくは斟酌) 近くて遠い国のような明治時代。 面白いなあと思う反面、どうして簡単に忘れてしまったのだろうとも思う。
Posted by 



