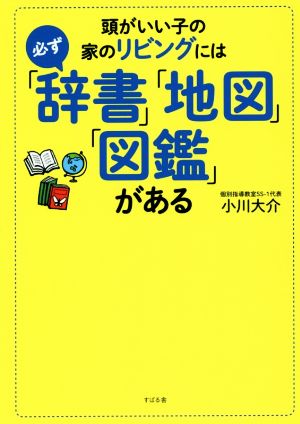
- 中古
- 店舗受取可
- 書籍
- 書籍
頭がいい子の家のリビングには必ず「辞書」「地図」「図鑑」がある
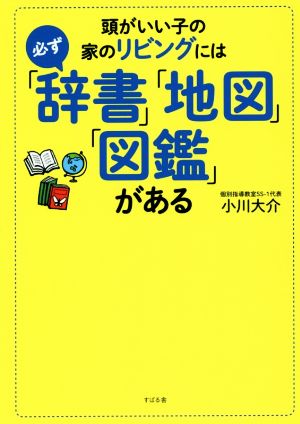
定価 ¥1,540
605円 定価より935円(60%)おトク
獲得ポイント5P
在庫あり
発送時期 1~5日以内に発送

店舗受取サービス対応商品
店舗受取なら1点でも送料無料!
店舗到着予定
12/18(水)~12/23(月)

商品詳細
| 内容紹介 | |
|---|---|
| 販売会社/発売会社 | すばる舎 |
| 発売年月日 | 2016/03/17 |
| JAN | 9784799104996 |


店舗受取サービス
対応商品
店舗受取なら1点でも送料無料!
さらにお買い物で使えるポイントがたまる
店舗到着予定
12/18(水)~12/23(月)
- 書籍
- 書籍
頭がいい子の家のリビングには必ず「辞書」「地図」「図鑑」がある
商品が入荷した店舗:0店
店頭で購入可能な商品の入荷情報となります
ご来店の際には売り切れの場合もございます
オンラインストア上の価格と店頭価格は異なります
お電話やお問い合わせフォームでの在庫確認、お客様宅への発送やお取り置き・お取り寄せは行っておりません
頭がいい子の家のリビングには必ず「辞書」「地図」「図鑑」がある
¥605
在庫あり
商品レビュー
4.3
39件のお客様レビュー
非常に参考になりました。 図鑑、地図、辞書はリビングにさりげなく増やしてコミュニケーションツールとして遊び道具として浸透させていきたいです。
Posted by 
あくまで辞書、地図、図鑑といったものは親と子どもを繋ぐツールであって、ただそこに置いておくだけでは、なにも意味を持たない。それらを通じて、子どもと積極的に関わりを持つ、親が本を手に取って読む姿を見せるということが大事であると思う。
Posted by 
「辞書」「地図」「図鑑」の良さは何となくわかっているつもりだったがが、どう活用すればいいのか、親はどう声がけするのがいいか、どんな辞書、地図、図鑑がいいのか具体的に挙げて、良い点を紹介している点がとてもわかりやすく、新しい発見がたくさんあった。
Posted by 


