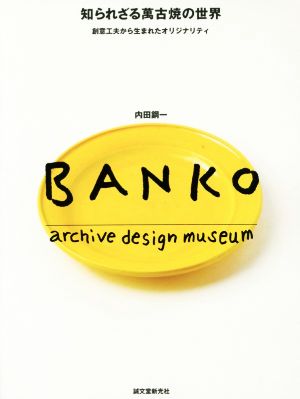
- 中古
- 書籍
- 書籍
- 1219-06-27
知られざる萬古焼の世界 創意工夫から生まれたオリジナリティ
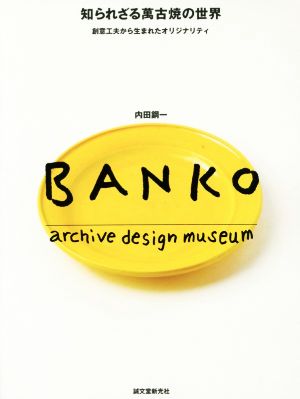
定価 ¥3,850
2,255円 定価より1,595円(41%)おトク
獲得ポイント20P
在庫わずか ご注文はお早めに
発送時期 1~5日以内に発送

商品詳細
| 内容紹介 | |
|---|---|
| 販売会社/発売会社 | 誠文堂新光社 |
| 発売年月日 | 2015/11/20 |
| JAN | 9784416715970 |
- 書籍
- 書籍
知られざる萬古焼の世界
商品が入荷した店舗:0店
店頭で購入可能な商品の入荷情報となります
ご来店の際には売り切れの場合もございます
オンラインストア上の価格と店頭価格は異なります
お電話やお問い合わせフォームでの在庫確認、お客様宅への発送やお取り置き・お取り寄せは行っておりません
知られざる萬古焼の世界
¥2,255
在庫わずか
ご注文はお早めに
商品レビュー
5
2件のお客様レビュー
明治期より三重県四日市市の地場産業として発展した萬古焼は、残念ながら現在は一般にあまり知られていない。 本書では他の有名窯場の陶磁器には無い萬古焼のオリジナリティに光を当て、スタイリストやデザイナーなど多角的な視点から、その魅力を語る。
Posted by 
ものすごく面白く、興味深い本です。まさに「知られざる」。。知らないことだらけだった! まず「万古焼とは何か」の数ページですでに興奮。かわいいイラストとともに、江戸時代中期からの四日市の歴史が書かれている。そして詳しい「万古焼の歩み」へと。素敵なイラストとともに、どんな変遷を経てき...
ものすごく面白く、興味深い本です。まさに「知られざる」。。知らないことだらけだった! まず「万古焼とは何か」の数ページですでに興奮。かわいいイラストとともに、江戸時代中期からの四日市の歴史が書かれている。そして詳しい「万古焼の歩み」へと。素敵なイラストとともに、どんな変遷を経てきたのかがとてもよくわかる。 もうここまででそうだったのか!のオンパレードで大興奮。 その次から、冒頭で触れた概略の詳しい内容に入っていきます。 まずは統制陶器・代用陶器について。昭和15年から終戦後しばらく、各窯場では生産数が管理され管理番号がつけられていたという。これが統制陶器。また、戦争が近づき金属が不足すると、金属製だった品を陶器で作る代用陶器が生まれる。ホーローの洗面器とかおろし器とか、やかんとかしびんとかね、すごく精巧に真似して作られていて面白い。 これらについてたっぷりビジュアルで見せたあとで、蒐集家の船橋健さんと対談(統制陶器を3300個も集めてるって!!!)。 88ページの内田さんのこの言葉が万古焼についてよく語ってるなと。 「もともと万古焼の歴史は、江戸期の古万古から始まったので、ほかの産地に比べて浅い。そして他産地との決定的な違いは、地元で原料となる土を大量に採取できないということ。でもだからこそ、試行錯誤と創意工夫が育まれた。一大窯業地じゃないけれど、流通うに便利な立地だったことで、さまざまな情報を取り入れながら生き残ってきたんです。 江戸期にさかのぼっても洒落気であったり、色づかいの奇抜さであったり、シノワズリのテイストだったり、ほかとは明らかに違う感覚がありました。そして昭和の時代にも、鯉の掛け花や貯金箱、細工ものの急須などは、まだ余裕のある時代の副産物だったとはいえ、ほかの周辺産地とは違う方向性を持って繋げていった。その流れが、今回統制品や代用品にも当てはまるとわかって、納得しましたし、面白かったです。」 (船橋さん、伊達に3300個持ってるわけじゃない! 笑) そのあとに続くカラーバリエーションというくくりで紹介される食器たちのカラフルで素敵なことといったら!! 万古焼にこんなにカラフルなお皿があるとは知らなかった!うっとり、見入ってしまいます。 なんと、それを使った高橋みどりさんのテーブルコーディネートもあります!素敵な!! ーーー そして後半は、万古焼のキーパーソンとして、秦秀雄さんと、日根野作三さんを取り上げます。 秦さんは北大路魯山人経営の高級料亭「星岡茶寮」の支配人を務めた、古美術評論家。晩年になって、誰も評価していなかった身辺の雑記に目を向け、その中でも特に、春山、泰山の万古急須を愛したという人。井伏鱒二「珍品堂主人」のモデルでもあるらしい。 いやー〜、こんな人が万古を評価していたとは、知らなかった〜。 気に入った急須の作り手、笹岡春山に、ろくろで急須を作ることを提案し、そのろくろ急須をについては「泰山」と名乗るようにと申し出た逸話とか。 急須問屋、各治さんへの「いい作家と巡り合えてうれしい」と認めたハガキが残っていたり。 各治の山本さんはこの本で内田さんと対談に応じており、そのころのことが生の声で伝わってくる。 そしてもう一人のキーパーソンが、日根野作三さん。戦後、陶磁器デザイナーという職業がまだ珍しかった時代にその先駆者として活躍し、やきものの発展に尽力した人。 これまたすんごい人がだったようで、豪快に、きびしく、若い作家やデザイナーを育てたそうだ。 デザイン画が残っているけど、すごく才能をかんじさせる。 あと「万古焼の系譜」として松岡製作所のストーンウェアが乗ってるけど、これがまたなんつー洗練された食器たちのなの! 北欧の食器にも通じる雰囲気。 ・・・とこのあたりまで読んで、期限切れ。図書館に返します。 あと、巻末では何とミナペルホネンの皆川さんと内山さんとの対談もあります! 素晴らしすぎる本です!!
Posted by 



