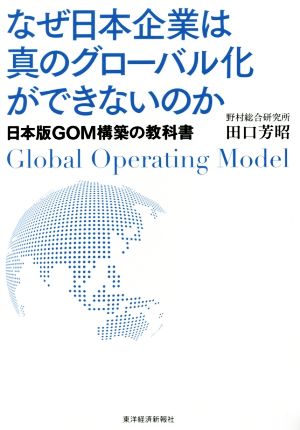
- 中古
- 店舗受取可
- 書籍
- 書籍
- 1209-02-02
なぜ日本企業は真のグローバル化ができないのか 日本版GOM構築の教科書
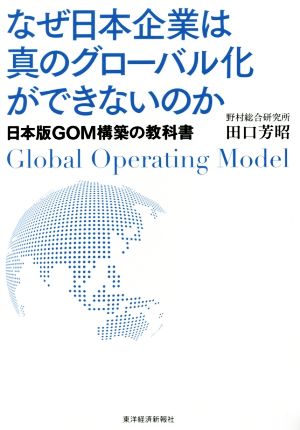
定価 ¥1,980
220円 定価より1,760円(88%)おトク
獲得ポイント2P
在庫わずか ご注文はお早めに
発送時期 1~5日以内に発送

店舗受取サービス対応商品
店舗受取なら1点でも送料無料!
店舗到着予定
2/21(金)~2/26(水)

商品詳細
| 内容紹介 | |
|---|---|
| 販売会社/発売会社 | 東洋経済新報社 |
| 発売年月日 | 2015/12/01 |
| JAN | 9784492557679 |


店舗受取サービス
対応商品
店舗受取なら1点でも送料無料!
さらにお買い物で使えるポイントがたまる
店舗到着予定
2/21(金)~2/26(水)
- 書籍
- 書籍
なぜ日本企業は真のグローバル化ができないのか
商品が入荷した店舗:0店
店頭で購入可能な商品の入荷情報となります
ご来店の際には売り切れの場合もございます
オンラインストア上の価格と店頭価格は異なります
お電話やお問い合わせフォームでの在庫確認、お客様宅への発送やお取り置き・お取り寄せは行っておりません
なぜ日本企業は真のグローバル化ができないのか
¥220
在庫わずか
ご注文はお早めに
商品レビュー
4
8件のお客様レビュー
真にグローバル組織を作るための具体的な提言がまとめられており、日々の業務を俯瞰して考えるきっかけをくれた。 弊部としてはGOM構築のためにグローバル本部を立ち上げたものの、①日本以外の特定の国のトップをグローバルヘッドとして新設役職に置いた結果(GOMモデル2に近いか)グロー...
真にグローバル組織を作るための具体的な提言がまとめられており、日々の業務を俯瞰して考えるきっかけをくれた。 弊部としてはGOM構築のためにグローバル本部を立ち上げたものの、①日本以外の特定の国のトップをグローバルヘッドとして新設役職に置いた結果(GOMモデル2に近いか)グローバルな事業内容がわかっておらず結局日本の既存本部が動かざるを得なくなった②海外人材がすぐに辞めてしまい立ち消えになってしまった(総括もろくにされていない)という経験があるため、 ①に対してはGOM構築の2条「情報をグループで公共財化する」によって1条「地域の壁を崩す」 を実現し地域横断的な方針立案ができるようにすること、②に対しては8条「長期にわたるGOM構築シナリオを保持する」によって人がいなくなって雲散霧消するのを回避するのが必要だなと感じた。 人材育成という観点では、p206「GOMを構築する人材を育成するには、「日本本社で入社後、10年間経理・財務畑を中心にキャリアを積んできました」という制度では困難である」というのが大変自分の耳に痛かった。ちょうど今年で同じ業務ひたすらやって10年になるわ、、勿論専門人材を目指すキャリアパスもあるのだが、今の興味関心としては全体感を持って仕事ができるようになりたいので、複数の業務を経験したいと感じている。その経験を踏まえて、キャリアのゴールとしてGOMのような経営・組織運営まで行くのか特定事業を横断的な視野で見るようになるのかは今後考えていきたい。 また駐在員依存からの脱却についてはローカル人材の育成と本部からのコミュニケーション強化、意思決定への巻き込みが必要だと感じた。本部からすると全体感がわかってなくて好きに言ってるだけ、ローカルからすると情報は落ちてこないし勝手に決められるし何も反映されないってなってるので、それゃ離れていくよねと。。というのを実現するには一旦駐在員を入れて、徐々にシフトしていくようにした方がいいと思うんだけどねえ。。(自分が駐在したい欲もありここは割り引いて検討) p191performance(数字面での業績)だけではなくbehavior(組織のミッションに根差した行動)を評価軸にするという点も、既に組織では目標設定に置かれてるので、自分自身の話として特定業務ばかり深掘りするのではなく全社的な方針を行動に移せる人材であることを示す為にも必要だと感じさせられた。昨年は既存業務を言い訳にして横串活動をあまりしてこなかったので心を入れ替えます。。 ITインフラの共通化による情報の公共財化については、とりあえずやってること見えるようにしようってだけでは意味がなくて、KPIをモニタリングする為に必要、という点も刺さった。まあ本部が何やってるかわからないってのが弊社の現状なので見える化だけでも意味はあるのだが、組織のゴールとしてはKPI の測定に使われるべきよね。 等々色々な点から広い視野で考えられ、よい機会になった。 あとはまとまった時間で読書できたので、デジタルデトックスになってすごくきもちよかった。。また時間作ろう。
Posted by 
題名は「なぜ日本企業は真のグローバル化ができないのか」であるが、本書の内容は、その問いに答えつつ、ではどうすれば?ということも論じている。それも、かなり骨太に。 自分なりに、本書からの学びを整理すると、下記の通り。 ■グローバル化の仕組みづくりは、単なる制度設計ではないし、ノウ...
題名は「なぜ日本企業は真のグローバル化ができないのか」であるが、本書の内容は、その問いに答えつつ、ではどうすれば?ということも論じている。それも、かなり骨太に。 自分なりに、本書からの学びを整理すると、下記の通り。 ■グローバル化の仕組みづくりは、単なる制度設計ではないし、ノウハウ的なものでもない。それは、経営の仕組みそのものだし、企業のガバナンスそのもの。従って、部分的に手をつけるといったいったものではなく、全体の改革が必要 ■時間がかかる。大きな改革と捉えるべきものであり、小手先の問題ではない。何代かの経営者が、取り組み続けて成果が出てくる、くらいに考えた方が良い ■やり方は各社各様。何を目指すのかによって、そもそも違うし、各社のビジネスやグローバル化の程度などによって、全く異なる 骨太で納得感は高いが、経営者でないと取り組めない問題が論じられている。
Posted by 
日本のグローバルの経営スタイルは「連邦経営」。多くの場合、地域/事業ごとに拠点を築き、それぞれが「自律的に」、事業規模を拡大することを意味する。 仕組み・システムとしての経営ではなく、「暗黙知を共有した人材(日本人)」に依存した経営モデル。 大半の日本企業のMission(何を...
日本のグローバルの経営スタイルは「連邦経営」。多くの場合、地域/事業ごとに拠点を築き、それぞれが「自律的に」、事業規模を拡大することを意味する。 仕組み・システムとしての経営ではなく、「暗黙知を共有した人材(日本人)」に依存した経営モデル。 大半の日本企業のMission(何を目的に)、Vision(どんな会社に)、Value(どんな価値観で)は自社ならではの尖った言葉で定義されていない。 グローバル企業のマネジメントの本質は、事業軸・地域軸・昨日軸の三次元の最適解を模索すること。 脱グローバルマネジメント1.0向けた問題・課題をまとめると、組織/ガバナンスの壁、業務/ITの壁、人材/ビジョンの壁がある。 ・組織/ガバナンスの壁→情報が事業・地域軸に集中し日本本社の機能軸は物理的にも、情報量でも現場からはなれてしまう。 ・業務/ITの壁→業務プロセスが標準化されていない、ITのグローバル化が困難なため、本社機能軸が自律的に情報をとれない、上がってきた数字を地域・事業間で比較できない(言葉の定義がバラバラなので。) ・人材/ビジョンの壁→日本人だけでは事業軸、地域軸、機能軸を支えられない状況になってきている。 守るべきもの(固有の競争力の源泉)を担保する仕組みを構築する
Posted by 
