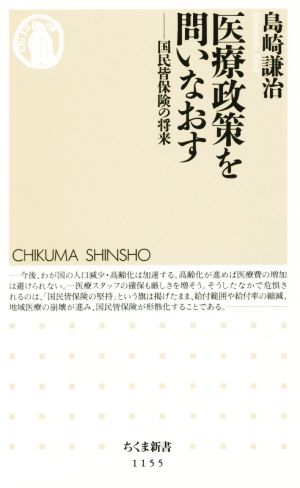
- 中古
- 書籍
- 新書
- 1226-25-06
医療政策を問いなおす 国民皆保険の将来 ちくま新書1155
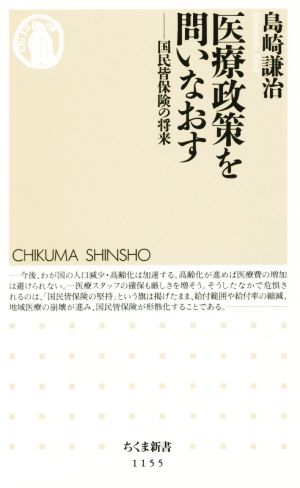
定価 ¥1,012
220円 定価より792円(78%)おトク
獲得ポイント2P
在庫なし
発送時期 1~5日以内に発送

商品詳細
| 内容紹介 | |
|---|---|
| 販売会社/発売会社 | 筑摩書房 |
| 発売年月日 | 2015/11/07 |
| JAN | 9784480068637 |
- 書籍
- 新書
医療政策を問いなおす
商品が入荷した店舗:0店
店頭で購入可能な商品の入荷情報となります
ご来店の際には売り切れの場合もございます
オンラインストア上の価格と店頭価格は異なります
お電話やお問い合わせフォームでの在庫確認、お客様宅への発送やお取り置き・お取り寄せは行っておりません
医療政策を問いなおす
¥220
在庫なし
商品レビュー
4.5
5件のお客様レビュー
医療政策の本だけあって、国民皆保険制度の理念や仕組み、問題点のみならず、需要側(国民構成と推移)と供給側(医療介護供給体制の変遷と現状)についても詳細に紐解いている。一冊読むと日本の医療制度の理念、変遷、仕組み、問題点がよく分かる。 やはりなんといっても悲しいのは(私個人の主張や...
医療政策の本だけあって、国民皆保険制度の理念や仕組み、問題点のみならず、需要側(国民構成と推移)と供給側(医療介護供給体制の変遷と現状)についても詳細に紐解いている。一冊読むと日本の医療制度の理念、変遷、仕組み、問題点がよく分かる。 やはりなんといっても悲しいのは(私個人の主張や解釈も混ざりますが) ・戦後急速に医療体制を整えるために民間に頼らざるを得なかったせいで多すぎる診療所や名ばかり急性期病床に医療費を吸い取られ続けている。 ・公的病床が3割程度しかない民間主体の医療供給体制のせいで診療報酬を持ってしか医療政策をコントロールできない。 ・1970年代に始まった高齢者バラマキ政策のツケを現在も払い続けている という点。金持ち(民間病院およびその代表である医師会)と多数派(高齢者)が民主主義を動かしていると考えるならばこれらは中々に解決困難な課題。
Posted by 
医療政策といった分野の知識・理解を深めたいと思いながらも、読み手の自分のアホさもあって、この分野の本ってなかなかとっつきづらく読み進むのが難しいものが多い。ところがこの本はかなり読みやすかった。 日本が誇る(?)国民皆保険として、医療保険制度を軸にこれまでをわかりやすく解説してく...
医療政策といった分野の知識・理解を深めたいと思いながらも、読み手の自分のアホさもあって、この分野の本ってなかなかとっつきづらく読み進むのが難しいものが多い。ところがこの本はかなり読みやすかった。 日本が誇る(?)国民皆保険として、医療保険制度を軸にこれまでをわかりやすく解説してくれ、そしてこの先の案を紹介してくれている。状況を解説するだけで予防線を張るかのように持論を披露してくれない本も多いけど、一歩踏み込んで著者なりの今後の方向性をしっかりと書いてくれているのも、見通しが利かない身としては視点が一つ得られるようでよい。 医療や介護の先行きってなかなか難しいものだし、財務省や経産省やらの経済発展ばかりに目を向け社会保障や健康・医療なんか二の次的な動きが目立ち暗澹たる気持ちにもなるし、国民皆保険も60年ほどで危うくなってきた感もあるけど、まだまだ保険制度をベースに現実と先行きを精緻に見通すことでできることはあるという希望のようなものも感じられる一冊だと思う。
Posted by 
『医療政策を問いなおす~国民皆保険の未来~』 島崎謙治 医療政策について、財源論、他国との制度の比較、現在の日本の医療政策の成立背景等がよくわかる。 個人的な興味関心は、職域医療政策である健康保険組合についてであるが、健康保険組合を論じる上では、そもそもの日本全体の制度について...
『医療政策を問いなおす~国民皆保険の未来~』 島崎謙治 医療政策について、財源論、他国との制度の比較、現在の日本の医療政策の成立背景等がよくわかる。 個人的な興味関心は、職域医療政策である健康保険組合についてであるが、健康保険組合を論じる上では、そもそもの日本全体の制度についても理解が必要であると感じ、本書を手に取った。 日本の医療政策として、社会保険方式(⇔租税方式)で国民皆保険(⇔アメリカのような一部保険)を実現しており、医療の提供においては現物給付方式(⇔償還払い方式)によって成り立っているということについて、それぞれの代替案や他国の制度の形を示しつつ、なぜそのような仕組みを取っているのかが詳説されている。個人的には、どうしても保険業界にいると、財源と給付について目が行きがちであったが、本書では現物給付方式を成立させている医療機関の供給サイドの仕組みや、現物給付方式にすることで民間医療機関が多いにもかかわらず、それらの経営原資を診療報酬に依存させ、実質的には政策誘導がしやすい形にしている(なっている)等の観点は新鮮であった。 また、社会保険方式の運営は、保険主義とイコールではないことなども、記載があったことは納得感がある。保険業界の身からすると、現代の保険商品のほとんどは応リスク負担保険料、つまり、一定のリスクに応じてその分保険料を負担するリスク細分化の商品設計になっているが、日本の社会保険は応能負担であり、個人のリスクにかかわらず、負担できる所得の有無によって、保険料が決定しているという点に、ちぐはぐさを感じざるを得ないが、ある意味、国民皆保険を達成するための方便として完璧な保険主義の遂行は不可能と認識しながらも運営でカバーしているという実態を改めて認識できた。 そうした中で、応リスク負担であるべきところを、応能負担にしていることにより、低リスク者から、高リスク者へ、高所得者から低所得者への所得移転がされることを理解した上で、そのような所得移転が容認されやすい一定顔の見える共同体として、カイシャ(職域)とムラ(地域)が現在の健康保険の基礎となったという点も、合点がいく。 一方で、高度経済成長期かつ人口ボーナスのある中で設計された日本の社会保障制度のほとんどが、人口減少社会と定常経済により、機能不全に陥っていることについて、課題点として挙げている。 そもそも、社会保険といいつつも、給付財源のうち保険料で賄われているのは5割であり、4割が公費、患者負担が1割となっているのは、保険業界の者か見ると明らかに保険制度とは言えないシロモノである。そして、もっと言えば公費で賄われているものの財源には、国債発行によるものも多くあり、明らかな給付過多である。後期高齢者の患者給付の異常な少なさ(十分な所得があるにもかかわらず、負担割合が少ないケースも散見されること)や、健康保険組合でも、後期高齢者医療制度への上納金が4割程度を占める等、世代間の格差が甚だしいというのが現状である。少子高齢化により、このままの仕組みであれば、社会保障制度の給付の財源割合はより、公費によって行くことも考えられる。社会保険方式を取りつつも、実態は税財源になりつつあるということが述べられている。その上でも、税財源確保のための消費税引き上げが急務であることなどの、政策提言も行われている。 本書の締めとして、そのような状況の中で、今以上に世代間格差が加速する前に、現状分析の下で理性的に議論することが求められる。社会保障制度は、寄木細工のように複雑な構造であり、部分最適が全体最適を意味しない。そのような中で、データを交えて真剣に議論するような土壌として、民主主義の成熟が欠かせないことが述べられており、そこに私も合意する。
Posted by 



