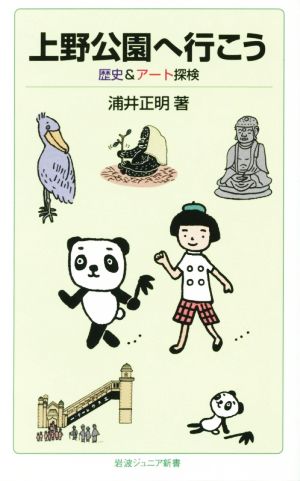
- 中古
- 書籍
- 新書
- 1226-06-02
上野公園へ行こう 歴史&アート探検 岩波ジュニア新書
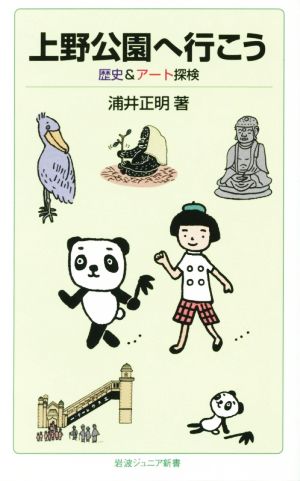
定価 ¥1,056
220円 定価より836円(79%)おトク
獲得ポイント2P
在庫なし
発送時期 1~5日以内に発送

商品詳細
| 内容紹介 | |
|---|---|
| 販売会社/発売会社 | 岩波書店 |
| 発売年月日 | 2015/07/24 |
| JAN | 9784005008032 |
- 書籍
- 新書
上野公園へ行こう 歴史&アート探検
商品が入荷した店舗:0店
店頭で購入可能な商品の入荷情報となります
ご来店の際には売り切れの場合もございます
オンラインストア上の価格と店頭価格は異なります
お電話やお問い合わせフォームでの在庫確認、お客様宅への発送やお取り置き・お取り寄せは行っておりません
上野公園へ行こう 歴史&アート探検
¥220
在庫なし
商品レビュー
2.8
7件のお客様レビュー
感想 懐の深い公園。芸術も教養も庶民の文化も。一見すると混沌としているが、経緯を知り現状を観察すれば全てが調和していることがわかる。
Posted by 
〇岩波ジュニア新書で「学校生活」を読む⑩ 浦井正明著『上野公園へ行こう 歴史&アート探検』(岩波ジュニア新書、2015) ・分 野:「学校生活」×「校外学習」 ・目 次: 序章 日本はじめてものがたり 第1章 江戸のなごり探検 第2章 天海と寛永寺からはじまった 第...
〇岩波ジュニア新書で「学校生活」を読む⑩ 浦井正明著『上野公園へ行こう 歴史&アート探検』(岩波ジュニア新書、2015) ・分 野:「学校生活」×「校外学習」 ・目 次: 序章 日本はじめてものがたり 第1章 江戸のなごり探検 第2章 天海と寛永寺からはじまった 第3章 合格大仏になったわけ 第4章 明治のなごり探検 第5章 西郷さんと彰義隊探検 第6章 二つの上野駅 第7章 美術館をめぐろう 第8章 博物館探検 第9章 上野動物園 第10章 東京文化会館 ・総 評 本書は、上野公園の魅力を、江戸時代から現代に至るまでの歴史を踏まえて紹介した本です。著者は、上野公園にある東叡山現龍寺の住職で、台東区文化財保護審議会委員も務めたことがある人物です。 上野公園と言えば、博物館や美術館などの文化施設が数多く存在し、都内の学校出身者であれば校外学習などで訪れた人も多いのではないでしょうか。また東京の観光名所の一つでもあり、上野動物園のパンダは非常に有名です。そんな見所満載の上野公園の全体像を解説したのが本書です。この本を読んで面白いなと思った点を、以下の3点にまとめます。 【POINT①】江戸時代の「上野」――江戸幕府と戦った天海の信念 江戸時代の「上野」は、徳川家の祈祷寺である寛永寺が建立された地でした。二代将軍の徳川秀忠が計画を立てた際、責任者となったのが天台宗の僧侶・天海です。彼は、寛永寺を徳川家のみの寺にしたいと考えていた幕府の反対を押し切り、誰もが参拝できる「庶民に開放された寺」にしました。その背景には、当時の江戸はまだ都市としての整備が進んでおらず、神社仏閣も少なかったため、江戸の庶民が気軽に参拝できる場所をつくりたいという天海の思いがありました。こうして上野は、庶民たちの“観光地”として、その歴史をスタートさせたのです。 【POINT②】明治時代の「上野」――近代化のシンボルとしての公園、そして博物館 明治新政府が誕生すると、徳川家にとって象徴的な場所であった上野=旧寛永寺の地を、近代化のシンボルとして「公園化」するという案が持ち上がります。やがてイギリスに留学していた官僚の町田久成が、上野に「博物館」を建設するという計画を提案し、了承されます。この時、モデルとなったのがフランスの王立植物園(ジャルダン・デ・プラント)で、博物館だけでなく動物園や植物園も併設する計画でした。その後、予算不足により、植物園は江戸時代からある小石川御薬園(現・小石川植物園)で間に合わせることになり、上野には博物館と動物園が建設されることになったのです。 【POINT③】 現代の「上野」――関係者が語る、その価値とは? 本書では「上野を愛する人たち」と題して、計6名の上野公園に関わる人たちのインタビューが掲載されています。この人たちが、上野公園の魅力として口をそろえて挙げるのが「自然」の存在です。即ち、上野公園には様々な種類の木々や不忍池といった「自然」があり、それと博物館などの文化施設が融合していることが、上野公園の魅力であると指摘しています。四季折々の景色が楽しめる名所として上野を整備した江戸時代の天海と、近代国家のシンボルとして上野に博物館を建てた明治新政府――両者の思いが合わさることによって、現代の上野公園の「魅力」が形作られたと言えるでしょう。 本書では、この他にも上野公園にまつわるエピソードが数多く紹介されています。この本を片手に上野公園を散策してみると、今まで何気なく通り過ぎていた建物にも様々な歴史があることに気づき、また違った景色を見ることができるでしょう。まだ上野公園に行ったことがない人はもちろん、既に上野公園に行ったことがある人にもオススメの一冊です。 (1298字)
Posted by 
『#上野公園へ行こう』 ほぼ日書評 Day466 夏休み中に散策しようと思い、借り出した資料だが、予定していた日は、台風やら何やらで、広範には歩き回れず、ただ、街歩きネタとしては、新書サイズ(岩波ジュニア文庫)ながら非常に充実した内容。 冒頭は、上野は「お初」ものが多い話。...
『#上野公園へ行こう』 ほぼ日書評 Day466 夏休み中に散策しようと思い、借り出した資料だが、予定していた日は、台風やら何やらで、広範には歩き回れず、ただ、街歩きネタとしては、新書サイズ(岩波ジュニア文庫)ながら非常に充実した内容。 冒頭は、上野は「お初」ものが多い話。 地下鉄開通ネタに続く、二つ目のエピソードは、日本(世界)初の「駅伝」について。大正6年の京都三条大橋から上野までの514kmを、23区間に分けて走るものだった。1人あたり、ほぼハーフマラソン、記録はどんなものだったのだろう? Wikipediaによれば、多少距離の表示が違うものの「関西組と関東組に分かれ京都の三条大橋を午後2時に出発し、東京の上野不忍池(しのばずのいけ)までの23区間、約508kmを昼夜問わず走り抜けるもので、先着の関東組がゴールに到着したのは翌々日の午前11時34分であった」とのこと。単純計算すると、フルマラソンを1時間50分ほどで走ることになる。ハーフとは言え、大正人、早い! 上野の五重塔、火災後、半年余りで再建はあり得ない? 実際にてっぺんまで登って確かめたのだと。命綱をつけたとは言え、生きた心地がしなかっただろう。そんな苦労をしながら、超短期「再建」謎はとけていないのだとか。 旧東京音楽学校奏楽堂、本書執筆当時(2015年頃)は閉鎖されていたが、近年公開され、月に数回演奏会も再開されているのは嬉しい限り。 芸大構内に残る、国内最後の赤煉瓦建築。実は関東大震災後に、強度を増すために全面モルタル塗りが施されたのを、後年、前野芸大教授が、自ら梯子を立て、学生の手伝いも得ながら、モルタルを剥がし、もとの赤煉瓦を掘り起こしたもの。 甲子園でも活躍した岩倉高校(鉄道専門学科を持つ)は、旧国鉄の前身となった(民間の)日本鉄道会社創立に尽力した(かつての500円札)岩倉具視の功績を讃える校名。 https://amzn.to/388MVhh
Posted by 



